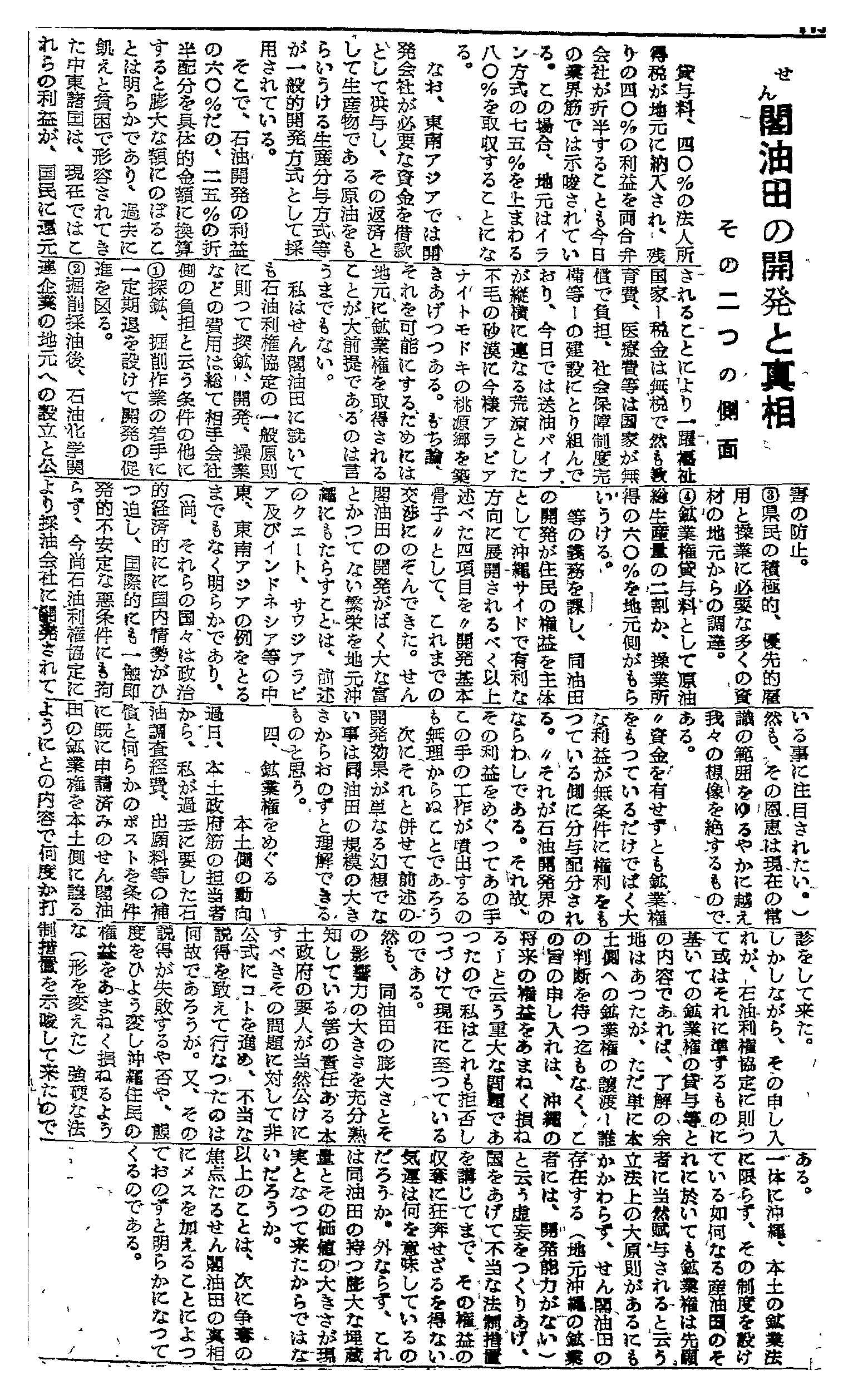キーワード検索
せん閣油田の開発と真相/ その二つの側面
原文表記
せん閣油田の開発と真相 その二つの側面
南西新報 昭和四十五年八月十四日
貸与料、四〇%の法人所得税が地元に納入され、残りの四〇%の利益を両合弁会社が折半することも今日の業界筋では示唆されている。この場合、地元はイラン方式の七五%を上まわる八〇%を取収することになる。
なお、東南アジアでは開発会社が必用な資金を借款として供与し、その返済として生産物である原油をもらいうける生産分与方式等が一般的開発方式として採用されている。
そこで、石油開発の利益の六〇%だの、二五%の折半配分を具体的金額に換算すると膨大な額にのぼることは明らかであり、過去に飢えと貧困で形容されてきた中東諸国は、現在ではこれらの利益が、国民に還元されることにより一躍福祉国家―税金は無税で然も教育費、医療費等は国家が無償で負担、社会保障制度完備等―の建設にとり組んでおり、今日では送油パイプが縦横に連なる荒涼とした不毛の砂漠に今様アラビアナイトモドキの桃源郷を築きあげつつある。もち論、それを可能にするためには地元に鉱業権を取得されることが大前提であるのは言うまでもない。
私はせん閣油田に就いても石油利権協定の一般原則に則つて探鉱、開発、操業などの費用は総て相手会社側の負担と云う条件の他に
①探鉱、掘削作業の着手に一定期退を設けて開発の促進を図る。
②掘削採油後、石油化学関連企業の地元への設立と公害の防止。
③県民の積極的、優先的雇用と操業に必要な多くの資材の地元からの調達。
④鉱業権貸与料として原油総生産量の二割か、操業所得の六〇%を地元側がもらいうける。
等の義務を課し、同油田の開発が住民の権益を主体として沖繩サイドで有利な方向に展開されるべく以上述べた四項目を〝開発基本骨子〟として、これまでの交渉にのぞんできた。せん閣油田の開発がばく大な富とかつてない繁栄を地元沖繩にもたらすことは、前述のクエート、サウジアラビア及びインドネシア等の中東、東南アジアの例をとるまでもなく明らかであり、(尚、それらの国々は政治的経済的にに国内情勢がひつ迫し、国際的にも一触即発的不安定な悪条件にも拘らず、今尚石油利権協定により採油会社に開発されている事に注目されたい。)然も、その恩恵は現在の常識の範囲をゆるやかに越え我々の想像を絶するものである。
〝資金を有せずとも鉱業権を持つているだけでばく大な利益が無条件に権利をもつている側に分与配分される。〟それが石油開発界のならわしである。それ故、その利益をめぐつてあの手この手の工作が噴出するのも無理からぬことであろう
次にそれと併せて前述の開発効果が単なる幻想でない事は同油田の規模の大きさからおのずと理解できるものと思う。
四、鉱業権をめぐる本土側の動向
過日、本土政府筋の担当者から、私が過去に要した石油調査経費、出願料等の補償と何らかのポストを条件に既に申請済みのせん閣油田の鉱業権を本土側に譲るようにとの内容で何度か打診をして来た。
しかしながら、その申し入れが、石油利権協定に則つて或はそれに準ずるものに基いての鉱業権の貸与等との内容であれば、了解の余地はあつたが、ただ単に本土側への鉱業権の譲渡―誰の判断を待つ迄もなく、この旨の申し入れは、沖繩の将来の権益をあまねく損ねる―と云う重大な問題であつたので私はこれも拒否しつづけて現在に至つているのである。
然も、同油田の膨大さとその影響力の大きさを充分熟知している筈の責任ある本土政府の要人が当然公けにすべきその問題に対して非公式にコトを進め、不当な説得を敢えて行つたのは何故であろうか。又、その説得が失敗するや否や、態度をひよう変し沖繩住民の権益をあまねく損ねるような(形を変えた)強硬な法制措置を示唆して来たのである。
一体に沖繩、本土の鉱業法に限らず、その制度を設けている如何なる産油国のそれに於いても鉱業権は先願者に当然賦与されると云う立法上の大原則があるにもかかわらず、せん閣油田の存在する(地元沖繩の鉱業者には、開発能力がない)と云う虚妄をつくりあげ、国をあげて不当な法制措置を講じてまで、その権益の収奪に狂奔せざるを得ない気運は何を意味しているのだろうか。外ならず、これは同油田の持つ膨大な埋蔵量とその価値の大きさが現実となつて来たからではないだろうか。
以上のことは、次に争奪の焦点たるせん閣油田の真相にメスを加えることによつておのずと明らかになつてくるのである。
現代仮名遣い表記
せん閣油田の開発と真相 その二つの側面
南西新報 昭和四十五年八月十四日
貸与料、四〇%の法人所得税が地元に納入され、残りの四〇%の利益を両合弁会社が折半することも今日の業界筋では示唆されている。この場合、地元はイラン方式の七五%を上まわる八〇%を取収することになる。
なお、東南アジアでは開発会社が必用な資金を借款として供与し、その返済として生産物である原油をもらいうける生産分与方式等が一般的開発方式として採用されている。
そこで、石油開発の利益の六〇%だの、二五%の折半配分を具体的金額に換算すると膨大な額にのぼることは明らかであり、過去に飢えと貧困で形容されてきた中東諸国は、現在ではこれらの利益が、国民に還元されることにより一躍福祉国家―税金は無税で然も教育費、医療費等は国家が無償で負担、社会保障制度完備等―の建設にとり組んでおり、今日では送油パイプが縦横に連なる荒涼とした不毛の砂漠に今様アラビアナイトモドキの桃源郷を築きあげつつある。もち論、それを可能にするためには、地元に鉱業権を取得されることが大前提であるのは言うまでもない。
私はせん閣油田に就いても石油利権協定の一般原則に則って、探鉱、開発、操業などの費用は総て相手会社側の負担と言う条件の他に、
①探鉱、掘削作業の着手に一定期退を設けて開発の促進を図る。
②掘削採油後、石油化学関連企業の地元への設立と公害の防止。
③県民の積極的、優先的雇用と操業に必要な多くの資材の地元からの調達。
④鉱業権貸与料として原油総生産量の二割か、操業所得の六〇%を地元側がもらいうける。
等の義務を課し、同油田の開発が住民の権益を主体として沖縄サイドで有利な方向に展開されるべく、以上述べた四項目を〝開発基本骨子〟として、これまでの交渉にのぞんできた。せん閣油田の開発がばく大な富とかつてない繁栄を地元沖縄にもたらすことは、前述のクエート、サウジアラビア及びインドネシア等の中東、東南アジアの例をとるまでもなく明らかであり(尚、それらの国々は政治的経済的に国内情勢がひっ迫し、国際的にも一触即発的不安定な悪条件にも拘らず、今尚石油利権協定により採油会社に開発されている事に注目されたい)、然も、その恩恵は現在の常識の範囲をゆるやかに越え、我々の想像を絶するものである。
〝資金を有せずとも鉱業権を持っているだけで、ばく大な利益が無条件に権利をもっている側に分与配分される〟。それが石油開発界のならわしである。それ故、その利益をめぐってあの手この手の工作が噴出するのも無理からぬことであろう。
次に、それと併せて、前述の開発効果が単なる幻想でない事は、同油田の規模の大きさからおのずと理解できるものと思う。
四、鉱業権をめぐる本土側の動向
過日、本土政府筋の担当者から、私が過去に要した石油調査経費、出願料等の補償と何らかのポストを条件に既に申請済みのせん閣油田の鉱業権を本土側に譲るようにとの内容で何度か打診をして来た。
しかしながら、その申し入れが、石油利権協定に則って、或はそれに準ずるものに基いての鉱業権の貸与等との内容であれば、了解の余地はあったが、ただ単に本土側への鉱業権の譲渡―誰の判断を待つ迄もなく、この旨の申し入れは、沖縄の将来の権益をあまねく損ねる―と言う重大な問題であったので、私はこれも拒否しつづけて現在に至っているのである。
然も、同油田の膨大さとその影響力の大きさを充分熟知している筈の責任ある本土政府の要人が、当然公けにすべきその問題に対して非公式にコトを進め、不当な説得を敢えて行ったのは何故であろうか。又、その説得が失敗するや否や、態度をひょう変し、沖縄住民の権益をあまねく損ねるような(形を変えた)強硬な法制措置を示唆して来たのである。
一体に沖縄、本土の鉱業法に限らず、その制度を設けている如何なる産油国のそれに於いても、鉱業権は先願者に当然賦与されると言う立法上の大原則があるにもかかわらず、せん閣油田の存在する(地元沖縄の鉱業者には、開発能力がない)と言う虚妄をつくりあげ、国をあげて不当な法制措置を講じてまで、その権益の収奪に狂奔せざるを得ない気運は何を意味しているのだろうか。外ならず、これは同油田の持つ膨大な埋蔵量とその価値の大きさが現実となって来たからではないだろうか。
以上のことは、次に争奪の焦点たるせん閣油田の真相にメスを加えることによっておのずと明らかになってくるのである。