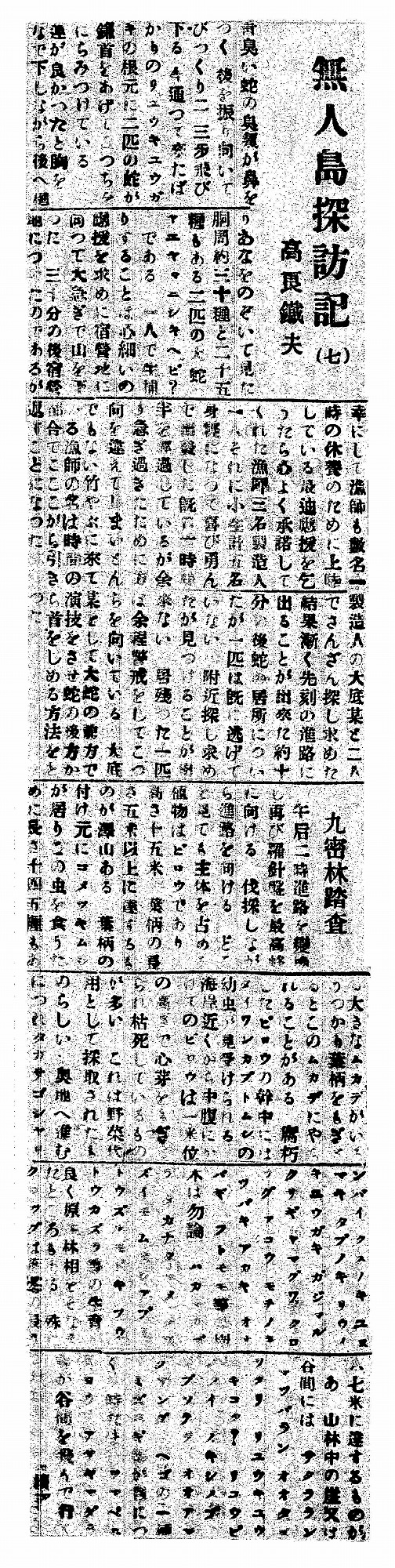キーワード検索
無人島探訪記(七)
原文表記
無人島探訪記(七)(★注・連載の六回目の筈である)
南琉タイムス 昭和二十五年五月十日
高 良 鐵 夫
靑臭い蛇の臭氣が鼻をつく 後を振り向いてびつくり二 三歩飛び下がる 今通つて來たばかりのリユウキユウガキの根元に二匹の蛇が鎌首をあげてこつちをにらみつけている
運が良かつたと胸をなで下しながら後へ廻りあなをのぞいて見た 胴周約三十糎と二十五糎もある二匹の大蛇 ヤエヤマニシキヘビ? である 一人で生捕りすることは心細いの應援を求めに宿營地に向つて大急ぎで山を下つた 三十分の後宿營地についたのであるが幸にして漁師も數名一時の休養のために上陸している最迪應援を乞うたら心よく承諾してくれた漁師三名製造人一人それに小生計五名身軽になつて喜び勇んで出發した既に一時間半を經過しているが余り急ぎ過きたために方向を違えてしまいとんでもない竹やぶに來ている漁師の名は時間の都合でここから引き返すことになつた
製造人の大底某と二人でさんざん深し求めた結果漸く先刻の進路に出ることが出來た約十分の後蛇の居所についたが一匹は既に逃げていない 附近探し求めたが見つけることが出來ない 居殘つた一匹は余程警戒をしてこつらを向いている 大底某をして大蛇の前方で演技をさせ蛇の後方から首をしめる方法をとつた
九密林調査
午后二時進路を變換し再び羅針盤を最高峰に向ける 伐採しながら進路を向ける どこを見ても主体を占める植物はビロウであり 高さ十五米 葉柄の長さ五米以上に達するものが澤山ある 葉柄の付け元にコメツキムシが居りこの虫を食うために長さ十四五糎もある大きなムカデがいるうつかりするとこのムカデにやられることがある 腐朽したビロウの幹中にはタイワンカブトムシの幼虫■見受けられる 海岸近くから中腹にかけてのビロウは一米位の高さで心芽をもぎとられ枯死しているものが多い これは野菜代用として採取されたものらしい 奥地へ進むにつれタカサゴシヤリンバイ クスノキ ユ■マキ タブノキ リウイキユウガキ ガジマル クサギ ヤマグワ クロツグ アコウ モチノキ ツバキ アカキ オオバギ フトモモ等 ■木は勿論 ハカ■■■■ タカナタマメ クワズイモ ム■■アブ■ トウズルモドキ フウトウカズラ等の生育 良く原生林相をそな■たところもある 殊にクロツグは■■の■■六七米に達するものが あ 山林中の崖又は谷間には サクララン マツバラン オオタニワタリ リユウキユウ■キコタ? リユウビ■■タイ ■キシメ■ ■ブソテツ オオア■ク■ン■ ヘゴの一種 ミズスギ等が目につく 時たま ツマベニ■ヨウ アサギマダラ が谷間を飛んで行
〈續〉
現代仮名遣い表記
無人島探訪記(六)
南琉タイムス 昭和二十五年五月十日
高 良 鐵 夫
青臭い蛇の臭気が鼻をつく。後を振り向いてびっくり、二、三歩飛び下がる。今通って来たばかりのリュウキュウガキの根元に二匹の蛇が鎌首をあげてこっちをにらみつけている。
運が良かったと胸をなで下しながら後へ廻り、あなをのぞいて見た。胴周約三十糎と二十五糎もある二匹の大蛇ヤエヤマニシキヘビ? である。 一人で生捕りすることは心細いの応援を求めに宿営地に向って大急ぎで山を下った。三十分の後宿営地についたのであるが、幸にして漁師も数名一時の休養のために上陸している最迪、応援を乞うたら心よく承諾してくれた。漁師三名、製造人一人、それに小生計五名身軽になって喜び勇んで出発した。既に一時間半を経過しているが、余り急ぎ過ぎたために方向を違えてしまい、とんでもない竹やぶに来ている。漁師の名は時間の都合でここから引き返すことになった。
製造人の大底某と二人でさんざん深し求めた結果、漸く先刻の進路に出ることが出来た。約十分の後蛇の居所についたが、一匹は既に逃げていない。附近探し求めたが見つけることが出来ない。居残った一匹は余程警戒をしてこちらを向いている。大底某をして大蛇の前方で演技をさせ、蛇の後方から首をしめる方法をとった。
九 密林調査
午後二時進路を変換し再び羅針盤を最高峰に向ける。伐採しながら進路を向ける。どこを見ても主体を占める植物はビロウであり、高さ十五米、 葉柄の長さ五米以上に達するものが沢山ある。葉柄の付け元にコメツキムシが居り、この虫を食うために長さ十四、五糎もある大きなムカデがいる。うっかりするとこのムカデにやられることがある。腐朽したビロウの幹中にはタイワンカブトムシの幼虫■見受けられる。海岸近くから中腹にかけてのビロウは一米位の高さで心芽をもぎとられ枯死しているものが多い。これは野菜代用として採取されたものらしい。奥地へ進むにつれタカサゴシャリンバイ、クスノキ、ユ■マキ、タブノキ、リュウキュウガキ、ガジュマル、クサギ、ヤマグワ、クロツグ、アコウ、モチノキ、ツバキ、アカキ、オオバギ、フトモモ等、■木は勿論ハカ■■■■、タカナタマメ、クワズイモ、ム■■アブ■、トウズルモドキ、フウトウカズラ等の生育■良く、原生林相をそな■たところもある。殊にクロツグは■■の■■六、七米に達するものが■あ■山林中の崖又は谷間にはサクララン、マツバラン、オオタニワタリ、リュウキュウ■キコタ? 、リユウビ■■タイ、■キシメ■、■ブソテツ、オオア■ク■ン■、ヘゴの一種、ミズスギ等が目につく。時たまツマベニ■ヨウ、アサギマダラ■が谷間を飛んで行く。
〈續〉