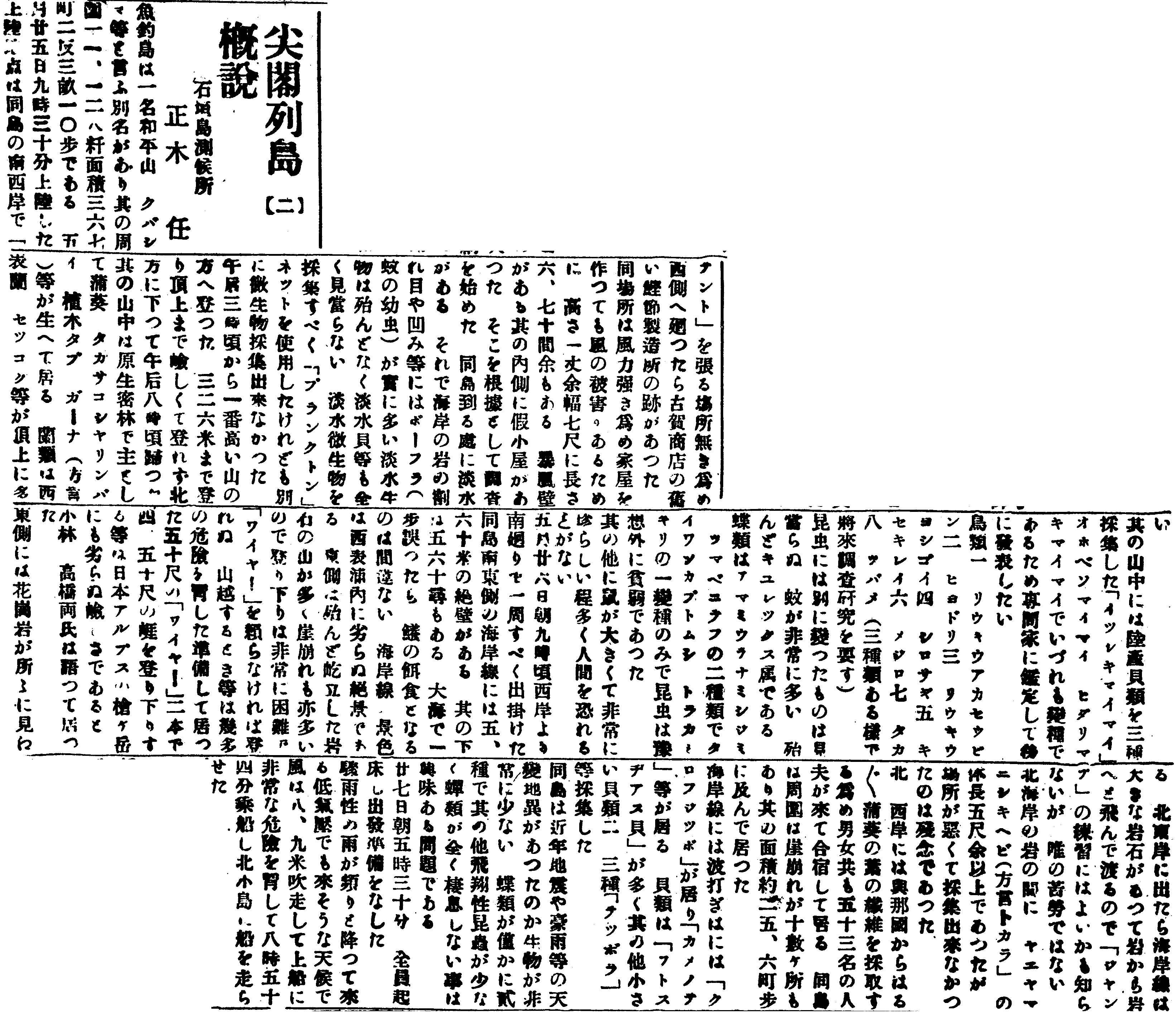キーワード検索
尖閣列島概説【二】
原文表記
尖閣列島概説【二】
海南時報 昭和十四年七月二日
石垣島測候所 正木 任
魚釣島は一名和平山 クバシマ等と言ふ別名があり其の周圍一一・一二八粁面積三六七町二反三畝一〇歩である 五月廿五日九時三十分上陸した 上陸地点は同島の南西岸で「テント」を張る場所無き爲西側へ廻つたら古賀商店の舊い鰹節製造所の跡があつた 同場所は風力強き爲め家屋を作つても風の被害■あるために 高さ一𠀋余幅七尺に長さ六、七十間余もある 暴風壁がある其の内側に假小屋があつた そこを根據として調査を始めた 同島到る處に淡水がある それで海岸の岩の割れ目や凹み等にはボーフラ(蚊の幼虫)が實に多い淡水生物は殆んどなく淡水貝等も全く見當らない 淡水微生物を採集すべく「プランクトン」ネツトを使用したけれども別に微生物採集出來なかつた 午后三時頃から一番高い山の方へ登つた 三二六米まで登り頂上まで嶮しくて登れず北方に下つて午后八時頃歸つた 其の山中は原生密林で主として蒲葵 タカサコシヤリンバイ 植木タブ ガーナ(方言)等が生へて居る 蘭類は西表蘭 セツコク等が頂上に多い
其の山中には陸産貝類を三種採集した「イツシキマイマイ」オホベソマイマイ ヒダリマキマイマイでいづれも變種であるため専門家に鑑定して後に発表したい
鳥類一 リウキウアカセウビン二 ヒヨドリ三 リウキウヨシゴイ四 シロサギ五 キセキレイ六 メジロ七 タカ八 ツバメ(三集類ある様で將來調査研究を要す)
昆虫には別に變つたものは見當らぬ 蚊が非常に多い 殆んどキユレツクス属である 蝶類はアマミウラナミシジミ ツマベニテフの二種類でタイワンカブトムシ トラカミキリの一變種のみで昆虫は予想外に貧弱であつた
其の他に鼠が大きくて非常に珍らしい程多く人間を恐れることがない
五月廿六日朝九時頃西岸より南廻り■一周すべく出掛けた同島南東側の海岸線には五、六十米の絶壁がある 其の下は五六十尋もある 大海で一歩誤つたら鱶の餌食となるのは間違いない 海岸線 景色は西表浦内に劣らぬ絶景である 東側は殆んど屹立した岩石の山が多く崖崩れも亦多いので登り下りは非常に困難■「ワイヤー」を頼らなければ登れぬ 山越する時等は幾多の危険を冒した準備して居つた五十尺の「ワイヤー」二本で四 五十尺の崕を登り下りする等は日本アルプスの槍ヶ岳にも劣らぬ嶮しさであると 小林 高橋両氏は語つて居つた
東側には花崗岩が所々に見える 北東岸に出たら海岸線は大きな岩石があつて岩から岩へと飛んで渡るので「ジヤンプ」の練習にはよいかも知らないが 唯の苦勞ではない
北海岸の岩の間に ヤエヤマニシキヘビ(方言トカラ)の体長五尺余以上であつたが 場所が惡くて採集出來なかつたのは殘念であつた
北 西岸には與那國からはるばる蒲葵の葉の繊維を採取する爲男女共も五十三名の人夫が來て合宿して居る 同島は周圍は崖崩れが十數ケ所もあり其の面積約二五、六町歩に及んで居つた
海岸線には波打ぎはには「クロフジツボ」が居り「カメノテ」等が居る 貝類は「フトスヂアス貝」が多く其の他小さい貝類二 三種「テツボラ」等採集した
同島は近年地震や豪雨等の天變地異があつたのか生物が非常に少ない 蝶類が僅かに弎種で其の他飛翔性昆蟲が少なく蟬類が全く棲息しない事は興味ある問題である
廿七日朝五時三十分 全員起床し出發準備をなした
驟雨性の雨が頻りと降つて來る低氣壓でも來そうな天候で風は八、九米吹走して上船に非常な危險を冒して八時五十四分乘船し北小島に船を走らせた
現代仮名遣い表記
尖閣列島概説【二】
海南時報 昭和十四年七月二日
石垣島測候所 正木 任
魚釣島は一名和平山、クバシマ等と言う別名があり、其の周囲一一・一二八粁、面積三六七町二反三畝一〇歩である。五月二十五日九時三十分上陸した。上陸地点は同島の南西岸で、「テント」を張る場所無き為西側へ廻ったら古賀商店の旧い鰹節製造所の跡があった。同場所は風力強き為め家屋を作っても風の被害■あるために、高さ一𠀋余幅七尺に長さ六、七十間余もある暴風壁がある。其の内側に仮小屋があった。そこを根拠として調査を始めた。同島到る処に淡水がある。それで海岸の岩の割れ目や凹み等にはボーフラ(蚊の幼虫)が実に多い。淡水生物は殆んどなく、淡水貝等も全く見当らない。淡水微生物を採集すべく「プランクトン」ネットを使用したけれども別に微生物採集出来なかった。午後三時頃から一番高い山の方へ登った。三二六米まで登り頂上まで険しくて登れず北方に下って午後八時頃帰った。其の山中は原生密林で主として蒲葵、タカサゴシャリンバイ、植木タブ、ガーナ(方言)等が生えて居る。蘭類は西表蘭、セッコク等が頂上に多い。
其の山中には陸産貝類を三種採集した。「イッシキマイマイ」、オホベソマイマイ、ヒダリマキマイマイで、いづれも変種であるため専門家に鑑定して後に発表したい。
鳥類一 リュウキュウアカショウビン、二 ヒヨドリ、三 リュウキュウヨシゴイ、四 シロサギ、五 キセキレイ、六 メジロ、七 タカ、八 ツバメ(三集類ある様で将来調査研究を要す)
昆虫には別に変ったものは見当らぬ。蚊が非常に多い。殆んどキュレックス属である。蝶類はアマミウラナミシジミ、ツマベニチョウの二種類で、タイワンカブトムシ、トラカミキリの一変種のみで昆虫は予想外に貧弱であった。
其の他に鼠が大きくて非常に珍らしい程多く人間を恐れることがない。
五月二十六日朝九時頃西岸より南廻り■一周すべく出掛けた。同島南東側の海岸線には五、六十米の絶壁がある。其の下は五、六十尋もある大海で、一歩誤ったら鱶の餌食となるのは間違いない。海岸線、景色は西表浦内に劣らぬ絶景である。東側は殆んど屹立した岩石の山が多く、崖崩れも亦多いので登り下りは非常に困難■「ワイヤー」を頼らなければ登れぬ。 山越する時等は幾多の危険を冒した。準備して居った五十尺の「ワイヤー」二本で四、五十尺の崖を登り下りする等は日本アルプスの槍ヶ岳にも劣らぬ険しさであると、小林・高橋両氏は語って居った。
東側には花崗岩が所々に見える。北東岸に出たら海岸線は大きな岩石があって岩から岩へと飛んで渡るので「ジャンプ」の練習にはよいかも知らないが、唯の苦労ではない。
北海岸の岩の間に、ヤエヤマニシキヘビ(方言トカラ)の体長五尺余以上であったが、場所が悪くて採集出来なかったのは残念であった。
北西岸には与那国からはるばる蒲葵の葉の繊維を採取する為男女共も五十三名の人夫が来て合宿して居る。同島は周囲は崖崩れが十数ヶ所もあり其の面積約二五、六町歩に及んで居った。
海岸線には波打ぎわには「クロフジツボ」が居り「カメノテ」等が居る。貝類は「フトスヂアス貝」が多く、其の他小さい貝類二、三種「テツボラ」等採集した。
同島は近年地震や豪雨等の天変地異があったのか生物が非常に少ない。 蝶類が僅かに二種で其の他飛翔性昆虫が少なく、蟬類が全く棲息しない事は興味ある問題である。
二十七日朝五時三十分、全員起床し出発準備をなした。
驟雨性の雨が頻りと降って来る。低気圧でも来そうな天候で風は八、九米吹走して上船に非常な危険を冒して、八時五十四分乗船し北小島に船を走らせた。