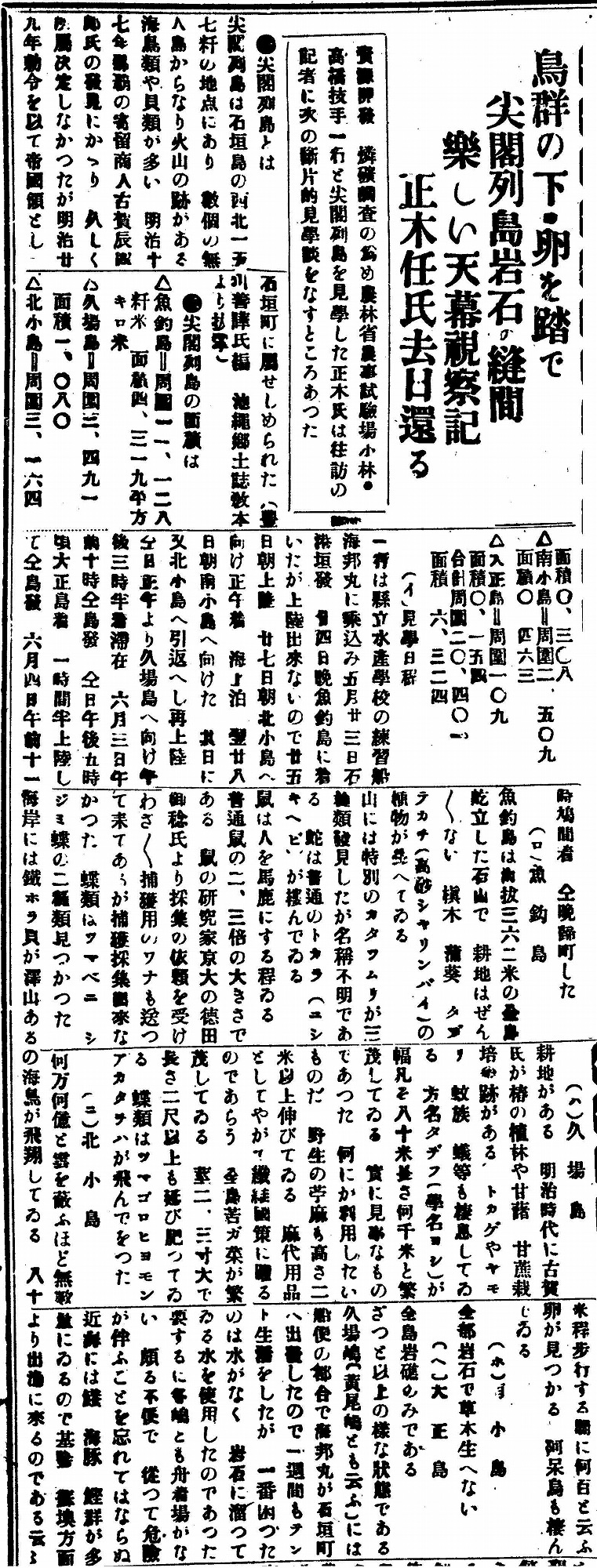キーワード検索
鳥群の下・卵を踏で尖閣列島岩石の縫間
原文表記
鳥群の下・卵を踏で尖閣列島岩石の縫間
樂しい天幕視察記正木任氏去日還る
先嶋朝日新聞 昭和十四年六月十四日
●尖閣列島とは
尖閣列島は石垣島の西北一五七粁の地点にあり 數個の無人島からなり火山の跡がある 海鳥類や貝類が多い 明治十七年那覇の寄留商人古賀辰四郞氏の發見にかゝり 久しく所属決定しなかったが明治廿九年勅令を以て帝國領とし石垣町に属せしめられた(豊川善曄氏編 沖縄郷土誌敎本より拔■)
●尖閣列島の面積は
◁魚釣島=周圍一一、一二八粁米 面積四、三一九平方キロ米
◁久場島=周圍三、四九一 面積一、〇八〇
◁北小島=周圍三、一六四 面積〇、三〇八
◁南小島=周圍二、五〇九 面積〇、四六三
◁大正島=周圍一〇九 面積〇、一五四
合計周圍二〇、四〇一
面積 六、三二四
(イ)見學日程
一行は縣立水産學校の練習船海邦丸に乘込み五月廿三日石垣港發 ■四日晩魚釣島に着いたが上陸出來ないので廿五日朝上陸 廿七日朝北小島へ向け正午着 海上泊 翌廿八日朝南小島へ向けた 其日に又北小島へ引返へし再上陸 仝日正午より久葉島へ向け午後三時半着滯在 六月三日午前十時仝島發 仝日午後五時頃大正島着 一時間半上陸して仝島發 六月四日午前十一時鳩間着 仝晩歸町した
(ロ)魚 鈎 島
魚釣島は海拔三六二米の全島屹立した石山で 耕地はぜんぜんない 槇木蒲葵、タブテカチ(高砂シヤリンバイ)の植物が■えてゐる 山には特別のカタツムリが三■類發見したが名稱不明である 蛇は普通のトカラ(ニシキヘビ)が棲んでゐる 鼠は人を馬鹿にする程ゐる 普通鼠の二、三倍の大きさである 鼠の研究家京大の徳田御稔氏より採集の依頼を受けわざわざ浦獲用のワナも送つて來てあ■が捕獲採集出來なかつた 蝶類はツマベニ シジミ蝶の二種類見つかつた 海岸には鐡ホラ貝が澤山ある
(ハ)久 場 島
耕地がある 明治時代に古賀氏が椿の植林や甘藷 甘蔗栽培跡がある トカゲやヤモリ 蚊族 蟻等も棲息してゐる 方名タデフ(學名ヨシ)が幅凡そ八十米長さ何千米と繁茂してゐる 實に見事なものであつた 何にか利用したいものだ 野生の苧麻も高さ二米以上伸びてゐる 麻代用品としてやがて纖維國策に躍るのであらう 全島苦ガ莱が繁茂してゐる 莖 二、三寸大で長さ二尺以上も延び肥つてゐる 蝶類はツマゴロヒヨモンアカタチハが飛んでをつた
(ニ)北 小 島
何万何億と雲を蔽ふほど無數の海鳥が飛翔してゐる 八十米程歩行する間に何百と云ふ卵が見つかる 阿呆鳥も棲んでゐる
(ホ)南 小 島
全部岩石で草木生へない
(ヘ)大 正 島
全島岩礁のみである
ざつと以上の様な状態である 久場嶋(黄尾嶋とも云ふ)には船便の都合で海邦丸が石垣町へ出發したので一週間もテント生活をしたが 一番困つたのは水がなく 岩石に溜つてゐる水を使用したのであつた 要するに各嶋とも舟着場がない 頗る不便で 従って危險が伴ふことを忘れてはならぬ 近海には鱶 海豚 鰹群が多量にゐるので基隆 蘇墺方面より出漁に來るのである云ふ
現代仮名遣い表記
鳥群の下・卵を踏で尖閣列島岩石の縫間
楽しい天幕視察記正木任氏去日還る
先嶋朝日新聞 昭和十四年六月十四日
●尖閣列島とは
尖閣列島は石垣島の西北一五七粁の地点にあり、数個の無人島からなり火山の跡がある。海鳥類や貝類が多い。明治十七年那覇の寄留商人古賀辰四郞氏の発見にかゝり、久しく所属決定しなかったが、明治二十九年勅令を以て帝国領とし石垣町に属せしめられた(豊川善曄氏編 沖縄郷土誌教本より抜■)。
●尖閣列島の面積は
◁魚釣島=周囲一一、一二八粁米 面積四、三一九平方キロ米
◁久場島=周囲三、四九一 面積一、〇八〇
◁北小島=周囲三、一六四 面積〇、三〇八
◁南小島=周囲二、五〇九 面積〇、四六三
◁大正島=周囲一〇九 面積〇、一五四
合計周囲二〇、四〇一 面積 六、三二四
(イ)見学日程
一行は県立水産学校の練習船海邦丸に乗込み五月二十三日石垣港発 ■四日晩魚釣島に着いたが上陸出来ないので二十五日朝上陸、二十七日朝北小島へ向け正午着、海上泊、翌二十八日朝南小島へ向けた。其日に又北小島へ引返えし再上陸、同日正午より久葉島へ向け午後三時半着滞在。 六月三日午前十時同島発、同日午後五時頃大正島着。一時間半上陸して同島発。六月四日午前十一時鳩間着、同晩帰町した。
(ロ)魚 釣 島、
魚釣島は海抜三六二米の全島屹立した石山で、耕地はぜんぜんない。槇木、 蒲葵、タブテカチ(高砂シャリンバイ)の植物が■えている。山には特別のカタツムリが三■類発見したが名称不明である。蛇は普通のトカラ(ニシキヘビ)が棲んでいる。鼠は人を馬鹿にする程いる。普通鼠の二、三倍の大きさである。鼠の研究家京大の徳田御稔氏より採集の依頼を受け、わざわざ浦獲用のワナも送って来てあ■が捕獲採集出来なかった。蝶類はツマベニ、シジミ蝶の二種類見つかった。海岸には鉄ホラ貝が沢山ある。
(ハ)久 場 島
耕地がある。明治時代に古賀氏が椿の植林や甘藷、甘蔗栽培跡がある。トカゲやヤモリ、蚊族、蟻等も棲息している。方名タデフ(学名ヨシ)が幅凡そ八十米、長さ何千米と繁茂している。実に見事なものであった。何にか利用したいものだ。野生の苧麻も高さ二米以上伸びている。麻代用品としてやがて繊維国策に躍るのであろう。全島苦が莱が繁茂している。茎 二、三寸大で長さ二尺以上も延び肥っている。蝶類はツマゴロヒョモン、アカタチハが飛んでおった。
(ニ)北 小 島
何万何億と雲を蔽うほど無数の海鳥が飛翔している。八十米程歩行する間に何百と言う卵が見つかる。阿呆鳥も棲んでいる。
(ホ)南 小 島
全部岩石で草木生えない。
(ヘ)大 正 島
全島岩礁のみである。
ざっと以上の様な状態である。久場島(黄尾島とも言う)には船便の都合で海邦丸が石垣町へ出発したので、一週間もテント生活をしたが、一番困ったのは水がなく、岩石に溜っている水を使用したのであった。要するに各島とも舟着場がない。頗る不便で、従って危険が伴うことを忘れてはならぬ。近海には鱶、海豚、鰹群が多量にいるので基隆、蘇墺方面より出漁に来るのである言う。