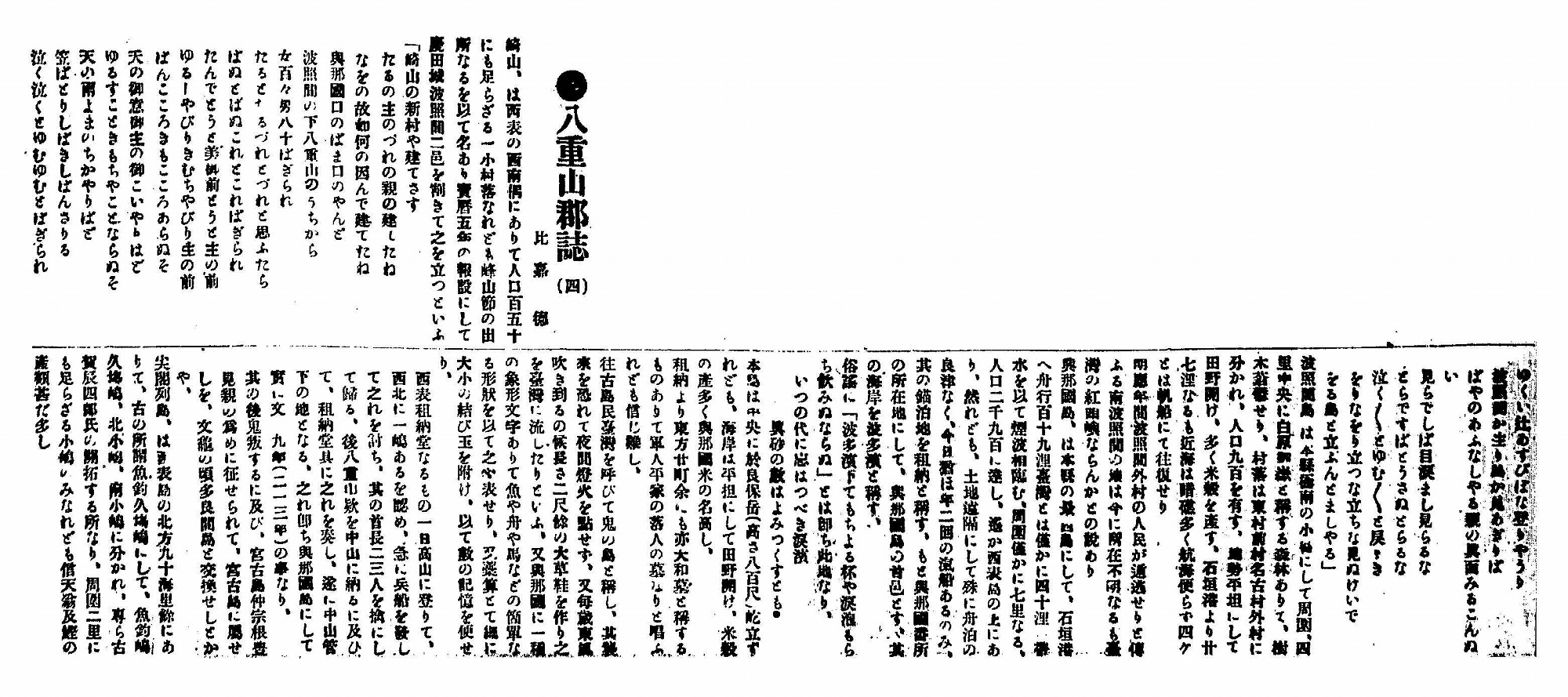キーワード検索
八重山郡誌(四)
原文表記
八重山郡誌(四)
沖繩毎日新聞 明治四十四年一月二十五日
比 嘉 徳
崎山、は西表の西南隅にありて人口百五十にも足らざる一小村落なれども崎山節の出所なるを以て名あり寶暦五年の報設にして慶田城波照間二邑を割きて之を立つといふ
「崎山の新村や建てさす
たるの主のづれの親の建てたね
なをの故如何の困んで建てたね
與那國口のばま口のやんど
波照間の下八重山のうちから
女百々男八十ばぎられ
たるとたるづれとづれと思ふたら
ばぬとばぬこれとこればぎられ
たんでとうと美御前とうと主の前
ゆるしやびりきむちやびり主の前
ばんこころきもこころあらぬそ
天の御意御主の御こいやりはど
ゆるすこときもちやことならぬそ
天の雨よまのちかやりばど
笠ばとりしばきしぱんさりる
泣く泣くとゆむゆむとばぎられ
ゆくい辻あすびぼな登りやうり
波照間か生り島か見あぎりば
ばやのあふなしやる親の眞面みるこんぬい
見らでしば目涙まし見らるな
とらですばとうさぬとらるな
泣くなくとゆむゆむと戻りき
をりなをり立つな立ちな見ぬけいで
をる島と立ふんとましやる」
波照間島は本縣極南の小嶋にして周圍、四里中央に白原御獄と稱する森林ありて、樹木蓊鬱せり、村落は東村前村名古村外村に分かれ、人口九百を有す、地勢平坦にして田野開け、多く米糓を産す、石垣港より廿七浬なるも近海は暗礁多く航海便らず四ヶとは帆船にて往復せり
明應年間波照間外村の人民が遁逃せりと傳ふる南波照間の地は今に所在不明なるも臺灣の紅頭嶼ならんかとの説あり
與那國島、は本縣の最西島にして、石垣港へ舟行百十九浬臺灣とは僅かに四十浬
帶水を以て煙波相臨む、周圍僅かに七里なる、人口二千九百に達し、遥か西表島の上にあり、然れども、土地遠隔にして殊に舟泊の良津なく、今日猶ほ年二回の滊船あるのみ、其の錨泊地を租納と稱す、もと與那國番所の所在地にして、與那國島の首邑とす、其の海岸を波多濱と稱す、
俗謡に「波多濱下てもちよる杯や涙泡もらち飮みぬならぬ」とは即ち此地なり、
いつの代に忘はつべき涙濱
眞砂の數はよみつくすとも
本島は中央に於良保岳(高さ八百尺)屹立すれども、海岸は平坦にして田野開け、米穀の産多く與那國米の名高し、
租納より東方廿町余にも亦大和墓と稱するものありて軍人平家の落人の墓なりと唱ふれども信じ難し、
往古島民臺灣を呼びて鬼の島と稱し、其襲來を恐れて夜間燈火を點せず、又毎歳東風吹き到るの候長さ二尺餘の大草鞋を作り之を臺灣に流したりといふ、又與那國に一種の象形文字ありて魚や舟や馬などの簡單なる形狀を以て之■表せり、又藁算とて繩に大小の結び玉を附け、以て數の記録を便せり、
西表租納堂なるもの一日高山に登りて、西北に一嶋あるを認め、急に兵船を發して之れを討ち、其の首長二三人を擒にして歸る、後八重山款を中山に納るに及ひて、租納堂具に之れを奏し、遂に中山管下の地となる、之れ即ち與那國島にして實に文■九年(二一三年)の事なり、
其の後鬼叛するに及び、宮古島仲宗根豊見親の爲めに征せられて、宮古島に属せしを、文龜の頃多良間島と交換せしとかや、
尖閣列島、は西表島の北方九十海里餘にありて、古の所謂魚釣久場島にして、魚釣島久葉嶋、北小嶋、南小嶋に分かれ、專ら古賀辰四郞氏の開拓する所なり、周圍二里にも足らざる小嶋のみなれども信天翁及鰹の産額甚だ多し
現代仮名遣い表記
八重山郡誌(四)
沖繩毎日新聞 明治四十四年一月二十五日
比 嘉 徳
崎山、は西表の西南隅にありて、人口百五十にも足らざる一小村落なれども、崎山節の出所なるを以て名あり。寶暦五年の■設にして慶田城波照間二邑を割きて之を立つという。
「崎山の新村や建てさす
たるの主のづれの親の建てたね
なをの故如何の困んで建てたね
與那國口のばま口のやんど
波照間の下八重山のうちから
女百々男八十ばぎられ
たるとたるづれとづれと思ふたら
ばぬとばぬこれとこればぎられ
たんでとうと美御前とうと主の前
ゆるしやびりきむちやびり主の前
ばんこころきもこころあらぬそ
天の御意御主の御こいやりはど
ゆるすこときもちやことならぬそ
天の雨よまのちかやりばど
笠ばとりしばきしぱんさりる
泣く泣くとゆむゆむとばぎられ
ゆくい辻あすびぼな登りやうり
波照間か生り島ゆ見あぎりば
ばやのあふなしやる親の真面みるこんぬい
見らでしば目涙まし見らるな
とらですばとうさぬとらるな
泣くなくとゆむゆむと戻りき
をりなをり立つな立ちな見ぬけいで
をる島と立ふんとましやる」
波照間島は本県極南の小島にして周囲四里、中央に白原御獄と称する森林ありて、樹木蓊鬱せり。村落は東村、前村、名古村、外村に分かれ、人口九百を有す。地勢平坦にして田野開け、多く米穀を産す。石垣港より二十七浬なるも近海は暗礁多く航海便らず、四ケとは帆船にて往復せり。
明応年間、波照間外村の人民が遁逃せりと伝うる南波照間の地は今に所在不明なるも、台湾の紅頭嶼ならんかとの説あり。
与那国島、は本県の最西島にして、石垣港へ舟行百十九浬、台湾とは僅かに四十浬。
帯水を以て煙波相臨む、周囲僅かに七里なる。人口二千九百に達し、遥か西表島の上にあり。然れども、土地遠隔にして殊に舟泊の良津なく、今日猶お年二回の汽船あるのみ。其の錨泊地を租納と称す。もと与那国番所の所在地にして、与那国島の首邑とす。其の海岸を波多浜と称す。
俗謡に「波多濱下てもちよる杯や涙泡もらち飲みぬならぬ」とは即ち此地なり。
いつの代に忘はつべき涙濱
眞砂の數はよみつくすとも
本島は中央に於良保岳(高さ八百尺)屹立すれども、海岸は平坦にして田野開け、米穀の産多く与那国米の名高し。
租納より東方二十町余にも亦大和墓と称するものありて■人平家の落人の墓なりと唱うれども信じ難し。
往古島民台湾を呼びて鬼の島と称し、其襲来を恐れて夜間燈火を点せず、又毎年東風吹き到るの候、長さ二尺余の大草鞋を作り之を台湾に流したりという。又与那国に一種の象形文字ありて、魚や舟や馬などの簡単なる形状を以て之■表せり。又藁算とて縄に大小の結び玉を附け、以て数の記録を便せり。
西表租納堂なるもの一日高山に登りて、西北に一島あるを認め、急に兵船を発して之れを討ち、其の首長二、三人を擒にして帰る。後八重山款を中山に納るに及びて、租納堂具に之れを奏し、遂に中山管下の地となる。之れ即ち与那国島にして実に文■九年(二一三年)の事なり。
其の後鬼反するに及び、宮古島仲宗根豊見親の為めに征せられて、宮古島に属せしを、文亀の頃多良間島と交換せしとかや。
尖閣列島、は西表島の北方九十海里余にありて、古の所謂魚釣久場島にして、魚釣島、久葉島、北小島、南小島に分かれ、專ら古賀辰四郞氏の開拓する所なり。周囲二里にも足らざる小島のみなれども、信天翁及鰹の産額甚だ多し。