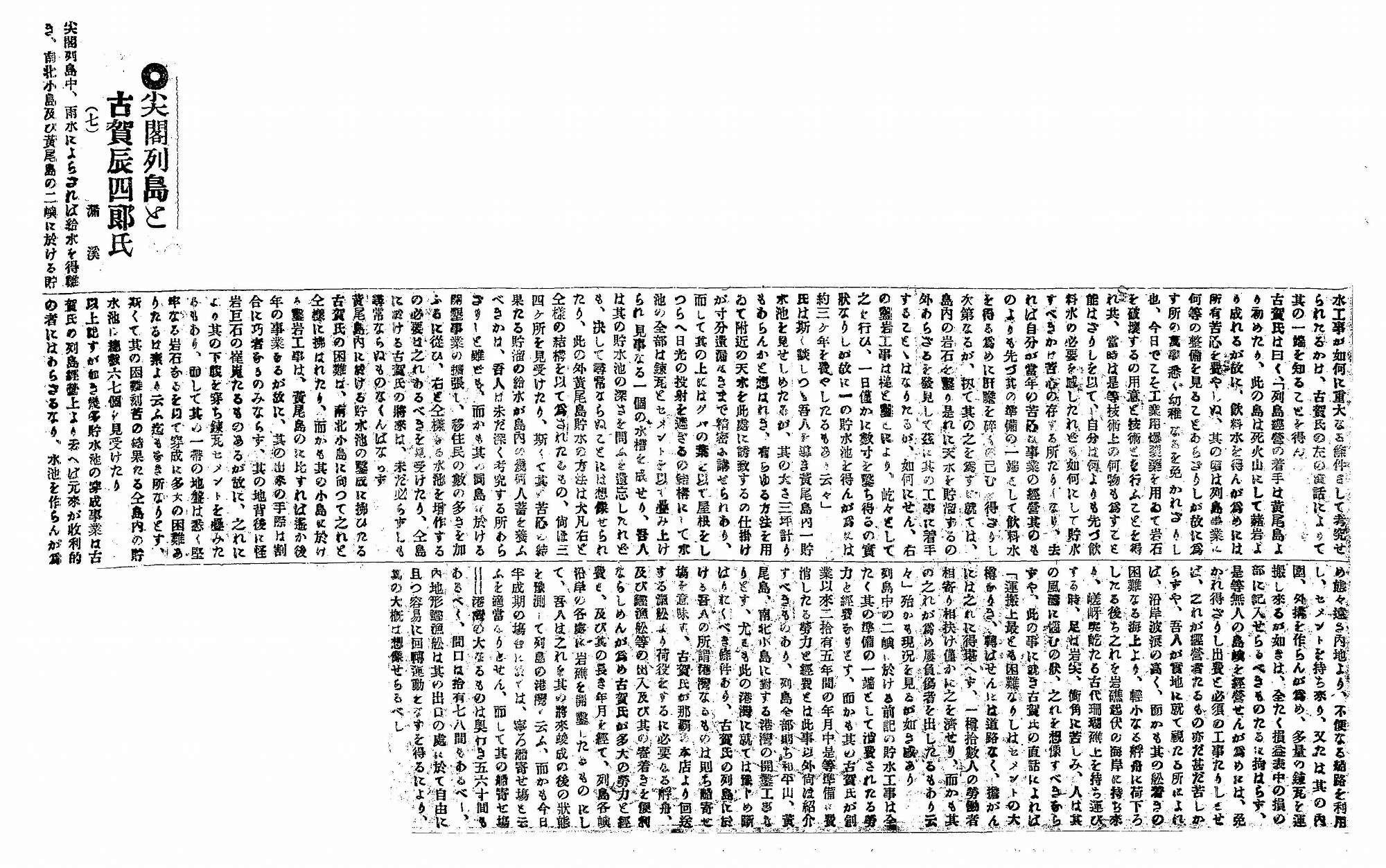キーワード検索
尖閣列島と古賀辰四郞氏(七)
原文表記
尖閣列島と古賀辰四郞氏(七)
琉球新報 明治四十一年六月二十二日 漏 渓
尖閣列島中、雨水によらざれば給水を得難き、南北小島及び黄尾島の二嶼に於ける貯水工事が如何に重大なる條件として考究せられたるかは、古賀氏の左の直話によりて其の一端を知ることを得ん
古賀氏は曰く、「列島經營の着手は黄尾島より初めたり、此の島は死火山にして赭岩より成れるが故に、飮料水を得んが爲めには所有苦心を費やしぬ、其の頃は列島事業に何等の整備を見ることあらざりしが故に爲す所の萬事悉く幼稚なるを免かれざりし也、今日でこそ工業用爆裂藥を用ゐて岩石を破壊するの用意と技術とを行ふことを得れ共、當時は是等技術上の何物も爲すこと能はざりしを以て、自分は何よりも先づ飮料水の必要を感したれども如何にして貯水すべきかは苦心の存する所たりしなり、去れば自分が當年の苦心は事業の經營其のものよりも先づ其の準備の一端として飮料水を得る爲めに肝膽を碎■■巳む■得ざりし次第なるが、扨て其の之を爲すに就ては、島内の岩石を鑿り是れに天水を貯溜するの外あらざるを發見して茲に其の工事に着手することゝはなりたるが、如何にせん、右の鑿岩工事は槌と鑿とにより、屹々として之を行ひ、一日僅かに數寸を鑿ち得るの實狀なりしが故に一の貯水池を得んが爲には約三ヶ年を費やしたるもあり云々」
氏は斯く談しつゝ吾人を導き黄尾島内一貯水池を見せしめたるが、其の大さ三坪計りもあらんかと想はれき、有らゆる方法を用ゐて附近の天水を此處に誘致するの仕掛けが寸分遺漏なきまで精密に講せられあり、而して其の上にはクバの葉を以て屋根をしつらへ日光の投射を遮ぎるの結構にして水池の全部は錬瓦とセメントを以て疊み上けられ見事なる一個の水槽を成せり、吾人は其の貯水池の深さを問ふを遺忘したれども、決して尋常ならぬことには想像せられたり、此の外黄尾島貯水の方法は大凡右と仝様の結構を以て爲されたるもの、尚ほ三四ヶ所を見受けたり、斯くて其の苦心の結果たる貯溜の給水が島内の幾何人畜を養ふべきかは、吾人は未だ深く考究する所あらざりしと雖ども、而かも其の同島に於ける開墾事業の壙張し、移住民の數の多きを加ふるに從ひ、右と仝様なる水池を增作するの必要は之れあるべきを見受けたり、仝島に於ける古賀氏の將來は、未だ必らずしも尋常ならぬものなくんばならず
黄尾島内に於ける貯水池の鑿成に拂ひたる古賀氏の困難は、南北小島に向つて之れと仝様に拂はれたり、而かも其の小島に於ける鑿岩工事は、黄尾島のに比すれば遙か後年の事業なるが故に、其の出來の手際は割合に巧者なるのみならず、其の地背後に怪岩巨石の崔嵬たるものあるが故に、之れにより其の下腹を穿ち錬瓦セメントを疊みたるもあり、而して其の一帶の地盤は悉く堅牢なる岩石なるを以て穿成に多大の困難ありたるは素より云ふ迄もなき所なりとす、斯くて其の困難刻苦の結果たる仝島内の貯水池は總數六七個を見受けたり
以上記すが如き幾多貯水池の穿成事業は古賀氏の列島經營上より云へば元來が收利的の者にはあらざるなり、水池を作らんが爲め態々遠き内地より、不便なる船路を利用し、セメントを持ち來り、又たは其の内圍、外構を作らんが爲め、多量の錬瓦を運搬し來るが如きは、全たく損益表中の損の部に記入せらるべきものたるに拘はらず、是等無人の島嶼を經營せんが爲めには、免かれ得ざりし出費と必須の工事たりしとせば、之れが經營者たるもの亦た甚だ苦しからずや、吾人が實地に就て觀たる所によれば、沿岸波浪の高く、而かも其の舩着きの困難なる海上より、輕小なる艀舟に荷下ろしたる後ち之れを岩礁起伏の海岸に持ち來り、嵯岈突屹たる古代珊瑚礁上を持ち運びする時、足は岩尖、衝角に苦しみ、人は其の風濤に悩むの狀、之れを想像すべきならずや、此の事に就き古賀氏の直話によれば「運搬上最とも困難なりしはセメントの大樽なりき、転はせんには道路なく、擔がんには之れに得堪ず、一樽拾數人の勞働者相寄り相扶け僅かに之を濟せり、而かも其の之れが爲め屢負傷者を出したるもあり云々」殆かも現况を見るが如き感あり
列島中の二嶼に於ける前記の貯水工事は全たく其の準備の一端として消費されたる勞力と經費なりとす、而かも其の古賀氏が創業以來二拾有五年間の年月中是等準備に費消したる勞力と經費とは此事以外尚ほ紹介すべきものあり、列島全部則ち和平山、黄尾島、南北小島に對する港灣の開墾工事なりとす、尤とも此の港灣に就ては豫じめ斷はりおくべき條件あり、古賀氏の列島に於ける吾人の所謂港灣なるものは則ち船寄せ場を意味す、古賀氏が那覇の本店より回送する滊舩より荷役をするに必要なる艀舟、及び鰹漁舩等の出入及び其の寄着きを便利ならしめんが爲め古賀氏が多大の勞力と經費と、及び其の長き年月を經て、列島各嶼沿岸の各處に岩礁を開鑿したるものにして、吾人は之れを其の將來竣成の後の狀態を豫測して列島の港灣と云ふ、而かも今日半成期の場合に於ては、寧ろ船寄せ場と云ふを適當なりとせん、而して其の船寄せ場==港灣の大なるものは奥行き五六十間もあるべく、間口は拾有七八間もあるべし、内地形鰹漁舩は其の出口の處に於て自由に且つ容易に回轉運動をなすを得るにより、其の大概は想像せらるべし
現代仮名遣い表記
尖閣列島と古賀辰四郞氏(七)
琉球新報 明治四十一年六月二十二日 漏 渓
尖閣列島中、雨水によらざれば給水を得難き南北小島及び黄尾島の二嶼に於ける貯水工事が、如何に重大なる条件として考究せられたるかは、古賀氏の左の演話によりて其の一端を知ることを得ん。
古賀氏は曰く、「列島経営の着手は黄尾島より初めたり。此の島は死火山にして赭岩より成れるが故に、飲料水を得んが為めには所有苦心を費やしぬ。其の頃は列島事業に何等の整備を見ることあらざりしが故に、為す所の万事悉く幼稚なるを免がれざりし也。今日でこそ工業用爆裂薬を用いて岩石を破壊するの用意と技術とを行うことを得れ共、当時は是等技術上の何物も為すこと能わざりしを以て、自分は何よりも先づ飲料水の必要を感じたれども、如何にして貯水すべきかは苦心の存する所たりしなり。去れば自分が当年の苦心は、事業の経営其のものよりも先づ其の準備の一端として飲料水を得る為めに肝胆を砕■■巳む■得ざりし次第なるが、扨て其の之を為すに就ては、島内の岩石を鑿り、是れに天水を貯溜するの外あらざるを発見して、茲に其の工事に着手することゝはなりたるが、如何にせん、右の鑿岩工事は槌と鑿とにより屹々として之を行い、一日僅かに数寸を鑿ち得るの実状なりしが故に、一の貯水池を得んが為には約三ヶ年を費やしたるもあり云々」。
氏は斯く談しつゝ吾人を導き黄尾島内一貯水池を見せしめたるが、其の大さ三坪計りもあらんかと想われき。有らゆる方法を用いて附近の天水を此処に誘致するの仕掛けが寸分遺漏なきまで精密に講せられあり。而して其の上にはクバの葉を以て屋根をしつらえ、日光の投射を遮ぎるの結構にして、水池の全部は錬瓦とセメントを以て畳み上げられ見事なる一個の水槽を成せり。吾人は其の貯水池の深さを問うを遺忘したれども、決して尋常ならぬことには想像せられたり。此の外黄尾島貯水の方法は大凡右と同様の結構を以て為されたるもの、尚お三、四ヶ所を見受けたり。斯くて其の苦心の結果たる貯溜の給水が島内の幾何人畜を養うべきかは、吾人は未だ深く考究する所あらざりしと雖ども、而かも其の同島に於ける開墾事業の拡張し、移住民の数の多きを加うるに従い、右と同様なる水池を増作するの必要は之れあるべきを見受けたり。同島に於ける古賀氏の将来は、未だ必らずしも尋常ならぬものなくんばならず。
黄尾島内に於ける貯水池の鑿成に払いたる古賀氏の困難は、南北小島に向って之れと同様に払われたり。而かも其の小島に於ける鑿岩工事は、黄尾島のに比すれば遙か後年の事業なるが故に、其の出来の手際は割合に巧者なるのみならず、其の地背後に怪岩巨石の崔嵬たるものあるが故に、之れにより其の下腹を穿ち、錬瓦セメントを畳みたるもあり。而して其の一帯の地盤は悉く堅牢なる岩石なるを以て、穿成に多大の困難ありたるは元より言う迄もなき所なりとす。斯くて其の困難刻苦の結果たる同島内の貯水池は総数六、七個を見受けたり。
以上記すが如き幾多貯水池の穿成事業は、古賀氏の列島経営上より言えば、元来が収利的の者にはあらざるなり。水池を作らんが為め態々遠き内地より、不便なる船路を利用し、セメントを持ち来り、又たは其の内囲、外構を作らんが為め、多量の錬瓦を運搬し来るが如きは、全たく損益表中の損の部に記入せらるべきものたるに拘わらず、是等無人の島嶼を経営せんが為めには、免かれ得ざりし出費と必須の工事たりしとせば、之れが経営者たるもの亦た甚だ苦しからずや。吾人が実地に就て観たる所によれば、沿岸波浪の高く、而かも其の船着きの困難なる海上より、軽小なる艀舟に荷下ろしたる後ち之れを岩礁起伏の海岸に持ち来り、嵯岈突屹たる古代珊瑚礁上を持ち運びする時、足は岩尖衝角に苦しみ、人は其の風濤に悩むの状、之れを想像すべきならずや。此の事に就き古賀氏の直話によれば「運搬上最とも困難なりしはセメントの大樽なりき。転ばせんには道路なく、担がんには之れに堪え得ず、一樽十数人の労働者相寄り相助け僅かに之を済せり。而かも其の之れが為め屢負傷者を出したるもあり云々」。殆かも現況を見るが如き感あり。
列島中の二嶼に於ける前記の貯水工事は全たく其の準備の一端として消費されたる労力と経費なりとす。而かも其の古賀氏が創業以来二十有五年間の年月中是等準備に費消したる労力と経費とは、此事以外尚お紹介すべきものあり。列島全部則ち和平山、黄尾島、南北小島に対する港湾の開墾工事なりとす。尤とも此の港湾に就ては予じめ断わりおくべき条件あり。古賀氏の列島に於ける吾人の所謂港湾なるものは、則ち船寄せ場を意味す。古賀氏が那覇の本店より回送する汽船より荷役をするに必要なる艀舟、及び鰹漁船等の出入及び其の寄着きを便利ならしめんが為め、古賀氏が多大の労力と経費と、及び其の長き年月を経て、列島各嶼沿岸の各処に岩礁を開鑿したるものにして、吾人は之れを其の将来竣成の後の状態を予測して列島の港湾と言う。而かも今日半成期の場合に於ては、寧ろ船寄せ場と言うを適当なりとせん。而して其の船寄せ場=港湾の大なるものは奥行き五、六十間もあるべく、間口は十有七、八間もあるべし。内地形鰹漁船は其の出口の処に於て自由に且つ容易に回転運動をなすを得るにより、其の大概は想像せらるべし。