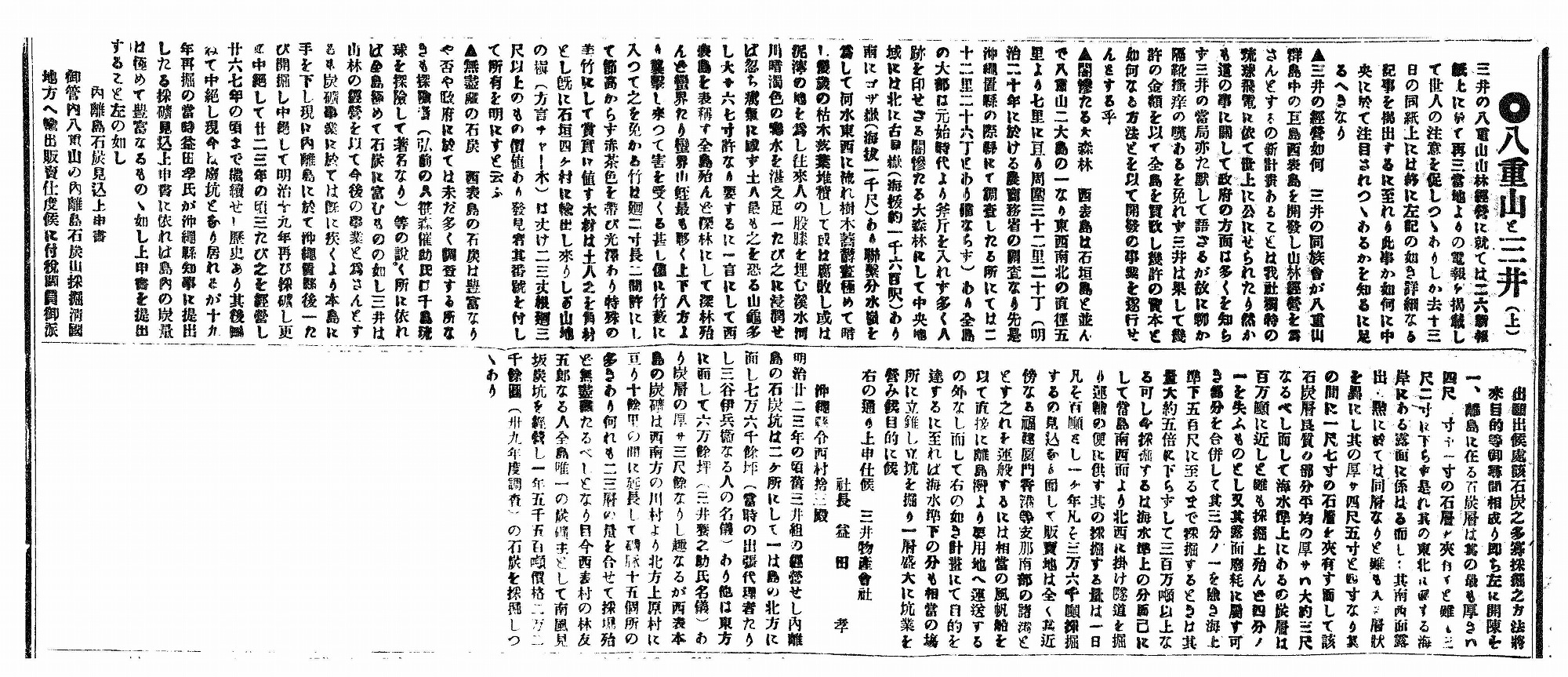キーワード検索
八重山と三井(上)
原文表記
八重山と三井(上)
琉球新報 明治四十一年二月二十二日
三井の八重山山林經營に就ては二六新報紙上に於て再三當地よりの電報を掲載して世人の注意を促しつゝありしか去十三日の同紙上には終に左記の如き詳細なる記事を掲出するに至れり此事か如何に中央に於て注目されつゝあるかを知るに足るへきなり
▲三井の經營如何 三井の同族會が八重山群島中の巨島西表島を開發し山林經營を爲さんとするの新計畫あることは我社獨特の琉球飛電に依て世上に公にせられたり然かも這の事に關して政府の方面は多くを知らず三井の當局亦た默して語ざるが故に聊か隔靴搔痒の嘆あるを免れず三井は果して幾許の金額を以て全島を買收し幾許の資本と如何なる方法とを以て開發の事業を遂行せんとする乎
▲闇惨たる大森林 西表島は石垣島と並んで八重山二大島の一なり東西南北の直經五里より七里に亘り周圍三十二里二十丁(明治二十年に於ける農商務省の調査なり先是沖繩置縣の際縣にて調査したる所にては二十二里二十六丁とあり確ならず)あり全島の大部は元始時代より斧斤を入れず多く人跡を印せざる闇惨たる大森林にして中央地域には北に古見嶽(海拔約一千六百呎)あり南にゴザ嶽(海拔一千尺)あり聯繫分水嶺を爲して河水東西に流れ樹木蕎欝晝極めて暗し幾歳の枯木落葉堆積して或は腐敗し或は泥濘の地を爲し往來人の股膝を埋む渓水河川暗濁色の毒水を湛え足一たび之に浸潤せば忽ち癘氣に感ず土人最も之を恐る山龜多し大サ六七寸許なり要するに一言にして西表島を表稱す全島殆んど深林にして深林殆んど蠻界たり蠻界山蛭最も夥く上下八方より襲撃し來つて害を受くる甚し僅に竹藪に入つて之を免かる竹は廻二寸長二間許にして節高からず赤茶色を帶び光澤あり特殊の美竹にして賞實に値す木材は土人之を角材とし既に石垣四ヶ村に輸出し來りしか山地の槇(方言チャー木)は丈け二三丈根廻三尺以上のもの價値あり發見者其番號を付して所有を明にすと云ふ
▲無盡蔵の石炭 西表島の石炭は豊富なりや否や政府に於ては未だ多く調査する所なきも探險者(弘前の人笹森催助氏は千島琉球を探險して著名なり)等の説く所に依れば全島極めて石炭に富むものの如し三井は山林の經營を以て今後の事業と爲さんとするも炭礦事業に於ては既に疾くより本島に手を下し現に内離島に於て沖繩置縣後一たび開掘し中絶して明治十九年再び採礦し更に中絶して廿二三年の頃三たび之を經營し廿六七年の頃まで繼續せし歴史あり其後重ねて中絶し現今は癈坑となり居れるが十九年再掘の當時益田孝氏が沖繩縣知事に提出したる採礦見込上申書に依れは島内の炭量は極めて豊富なるものゝ如し上申書を提出すること左の如し
内離島石炭見込上申書
御管内八重山の内離島石炭山採掘淸國地方へ輸出販賣仕度候に付税關員御派出願出候處該石炭之多寡採掘之方法將來目的等御尋間相成り即ち左に開陳す
一、離島に在る石炭層は其の最も厚きハ四尺■寸十一寸の石層を夾有すと雖も三尺二寸に下らず是れ其の東北に面する海岸にある露面に係はる而して其南西面露出の點に於ては同層なりと雖も大に層状を異にし其の厚サ四尺五寸と四寸なり其の間に一尺七寸の石層を夾有す而して該石炭層良質の部分平均の厚サハ大約三尺なるべし而して海水準上にあるの炭層は百万噸に近しと雖も採掘上殆んど四分ノ一を失ふものとし又其露面癈耗に属す可き部分を合併して其三分ノ一を除き海上準下五百尺に至るまで採掘するときは其量大約五倍に下らずして三百万噸以上なる可し今採掘するは海水準上の分而巳にして當島南西面より北西に掛け隧道を掘り運輸の便に供す其の採掘する量は一日凡そ百噸とし一ヶ年凡そ三万六千噸採掘するの見込なり而して販賣地は全く其近傍なる福建厦門香港等支那南部の諸港とす之れを運搬するには相當の風帆船を以て直接に離島灣より要用地へ運送するの外なし而して右の如き計畫にて目的を達するに至れば海水準下の分も相當の場所に立錐し立坑を掘り一層盛大に坑業を營み候目的に候
右の通り上申仕候 三井物産會社
社長 益田 孝
沖繩縣令西村捨三殿
明治廿二三年の頃舊三井組の經營せし内離島の石炭坑は二ヶ所にして一は島の北方に面し七万六千餘坪(當時の出張代理者たりし三谷伊兵衛なる人の名儀)あり他は東方に面して六万餘坪(三井養之助氏名儀)あり炭層の厚サ三尺餘なりし趣なるが西表本島の炭礦は西南方の川村より北方上原村に亘り十餘里の間に延長して礦脈十五個所の多きあり何れも二三層の量を合せて採掘殆ど無盡蔵たるべしとなり目今西表村の林友五郞なる人全島唯一の炭礦主として南風見坂炭坑を經營し一年五千五百噸價格二万二千餘圓(卅九年度調査)の石炭を採掘しつゝあり
現代仮名遣い表記
八重山と三井(上)
琉球新報 明治四十一年二月二十二日
三井の八重山山林経営に就ては二六新報紙上に於て再三当地よりの電報を掲載して世人の注意を促しつゝありしが、去十三日の同紙上には終に左記の如き詳細なる記事を掲出するに至れり。此事が如何に中央に於て注目されつゝあるかを知るに足るべきなり。
▲三井の経営如何 三井の同族会が、八重山群島中の巨島西表島を開発し、山林経営を為さんとするの新計画あることは、我社独特の琉球飛電に依て世上に公にせられたり。然かも此の事に関して、政府の方面は多くを知らず。三井の当局亦た黙して語ざるが故に、聊か隔靴搔痒の嘆あるを免れず。三井は果して幾許の金額を以て全島を買収し、幾許の資本と如何なる方法とを以て開発の事業を遂行せんとする乎。
▲闇惨たる大森林 西表島は石垣島と並んで八重山二大島の一なり。東西南北の直経五里より七里に亘り、周囲三十二里二十丁(明治二十年に於ける農商務省の調査なり。先是沖縄置県の際県にて調査したる所にては二十二里二十六丁とあり。確ならず)あり。全島の大部は元始時代より斧斤を入れず。多く人跡を印せざる闇慘たる大森林にして、中央地域には北に古見嶽(海抜約一千六百呎)あり、南にゴザ嶽(海抜一千尺)あり。連繫分水嶺を為して河水東西に流れ、樹木蕎鬱昼極めて暗し。幾歳の枯木落葉堆積して、或は腐敗し或は泥濘の地を為し、往来人の股膝を埋む。渓水河川暗濁色の毒水を湛え、足一たび之に浸潤せば忽ち癩気に感ず。土人最も之を恐る。山亀多し。大さ六、七寸許なり。要するに一言にして西表島を表称す。全島殆んど深林にして深林殆んど蛮界たり。蛮界山蛭最も夥く、上下八方より襲撃し来って害を受くる甚し。僅に竹藪に入って之を免がる。竹は廻二寸長二間許にして節高からず。赤茶色を帯び光沢あり。特殊の美竹にして賞実に値す。木材は土人之を角材とし、既に石垣四ヶ村に輸出し来りしが、山地の槇(方言チャー木)は丈け二、三丈、根廻三尺以上のもの価値あり。発見者其番号を付して所有を明にすと言う。
▲無尽蔵の石炭 西表島の石炭は豊富なりや否や。政府に於ては未だ多く調査する所なきも探険者(弘前の人笹森儀助氏は千島琉球を探検して著名なり)等の説く所に依れば、全島極めて石炭に富むものの如し。三井は山林の経営を以て今後の事業と為さんとするも、炭鉱事業に於ては既に疾くより本島に手を下し、現に内離島に於て沖縄置県後一たび開掘し、中絶して明治十九年再び採鉱し、更に中絶して二十二、三年の頃三たび之を経営し、二十六、七年の頃まで継続せし歴史あり。其後重ねて中絶し、現今は廃坑となり居れるが、十九年再掘の当時益田孝氏が沖縄県知事に提出したる採鉱見込上申書に依れば、島内の炭量は極めて豊富なるものゝ如し。上申書を提出すること左の如し。
内離島石炭見込上申書
御管内八重山の内離島石炭山採掘清国地方へ輸出販売仕度候に付税関員御派出願出候処、該石炭之多寡、採掘之方法、将来、目的等御尋問相成り、即左に開陳す。
一、離島に在る石炭層は、其の最も厚きは四尺■寸十一寸の石層を狭有すと雖も、三尺二寸に下らず。是れ其の東北に面する海岸にある露面に係わる。而して其南西面露出の点に於ては、同層なりと雖も大に層状を異にし、其の厚さ四尺五寸と四寸なり。其の間に一尺七寸の石層を狭有す。而して該石炭層良質の部分、平均の厚さは大約三尺なるべし。而して海水準上にあるの炭層は百万屯に近しと雖も、採掘上殆んど四分ノ一を失うものとし、又其露面廃耗に属す可き部分を合併して其三分ノ一を除き海上準下五百尺に至るまで採掘するときは、其量大約五倍に下らずして三百万屯以上なる可し。今採掘するは海水準上の分而巳にして、当島南西面より北西に掛け隧道を掘り運輸の便に供す。其の採掘する量は一日凡そ百屯とし、一ヶ年凡そ三万六千屯採掘するの見込なり。而して販売地は全く其近傍なる福建、厦門、香港等支那南部の諸港とす。之れを運搬するには相当の風帆船を以て、直接に離島湾より要用地へ運送するの外なし。而して右の如き計画にて目的を達するに至れば、海水準下の分も相当の場所に立錐し立坑を掘り、一層盛大に坑業を営み候目的に候。
右の通り上申仕候。
三井物産会社
社長 益田 孝
沖縄県令西村捨三殿
明治二十二、三年の頃、旧三井組の経営せし内離島の石炭坑は二ヶ所にして、一は島の北方に面し七万六千余坪(当時の出張代理者たりし三谷伊兵衛なる人の名儀)あり。他は東方に面して六万余坪(三井養之助氏名儀)あり。炭層の厚さ三尺余なりし趣なるが、西表本島の炭鉱は西南方の川村より北方上原村に亘り十余里の間に延長して鉱脈十五個所の多きあり。何れも二、三層の量を合せて採掘殆ど無尽蔵たるべしとなり。目今西表村の林友五郞なる人全島唯一の炭鉱主として南風見坂炭坑を経営し、一年五千五百屯、価格二万二千余円(三十九年度調査)の石炭を採掘しつゝあり。