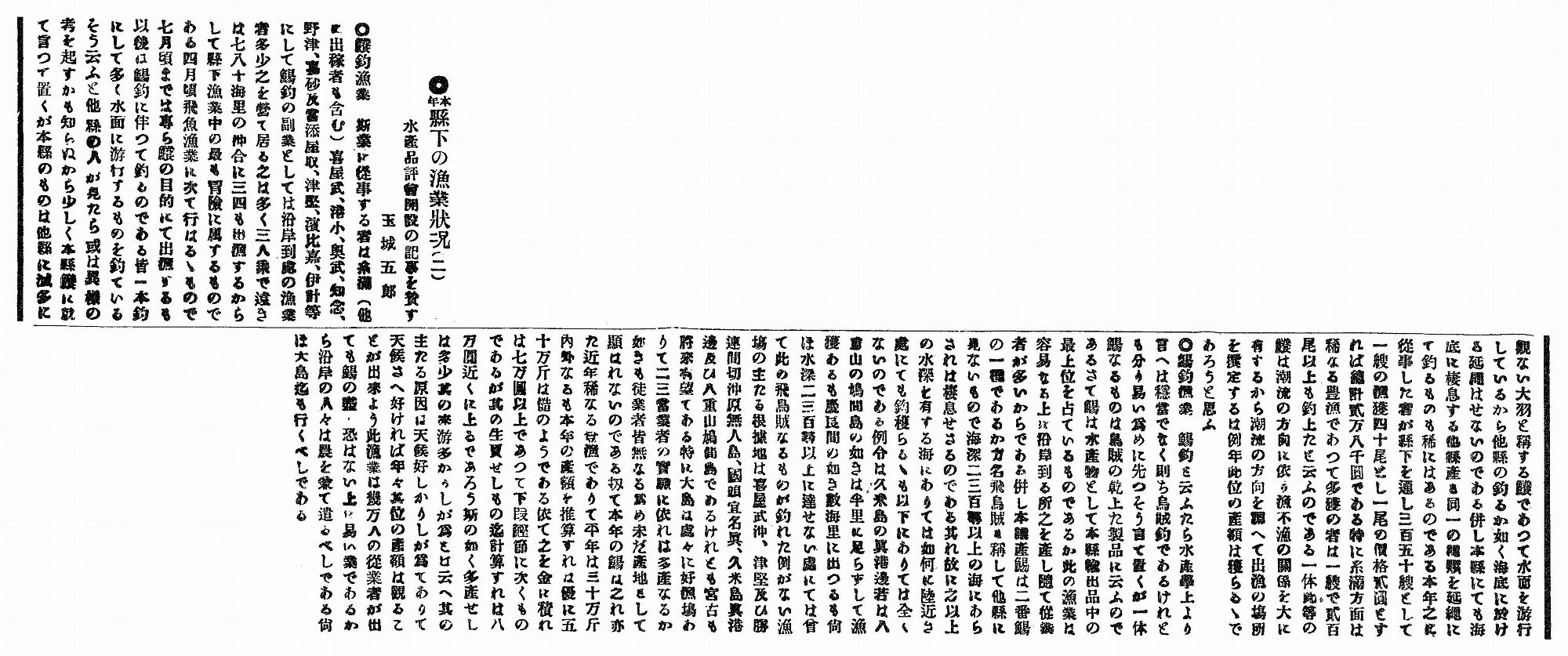キーワード検索
◎本年縣下の漁業狀况(二)
原文表記
◎本年縣下の漁業狀况(二)
水產品評會開設の記事を賛す
玉城五郞
◎鱶釣漁業 斯業に從事する者は糸満(他に出稼者も含む)喜屋武、港小、奧武、知念、野津、嘉砂及當添屋取、津堅、濱比嘉、伊計等にして鯣釣の副業としては沿岸到處の漁業者多少之を營て居る之は多く三人乗で遠きは七八十海里の冲合に三四も出漁するからして縣下漁業中の最も冒險に属するものである四月頃飛魚漁業に次て行はるゝもので七月頃までは專ら鱶の目的にて出漁するも以後は鯣釣に伴つて釣るのである皆一本釣にして多く水面に游行するものを釣ているそう云ふと他縣の人が見たら或は異樣の考を起すかも知らぬから少しく本縣鱶に就て言つて置くが本縣のものは他縣に滅多に觀ない大羽と稱する鱶であつて水面を游行しているから他縣の釣るか如く海底に於ける延繩はせないのである併し本縣にても海底に棲息する他縣產も同一の種類を延繩にて釣るものは稀にはあるのである本年之に從事した者が縣下を通し三百五十艘として一艘の漁獲四十尾とし一尾の價格貳圓とすれば總計貳万八千圓である特に糸滿方面は稀なる豊漁であつて多獲の者は一艘で貳百尾以上も釣上たと云ふのである一体此等の鱶は潮流の方向に依り漁不漁の關係を大に有するから潮流の方向を調へて出漁の塲所を撰定するは例年此位の產額は獲らるゝであろうと思ふ
◎鯣釣漁業 鯣釣と云ふたら水產學上より言へは穩當でなく則ち烏賊釣であるけれとも分り易い爲めに先つそう言て置くが一体鯣なるものは烏賊の乾上た製品に云ふのであるさて鯣は水產物として本縣輸出品中の最上位を占ているものであるか此の漁業は容易なる上に沿岸到る所之を產し随て從業者が多いからである併し本縣產鯣は二番鯣の一種であるか方名飛烏賊■稱して他縣に見ないもので海深二三百等以上の海にあらされは棲息せさるのである其れ故に之以上の水深を有する海にありては如何に陸近き處にても釣穫らるゝも以下にありては全くないのである例令は久米島の眞港邊若は八重山の鳩間島の如きは半里に足らずして漁獲あるも慶良間の如き數海里に出つるも尙ほ水深二三百等以上に達せない處にては曾て此の飛烏賊なるものが釣れた例がない漁塲の主たる根據地は喜屋武沖、津堅及ひ勝連間切沖原無人島、國頭宜名眞、久米島眞港邊及ひ八重山鳩間島であるけれども宮古も將來有望てある特に大島は處々に好漁塲ありて二三當業者の實驗に依れは多產なるか如きも徒業者皆無なる爲め未だ產地として顯はれないのである扨て本年の鯣は之を亦た近年稀なる豊漁でありて平年は三十万斤内外なるも本年の產額を推算すれは優に五十万斤は慥のようである依て之を金に積れは七万圓以上であつて下叚鰹節に次くものであるが其の生■せしもの迄計算すれは八万圓近くに上るであろう斯の如く多產せしは多少其の來游多かりしが爲とは云へ其の主たる原因は天候好しかりしが爲てありて天候さへ好ければ年々其位の產額は觀ることが出來よう此漁業は幾万人の從業者が出ても鯣の■■恐はない上に易い業であるから沿岸の人々は農を兼て遺るべしである尙ほ大島迄も行くべしである
現代仮名遣い表記
◎本年県下の漁業状況(二)
水産品評会開設の記事を讃す
玉城五郎
◎フカ釣漁業 この業に従事する者は糸満(他に出稼者も含む)喜屋武、港小、奥武、知念、野津、嘉砂及當添屋取、津堅、浜比嘉、伊計等にして、スルメ釣の副業としては沿岸到る処の漁業者多少これを営て居る。これは多く三人乗で、遠きは七八十海里の沖合に三四も出漁するからして、県下漁業中の最も冒険に属するものである。四月頃トビウオ漁業に次て行はるるもので、七月頃までは専らフカの目的にて出漁するも、以後はスルメ釣に伴って釣るのである。皆一本釣にして、多く水面に游行するものを釣ている。そう云うと他県の人が見たら、或は異様の考を起すかも知らぬから少しく、本県フカについて言って置くが、本県のものは他県に滅多に観ない大羽と称するフカであって、水面を游行しているから、他県の釣るか如く海底に於ける延縄はせないのである。併し本県にても海底に棲息する他県産も、同一の種類を延縄にて釣るものは稀にはあるのである。本年これに従事した者が県下を通し三百五十艘として、一艘の漁獲四十尾とし一尾の価格二円とすれば、総計二万八千円である。特に糸満方面は稀なる豊漁であつて、多獲の者は一艘で二百尾以上も釣上たと云うのである。一体これらのフカは潮流の方向に依り漁不漁の関係を大に有するから潮流の方向を調べて出漁の場所を選定するは例年この位の産額は獲らるるであろうと思う
◎フカ釣漁業 スルメ釣と云うたら水産学上よりいへば、穏当でなく則ちイカ釣である。けれども分り易い為めにまずそういうて置くが、一体スルメなるものはイカの乾上た製品に云うのである。さてスルメは水産物として本県輸出品中の最上位を占ているものであるが、この漁業は容易なる上に沿岸到る所これを産し随て従業者が多いからである。しかし本県産スルメは二番スルメの一種であるが方名飛イカ■称して他県に見ないもので、海深二三百等以上の海にあらされは棲息せさるのである。それ故に、これ以上の水深を有する海にありては如何に陸近き処にても釣穫らるるも、以下にありては全くないのである。例令は久米島の真港辺もしくは八重山の鳩間島の如きは、半里に足らずして漁獲あるも、慶良間の如き数海里に出つるも、尚お水深二三百等以上に達せない処にては曽て、この飛イカなるものが釣れた例がない。漁場の主たる根拠地は喜屋武沖、津堅及び勝連間切、沖原無人島、国頭宜名真、久米島真港辺及び八重山鳩間島であるけれども、宮古も将来有望である。特に大島は処々に好漁場ありて、二三当業者の実験によれば多産なるか如きも、徒業者皆無なる為め未だ産地として顕はれないのである。さて、本年のスルメはこれをまた近年稀なる豊漁でありて平年は三十万斤内外なるも本年の産額を推算すれは優に五十万斤は慥のようである。よってこれを金に積れは七万円以上であって下叚鰹節につぐものであるが、その生■せしもの迄計算すれば八万円近くに上るであろう。この如く多産せしは多少その来游多かりしが為とは云へ、その主たる原因は天候好しかりしが為てありて、天候さへ好ければ年々その位の産額は観ることが出来よう。この漁業は幾万人の従業者が出てもスルメの■■恐はない上に易い業であるから、沿岸の人々は農を兼てやるべしである。尚お、大島迄も行くべしである。