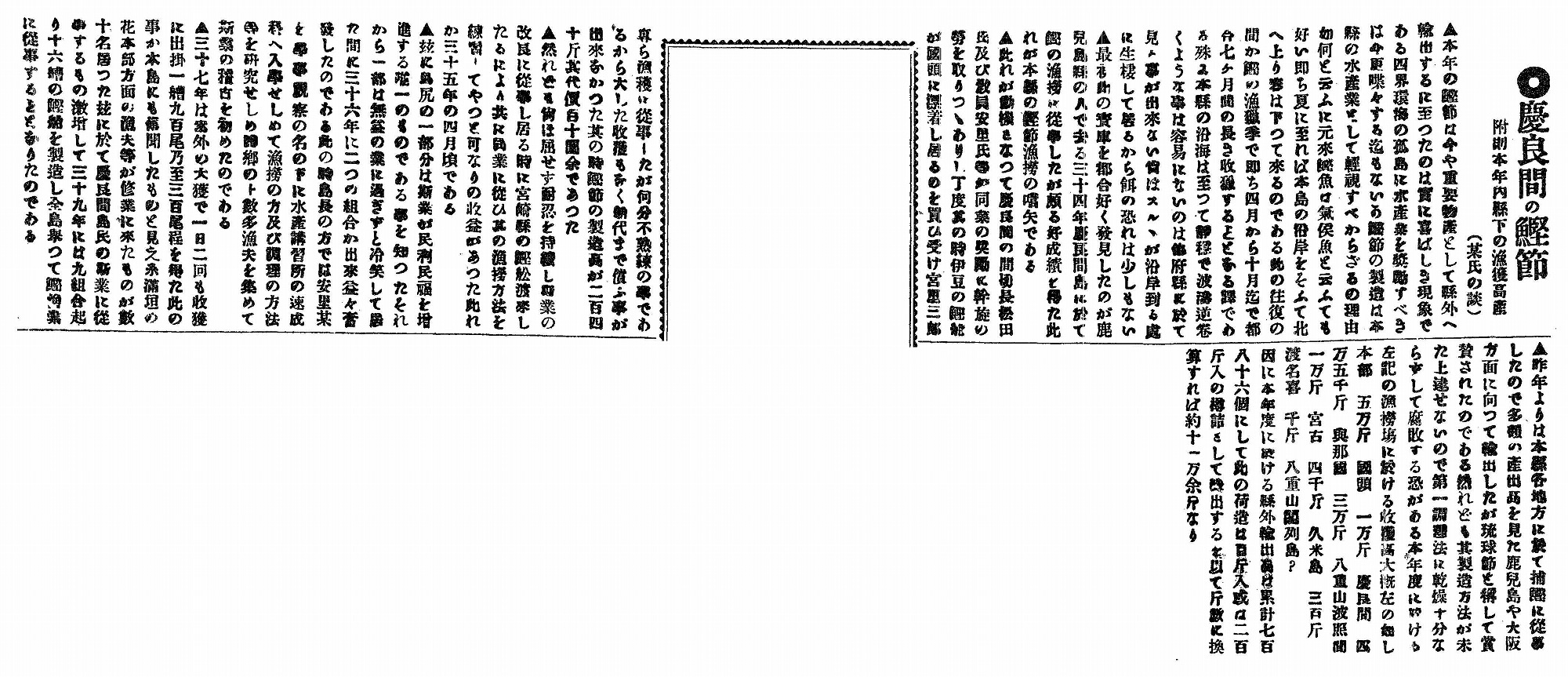キーワード検索
◎慶良間の鰹節
原文表記
◎慶良間の鰹節
附則本年内懸下の漁獲高產
(某氏の談)
▲本年の鰹節は今や重要産物として懸外へ輸出するに至つたのは實に喜ばしき現象である四界環海の孤島に水産業を奬勵すべきは今更喋々する迄もないか鰹節の製造は本懸の水産業として輕視すべからざるの理由如何と云ふに元來鰹魚は氣候魚と云ふても好い即ち夏に至れば本島の沿岸をそふて北へのぼり春は下つて來るのである此の往復の間か鰹の漁猟季で即ち四月から十月迄で都合七ヶ月間の長き収穫することとなる譯である殊に本懸の沿岸は至つて靜穏で波濤逆巻くような事は容易にないのは他府懸に於て見る事が出來ない尚ほスルヽが沿岸到る處に生棲して居るから餌の恐れは少しもない
▲最■■之寶庫を都合よく發見したのが鹿兒島懸の人で去る三十四年慶良間島に於て鰹の漁撈に從事したが頗る好成績を得た此れが本懸の鰹節漁撈の■矢である
▲此れが動機となつて慶良間の間切長松田氏及び敎員安里氏等が同業の奬勵に斡旋の勞を取りつゝありし丁度其の時伊集の鰹船が國頭に漂着し居るのを買ひ受け宮里三郎専ら漁穫に從事したが何分不熟練の事であるから大した収穫もなく船代まで償ふ事が出來なかつた其の時鰹節の製造高が二百四十斤其代價百十圓余であつた
▲然れども尚ほ屈せず耐忍を持續し斯業の改良に從事し居る時に宮崎懸の鰹舩渡來したるにより共に同業に從ひ其の漁撈方法を練習してやつと可なりの收益があつた此れか三十五年の四月頃である
▲茲に島尻の一部分は斯業が民利民福を增進する唯一のものである事を知つたそれから一部は無益の業に過ぎずと冷笑して居た間に三十六年に二つの組合が出來益々奮發したのである此の時島長の方では安里某を學事観察の名の下に水産講習所の速成科へ入學せしめて漁撈の方及び調理の方法等を研究せしめ歸鄕の上數多漁夫を集めて斯業の稽古を初めたのである
▲三十七年は案外の大獲で一日二回も収獲に出掛一艚九百尾乃至三百尾程を得た此の事か本島にも■聞したものと見え糸滿垣の花本部方面の漁夫当が修業に來たものが數十名居つた茲に於て慶良間島民の斯業に從事するもの激增して三十九年には九組合起り十六艚の鰹船を製造し全島擧つて鰹漁業に從事するとなりたのである
▲昨年よりは本懸各地方に於て捕鰹に從事したので多額の産出高を見た鹿兒島や大阪方面に向つて輸出したが琉球節と稱して賞賛されたのである然れども其製造方法が未た上達せないので第一調■法に乾燥十分ならずして腐敗する恐れがある本年度に於ける左記の漁撈塲に於ける収穫高大概左の如し
本部 五万斤 國頭 一万斤 慶良間 四万五千斤 與那國 三万斤 八重山波照間 一万斤 宮古 四千斤 久米島 三百斤 渡名喜 千斤 八重山閣列島?
因に本年度に於ける縣外輸出高は累計七百八十六個にして此の荷造は百斤入或は二百斤入りの樽詰として■出するを以て斤數に換算すれば約十一万余斤なり
現代仮名遣い表記
◎慶良間の鰹節
附則本年内県下の漁獲高産
(某氏の談)
▲本年の鰹節は今や重要産物として県外へ輸出するに至ったのは、実に喜ばしき現象である。四界環海の孤島に水産業を奨励すべきは、今更喋々する迄もないが、鰹節の製造は本県の水産業として軽視すべからざるの理由如何と云うに、元来鰹魚は気候魚と云っても好い。即ち、夏に至れば本島の沿岸をそうて北へのぼり、春は下って来るのである。此の往復の間が鰹の漁猟季で、即ち四月から十月迄で都合七ヶ月間の長き収穫することとなる訳である。殊に本県の沿岸は至って静穏で、波濤逆巻くような事は容易にないのは他府県に於て見る事が出来ない。尚ほ、スルルが沿岸到る処に生棲して居るから、餌の恐れは少しもない。
▲最■■之宝庫を都合よく発見したのが鹿児島県の人で、去る三十四年、慶良間島に於て鰹の漁労に従事したが頗る好成績を得た。此れが本県の鰹節漁労の■矢である。
▲此れが動機となって、慶良間の間切長松田氏及び教員安里氏等が同業の奨励に斡旋の労を取りつつありし、丁度其の時、伊集の鰹船が国頭に漂着し居るのを買い受け、宮里三郎専ら漁穫に従事したが何分不熟練の事であるから大した収穫もなく、船代まで償ふ事が出来なかった。其の時、鰹節の製造高が二百四十斤其代価百十円余であった。
▲然れども尚ほ屈せず耐忍を持続し、斯業の改良に従事し居る時に宮崎県の鰹船渡来したるにより共に同業に従い、其の漁労方法を練習してやっと可なりの収益があった。此れが三十五年の四月頃である。
▲茲に、島尻の一部分は斯業が民利民福を増進する唯一のものである事を知った。それから一部は無益の業に過ぎずと冷笑して居た間に三十六年に二つの組合が出来、益々奮発したのである。此の時、島長の方では安里某を学事観察の名の下に、水産講習所の速成科へ入学せしめて漁労の方及び調理の方法等を研究せしめ、帰郷の上数多漁夫を集めて、斯業の稽古を初めたのである。
▲三十七年は案外の大獲で、一日二回も収獲に出掛一艚九百尾乃至三百尾程を得た。此の事が本島にも■聞したものと見え、糸満、垣の花、本部方面の漁夫当が修業に来たものが数十名居った。茲に於て慶良間島民の斯業に従事するもの激増して、三十九年には九組合起り十六艚の鰹船を製造し、全島挙げて鰹漁業に従事するとなりたのである。
▲昨年よりは、本県各地方に於て捕鰹に従事したので、多額の産出高を見た。鹿児島や大阪方面に向って輸出したが、琉球節と称して賞賛されたのである。然れども、其製造方法が未だ上達しないので、第一調■法に乾燥十分ならずして腐敗する恐れがある。本年度に於ける左記の漁労場に於ける収穫高、大概左の如し。
本部 五万斤 国頭 一万斤 慶良間 四万五千斤 与那国 三万斤 八重山波照間 一万斤 宮古 四千斤 久米島 三百斤 渡名喜 千斤 八重山閣列島?
因に本年度に於ける県外輸出高は、累計七百八十六個にして此の荷造は百斤入、或は二百斤入りの樽詰として■出するを以て、斤数に換算すれば約十一万余斤なり。