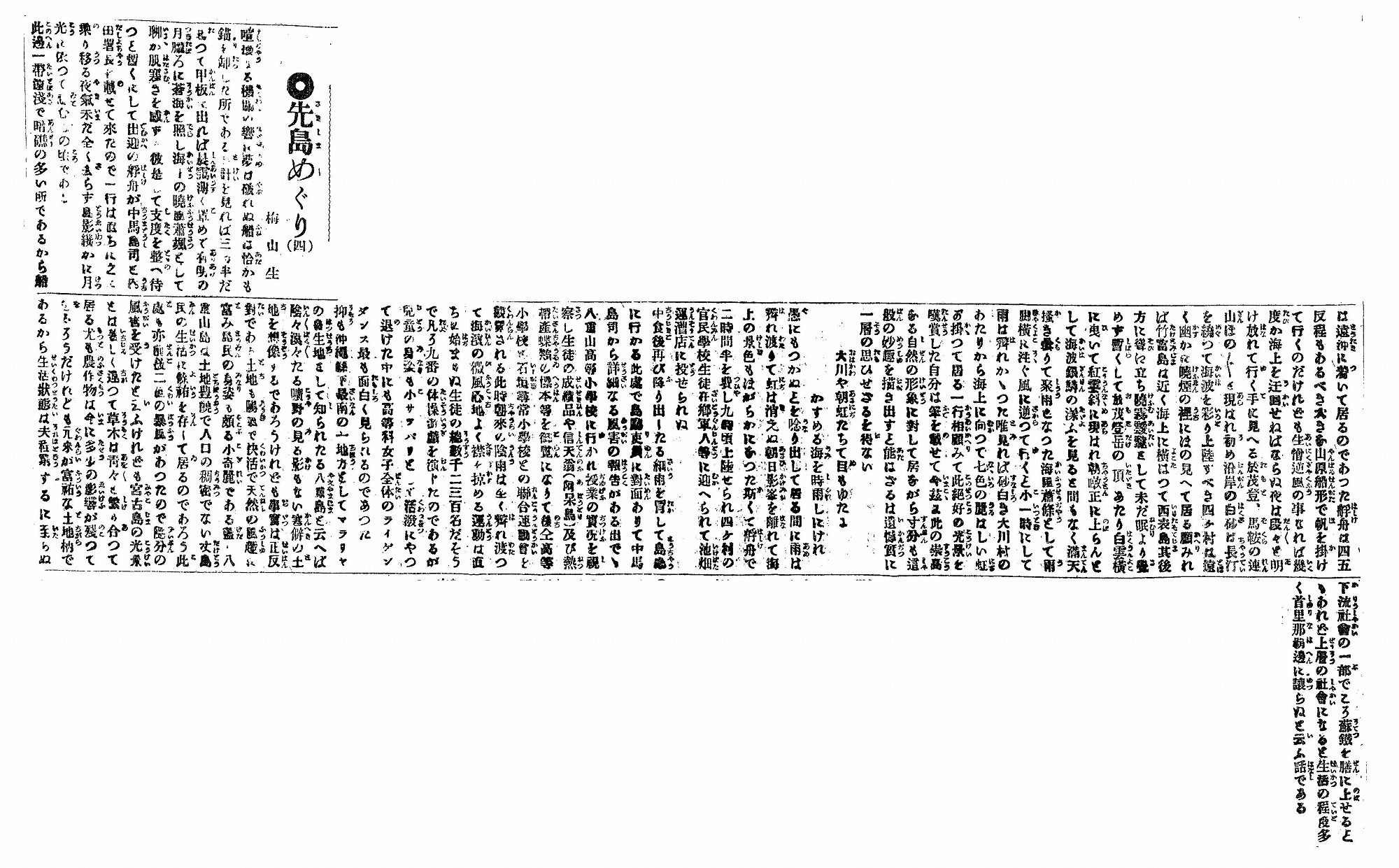キーワード検索
先島めぐり(四)
原文表記
先島めぐり(四)
琉球新報 明治四十年二月十九日
梅 山 生
喧擾なる機關の響に夢は破れぬ船は恰かも錨を卸した所である時計を見れば三■半だ起つて甲板に出れば晨靄薄く罩めて有明の月朧ろに蒼海を照し海上の暁風蕭颯として聊か肌寒さを感ずる彼是して支度を整へ待つこと暫くにして出迎の艀舟(はしけ)が中馬島司と内田署長を載せて來たので一行は直ちに之に乘り移る夜氣未だ全く去らず。島影纔かに月光に依つて認むるの頃である
此邊一帶遠淺で暗礁の多い所であるから船は遠沖に着いて居るのであつた艀舟は四五反程もあるべき大きな山原船形で帆を掛けて行くのだけれども生憎逆風の事なれば幾度か海上を迂回せねばならぬ夜は段々と明け放れて行く手に見へる於茂登、馬鞍の連山ほのぼのと現はれ初め沿岸の白砂は長汀を繞つて海波を彩り上陸すべき四ヶ村は遠く幽かに暁煙の裡にほの見へて居る顧みれば竹富島は近く海上に横はつて西表島其後方に聳え立ち暁霧靉靆として未だ眠より覺めず暫くして於茂登岳の頂あたり白雲横に曳いて紅雲斜に現はれ朝暾正に上らんとして海波銀鱗の漾ふを見ると間もなく滿天搔き曇りて聚雨となつた海風蕭条として雨脚横に注ぐ風に逆つて行くこと小一時にして雨は霽れかゝつた唯見れば砂白き大川村のあたりから海上に向つて七色の麗はしい虹の掛つて居る一行相顧みて此絶好の光景を嘆賞した自分は筆を載せて今茲に此の崇高なる自然の形象に對して居ながら寸分も這般の妙趣を描き出すこと能はざるは遺憾實に一層の思ひせざるを得ない
大川や朝虹たちて目もゆたに
かすめる海を時雨しにけれ
愚にもつかぬことを唸り出して居る間に雨は霽れ渡りて虹は消えぬ朝日影峰を離れて海上の景色もほがらかになつた斯くて艀舟で二時間半を費し九時頃上陸せられ四ヶ村の官民學校生徒在郷軍人等に迎へられて池畑運漕店に投ぜられぬ
中食後再び降り出したる細雨を冒して島廳に行かる此處で島廳吏員に對面ありて中馬島司から詳細なる風害の報告がある出でゝ八重山高等小學校に行かれ授業の實況を視察し生徒の成績品や信天翁(阿呆鳥)及び熱帶産蝶類の標本等を御覧になりて後仝高等小學校と石垣尋常小學校との聯合運動會を観覧される此時朝來の陰雨は全く霽れ渡つて海濱の微風心地よく襟を掠める運動は直ちに始まりぬ生徒の總數千二三百名だそうで凡そ九番の体操遊戯を演じたのであるが児童の身姿も小サツパリとして活潑にやつて退けた中にも高等科女子全体のライゲンダンス最も面白く見られるのであつた
抑も沖繩縣下最南の一地方としてマラリヤの發生地として知られたる八重山島と云へば陰々漠々たる曠野の見る影もない寒僻の土地を想像するであろうけれども事實は正反對である土地も陽氣で快活で天然の風趣に富み島民の身姿も頗る小奇麗である蓋し八重山島は土地豊饒で人口の稠密でない丈島民の生活に餘裕を存して居るのであろう此處も亦前後二回の暴風があつたので随分の風害を受けたと云ふけれども宮古島の光景とは著しく違つて草木は青々と繁り合つて居る尤も農作物は今に多少の影響が殘つて■(を)るそうだけれども元來が富裕な土地柄であるから生活狀態は夫程窮するに至らぬ下流社會の一部でこそ蘇鉄を膳に上せることもあれど上層の社會になると生活の程度多く首里那覇邊に譲らぬと云ふ話である
現代仮名遣い表記
先島めぐり(四)
琉球新報 明治四十年二月十九日
梅 山 生
喧擾なる機関の響に夢は破れぬ。船は恰かも錨を卸した所である。時計を見れば三■半だ。起って甲板に出れば、晨靄薄く罩めて有明の月朧ろに蒼海を照し、海上の暁風蕭颯として聊か肌寒さを感ずる。彼是して支度を整え待つこと暫くにして、出迎の艀舟が中馬島司と内田署長を載せて来たので、一行は直ちに之に乗り移る。夜気未だ全く去らず。島影纔かに月光に依って認むるの頃である。
此辺一帯遠浅で暗礁の多い所であるから、船は遠沖に着いて居るのであった。艀舟は四、五反程もあるべき大きな山原船形で、帆を掛けて行くのだけれども、生憎逆風の事なれば幾度か海上を迂回せねばならぬ。夜は段々と明け放れて、行く手に見える於茂登、馬鞍の連山ほのぼのと現われ初め、沿岸の白砂は長汀を巡って海波を彩り、上陸すべき四ヶ村は遠く幽かに暁煙の裡にほの見えて居る。顧みれば竹富島は近く海上に横わって、西表島其後方に聳え立ち、暁霧靉靆として未だ眠より覚めず。暫くして於茂登岳の頂あたり白雲横に曳いて紅雲斜に現われ、朝暾正に上らんとして海波銀鱗の漂を見ると間もなく、満天搔き曇りて聚雨となった。海風蕭条として雨脚横に注ぐ。風に逆って行くこと小一時にして雨は晴れかゝった。唯見れば、砂白き大川村のあたりから海上に向って七色の麗わしい虹の掛って居る。一行相顧みて此絶好の光景を嘆賞した。自分は筆を載せて今茲に此の崇高なる自然の形象に対して居ながら、寸分も此般の妙趣を描き出すこと能わざるは遺憾実に一層の思いせざるを得ない。
大川や朝虹たちて目もゆたに
かすめる海を時雨しにけれ
愚にもつかぬことを唸り出して居る間に雨は晴れ渡りて虹は消えぬ。朝日影峰を離れて海上の景色もほがらかになった。斯くて艀舟で二時間半を費し九時頃上陸せられ、四ヶ村の官民学校生徒、在郷軍人等に迎えられて池畑運漕店に投ぜられぬ。
中食後再び降り出したる細雨を冒して島庁に行かる。此処で島庁吏員に対面ありて、中馬島司から詳細なる風害の報告がある。出でて八重山高等小学校に行かれ、授業の実況を視察し、生徒の成績品や信天翁(阿呆鳥)及び熱帯産蝶類の標本等を御覧になりて後、同高等小学校と石垣尋常小学校との連合運動会を観覧される。此時朝来の陰雨は全く晴れ渡って、海浜の微風心地よく襟を掠める。運動は直ちに始まりぬ。生徒の総数千二、三百名だそうで、凡そ九番の体操遊戯を演じたのであるが、児童の身姿も小サッパリとして活発にやって退けた。中にも高等科女子全体のライゲンダンス最も面白く見られるのであった。
抑も沖縄県下最南の一地方としてマラリヤの発生地として知られたる八重山島と言えば、陰々漠々たる広野の見る影もない寒僻の土地を想像するであろうけれども、事実は正反対である。土地も陽気で快活で天然の風趣に富み、島民の身姿も頗る小奇麗である。蓋し八重山島は土地豊饒で人口の稠密でない丈島民の生活に余裕を存して居るのであろう。此処も亦前後二回の暴風があったので随分の風害を受けたと言うけれども、宮古島の光景とは著しく違って、草木は青々と繁り合って居る。尤も農作物は今に多少の影響が残って■(を)るそうだけれども、元来が富裕な土地柄であるから生活状態は夫程窮するに至らぬ。下流社会の一部でこそ蘇鉄を膳に上せることもあれど、上層の社会になると生活の程度多く首里那覇辺に譲らぬと言う話である。