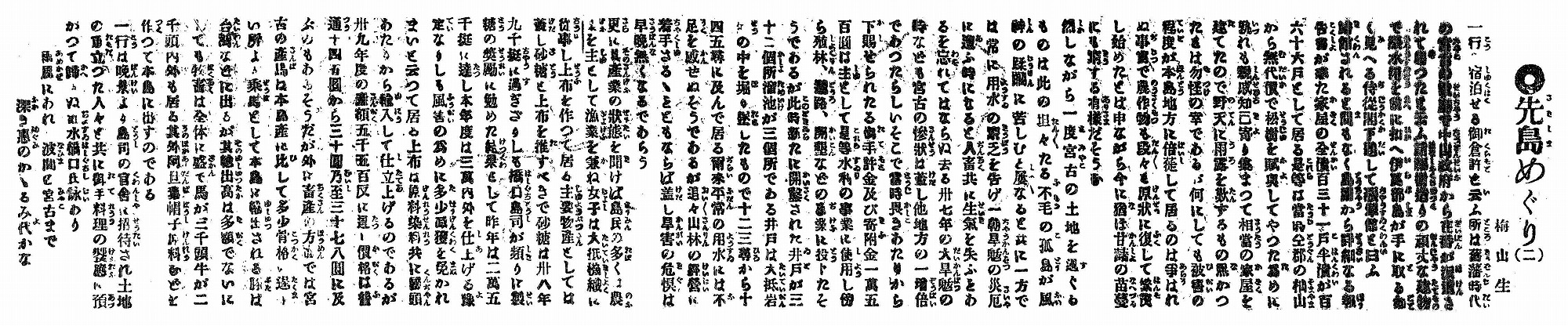キーワード検索
◎先島めぐり(二)
原文表記
◎先島めぐり(ニ)
梅山生
一行の宿泊せる御倉許と云ふ所は舊藩時代の宮古の政廳で中山政府から在藩が派遣されて■つたと云ふ■■■造りの頑丈な建物で漲水港を■に扣へ伊良部島が手に取る如く見へる侍從閣下題して漲翠舘と曰ふ
歸舘されると間もなく島廳から詳細なる報告書が來た家屋の全壊百三十一戸半壊が百六十六戸として居る是等は當時仝郡の杣山から無代價で松樹を賦與してやつた爲めに孰れも親戚知己寄り集まつて相當の家屋を建てたので野天に雨露を歎ずるもの無かつたとは勿怪の幸であるが何にしても被害の程度が本島地方に倍蓰して居るのは争はれぬ事實で農作物も段々と原状に復して繁茂し始めたとは申ながら今に猶ほ甘藷の苗蔓にも窮する有樣だそうな
然しながら一度宮古の土地を過ぐるものは此の坦々たる不毛の孤島が風神の蹂躙に苦しむこと屢なると共に一方では常に用水の窮乏を告げ一朝旱魃の災厄に遭ふ時になると人畜共に生氣を失ふことあるを忘れてはならぬ去る卅七年の大旱魃の時なども宮古の惨状は蓋し他地方の一增倍であつたらしいそこで當時畏きあたりから下賜せられたる御手許金及び寄付金一萬五百圓は主として是等水利の事業に使用し傍ら殖林、道路、開墾などの事業に投じたそうであるが此時新たに開鑿された井戸が三十二個所溜池が三個所である井戸は大抵岩礁の中を掘り墜したのもので十二三尋から一四五尋に及んで居る爾来平常の用水には不足を感ぜぬそうであるが追々山林の經營に着手さるヽをことともならば蓋し旱害の危惧は早晩無くなるであらう
更に其産業の状態を聞けば島民の多くは農業を主として漁業を兼ね女子は大抵機織に從事し上布を作つて居る主要產物としては蓋し砂糖と上布を推すべきで砂糖は卅八年九千挺に過ぎざりしも橋口島司が頻りに製糖の奬勵に勉めた結果として昨年はニ萬五千挺に達し本年度は三萬内外を仕上げる豫定なりしも風害の爲めに多少减獲を免れまいと云つて居る上布は原料染料共に國頭あたりから輸入して仕立上げるのであるが卅九年度の産額五千五百反に達し價格は普通十四五圓から三十圓乃至三十七八圓に及ぶのもあるそうだが外に畜産の方面では宮古の產馬は本島產に比して多少骨格の逞しい所より乗馬として本島に輸出される豚は台灣などに出るが其輸出高は多額でないにしても牧畜は全体に盛んで馬が三千頭牛が二千頭内外も居る其外阿旦葉帽子原料などを作つて本島に出すのである
一行は晩景より島司の官舎に招待され土地の重立つた人々と共に御手料理の饗應に預かつて歸りぬ■水橋口氏詠あり
雨風にあれ■波間の宮古まで
深き恵のかヽるみ代かな
現代仮名遣い表記
◎先島めぐり(ニ)
梅山生
一行の宿泊せる御倉許と云う所は、旧藩時代の宮古の政庁で、中山政府から在藩が派遣されて■ったと云う。■■■造りの頑丈な建物で、漲水港を■に控え伊良部島が手に取る如く見える。侍従閣下題して漲翠舘と曰う。
帰館されると間もなく島庁から詳細なる報告書が来た。家屋の全壊百三十一戸、半壊が百六十六戸として居る。是等は当時同郡の杣山から無代価で松樹を賦与してやった為めに、いづれも親戚知己寄り集まって相当の家屋を建てたので、野天に雨露を歎ずるもの無かったとは勿怪の幸であるが、何にしても被害の程度が本島地方に倍蓰して居るのは争はれぬ事実で、農作物も段々と原状に復して繁茂し始めたとは申ながら、今になお甘藷の苗蔓にも窮する有様だそうな。
しかしながら一度宮古の土地を過ぎるものは、此の坦々たる不毛の孤島が風神の蹂躙に苦しむことしばしばなると共に、一方では常に用水の窮乏を告げ、一朝干ばつの災厄に遭う時になると人畜共に生気を失ふことあるを忘れてはならぬ。去る三十七年の大干ばつの時なども、宮古の惨状はまさしく他地方の一増倍であったらしい。そこで当時、かしこきあたりから下賜せられたる御手許金及び寄付金一万五百円は、主として是等水利の事業に使用し、傍ら植林、道路、開墾などの事業に投じたそうであるが、此時新たに開削された井戸が三十二個所、溜池が三個所である。井戸は大抵岩礁の中を掘り墜したのもので、十二三尋(ひろ)から一四五尋(ひろ)に及んで居る。それ以来、平常の用水には不足を感ぜぬそうであるが、追々山林の経営に着手さるるをことともならば、たしかに干害の危惧は早晩無くなるであろう。
更に其産業の状態を聞けば、島民の多くは農業を主として漁業を兼ね、女子は大抵機織に従事し上布を作って居る。主要産物としては確かに砂糖と上布を推すべきで、砂糖は三十八年九千挺に過ぎざりしも、橋口島司がしきりに製糖の奨励に勉めた結果として昨年はニ万五千挺に達し、本年度は三万内外を仕上げる予定なりしも風害の為めに多少减獲を免れまいと云って居る。上布は原料染料共に国頭あたりから輸入して仕立上げるのであるが、三十九年度の産額五千五百反に達し、価格は普通十四五円から三十円ないし三十七八円に及ぶのもあるそうだが、外に畜産の方面では、宮古の産馬は本島産に比して多少骨格の逞しい所より乗馬として本島に輸出される。豚は台湾などに出るが、其輸出高は多額でないにしても牧畜は全体に盛んで馬が三千頭、牛が二千頭内外も居る。其外、阿旦葉帽子原料などを作って本島に出すのである。
一行は晩景より島司の官舎に招待され、土地の重立つた人々と共に御手料理の饗応に預かって帰りぬ。■水橋口氏詠あり
雨風にあれ■波間の宮古まで
深き恵のかかるみ代かな