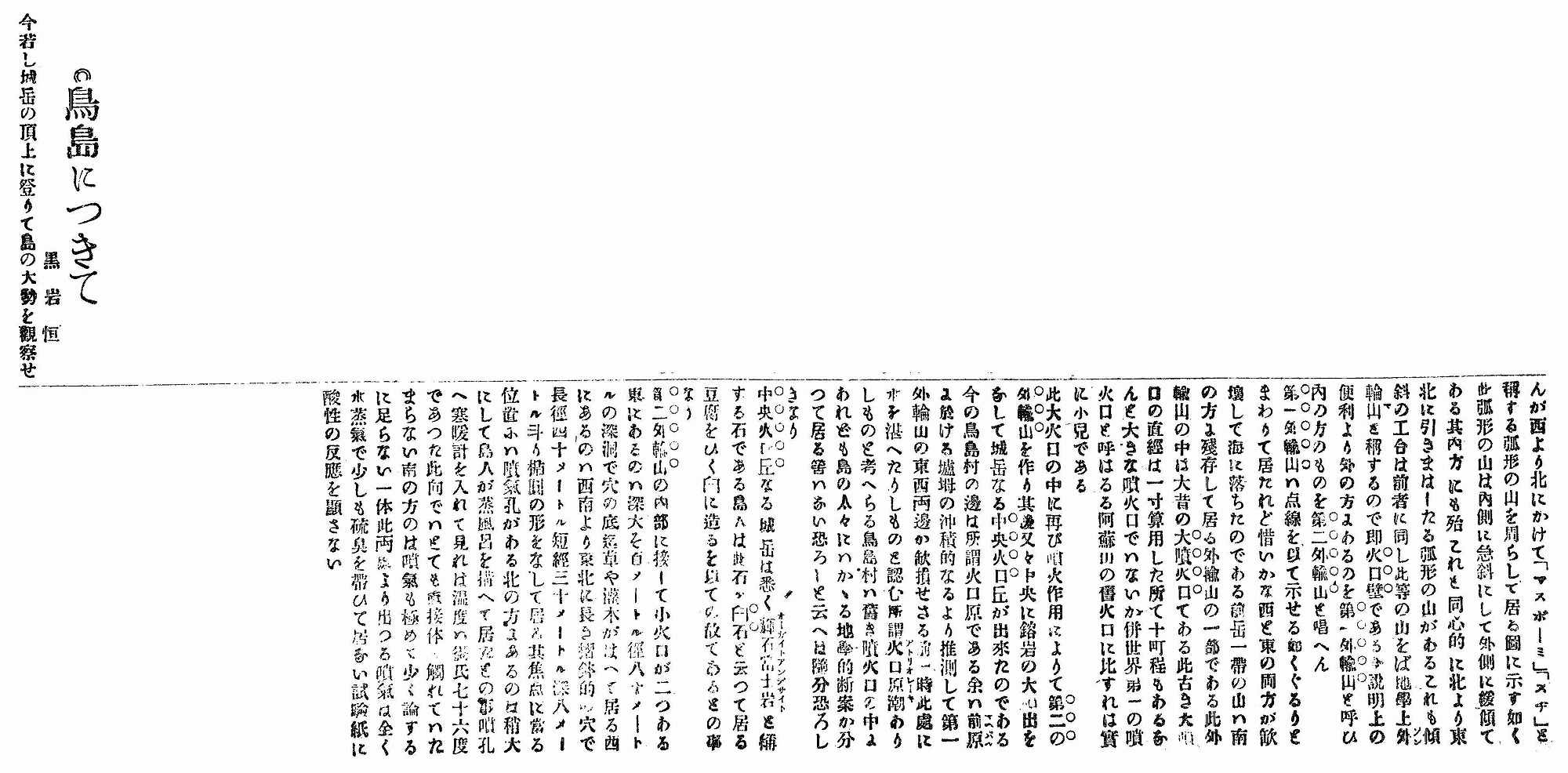キーワード検索
◎鳥島につきて 黑岩恒
原文表記
◎鳥島につきて 黑岩恒
今若し城岳の頂上に登りて島の大勢を觀察せんが西より北にかけて「マスポーミ」「スヂ」と稱する弧形の山を周らして居る圖に示す如く此弧形の山は内側に急斜にして外側に緩傾てある其内方にも殆これを同心的に北より東北に引きまはしたる弧形の山があるこれも傾斜の工合は前者に同し此等の山をば地學上外輪山と稱するので即火口壁である今説明上の便利より外の方にあるの第一外輪山と呼ひ内の方のものを第二外輪山と唱へん
第一外輪山ハ点線を以て示せる如くぐるりとまわりて居たれど惜いかな西と東の両方が缼壤して海に落ちたのである前岳一帶の山ハ南の方に殘存して居る外輪山の一部である此外輪山の中は大昔の大噴火口てある此古き大噴口の直經は一寸算用した所て十町程もあるなんと大きな噴火口でハないか併世界第一の噴火口と呼はるる阿蘇山の舊火口に比すれは實に小兒である
此大火口の中に再び噴火作用によりて第二の外輪山を作り其■又々中央に鎔岩の大噴出をなして城岳なる中央火口岳が出来たのである今の鳥島村の邊は所謂火口原である余は前原に於ける壚拇の沖積的なるより推測して第一外輪山の東西両邊か缼損せさる前一時此處に水を湛へたりしものと認む所謂火口原潮(アトリオレーキ)ありしものと考へらる鳥島村ハ舊き噴火口の中にあれども島の人々にはかゝる地學的断案か分つて居る筈ハない恐ろしと云へは随分恐ろしきなり
中央火口丘なる城岳は悉く輝石富士岩(オーガイトアンデサイト)と稱する石である島人は此石を臼石と云つて居る豆腐をひく臼に造るを似ての故てあるとの事なり
第二外輪山の内部に接して小火口が二つある東にあるのハ深大そ百メートル徑八十メートルの深洞で穴の底迄草や灌木がはへて居る西にあるのハ西南より東北に長き摺鉢的の穴で長徑四十メートル短經三十メートル深八メートル斗り楯圓の形をなして居る其焦点に當る位置にハ噴氣孔がある北の方にあるのは稍大にして島人が蒸風呂を搆へて居たとの事噴孔へ寒暖計を入れて見れは温度ハ摂氏七十六度であつた此向でハとても直接体■觸れてはたまらない南の方のは噴氣も極めて少く論するに足らない一体此両處より出つる噴氣は全く水蒸気で少しも硫臭を帶ひて居ない試驗紙に酸性の反應を顯さない
現代仮名遣い表記
◎鳥島につきて 黒岩恒
今、若し城岳の頂上に登りて島の大勢を観察せんが、西より北にかけて「マスポーミ」「スヂ」と称する弧形の山を周らして居る図に示す如く、この弧形の山は内側に急斜にして外側に緩傾である。その内方にも、ほとほとこれと同心的に北より東北に引きまわしたる弧形の山がある。これも傾斜の工合は前者に同じ此等の山をば地学上外輪山と称するので、即火口壁である。今説明上の便利より、外の方にあるの第一外輪山と呼び、内の方のものを第二外輪山と唱えん。
第一外輪山は点線を以て示せる如くぐるりとまわりて居たれど、惜しいかな西と東の両方が欠壌して海に落ちたのである。前岳一帯の山は南の方に残存して居る外輪山の一部である。この外輪山の中は大昔の大噴火口である、この古き大噴口の直径は一寸算用した所で十町程もある、なんと大きな噴火口ではないか。しかし、世界第一の噴火口と呼ばるる阿蘇山の旧火口に比すれば、実に小児である。
この大火口の中に再び噴火作用によりて第二の外輪山を作り、その■又々中央に鎔岩の大噴出をなして城岳なる中央火口岳が出来たのである。今の鳥島村の辺は所謂火口原である。余は前原に於ける壚拇の沖積的なるより推測して、第一外輪山の東西両辺が欠損せさる前一時此処に水を湛えたりしものと認む。所謂、火口原潮(アトリオレーキ)ありしものと考えらる。鳥島村は旧き噴火口の中にあれども、島の人々にはかかる地学的断案が分って居る筈はない、恐ろしといえば随分恐ろしきなり。
中央火口丘なる城岳は、ことごとく輝石富士岩(オーガイトアンデサイト)と称する石である。島人は此石を臼石と云って居る、豆腐をひく臼に造るを似ての故であるとの事なり。
第二外輪山の内部に接して、小火口が二つある。東にあるのは深大そ百メートル径八十メートルの深洞で、穴の底まで草や灌木がはえて居る。西にあるのは西南より東北に長き摺鉢的の穴で、長径四十メートル短経三十メートル深八メートル斗り楯円の形をなして居る。その焦点に当る位置には噴気孔がある、北の方にあるのは稍大にして島人が蒸風呂を搆えて居たとの事、噴孔へ寒暖計を入れて見れば温度は摂氏七十六度であった、此向ではとても直接体■触れてはたまらない。南の方のは噴気も極めて少く、論するに足らない。一体此両処より出づる噴気は全く水蒸気で少しも硫臭を帯びて居ない、試験紙に酸性の反応を顕さない。