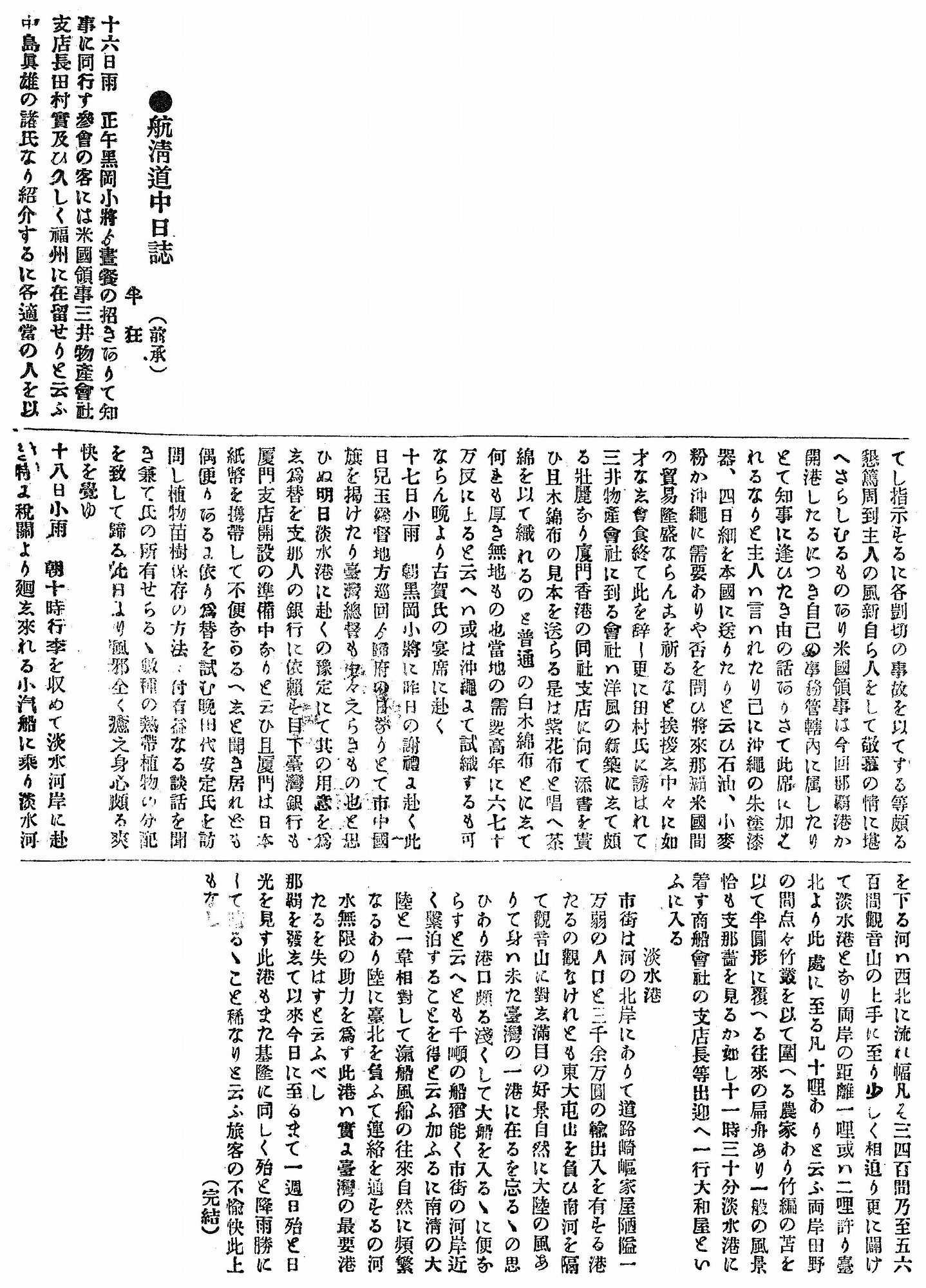キーワード検索
雜 報 ●航淸道中日誌(前承)
原文表記
●航淸道中日誌 (前承)
半 狂
十六日雨 正午黒岡小將より晝餐の招きありて知事に同行す參會の客には米國領事三井物產會社支店長田村實及ひ久しく福州に在留せりと云ふ中島眞雄の諸氏なり紹介するに各適當の人を以て指示するに各剴切の事故を以てする等頗る懇篤周到主人の風新自ら人をして敬慕の情に堪へさらしむるものあり米國領事は今回那覇港が開港したるにつき自己の事務管轄内に属したりとて知事に逢いたき由の話ありさて此席に加はれるなりと主人ハ言ハれたり己に沖繩の朱塗漆器、四日細を本國に送りたりと云ひ石油、小麥粉か沖繩に需要ありや否を問ひ将來那覇米國間の貿易隆盛ならんことを祈るなと挨拶し中々に如才な志會食終て此を辞し更に田村氏に誘はれて三井物產會社に到る會社ハ洋風の新築にして頗る壮麗なり厦門香港の同社支店に向いて添書を貰ひ且木綿布の見本を送らる是は紫花布と唱へ茶綿を以て織れるのと普通の白木綿布とに志て何れも厚き無地もの也當地の需要高年に六七十万反に上ると云へハ或は沖繩にて試織するも可ならん晩より古賀氏の宴席に赴く
十七日小雨 朝黒岡小將に昨日の謝禮に赴く此日兒玉総督地方巡回より歸府の日なりとて市中國旗を掲けたり臺灣總督も■々えらきもの也と思ひぬ明日淡水港に赴くの豫定にて其の用意を爲し爲替を支那人の銀行に依頼す目下臺灣銀行も厦門支店の開設の準備中なりと云ひ且厦門は日本紙幣を携帶して不便なかる経志と聞き居れども偶便りあるに依り爲替を試む晩田代安定氏を訪問し植物苗樹保存の方法に付有益なる談話を聞き兼て氏の所有せらるヽ數種の𤍠帯植物の分配を致して歸る此日より風邪全く癒え身心頗る爽快を覺ゆ
十八日小雨 朝十時行李を収めて淡水河岸に赴き特に税關より廻し來れる小汽船に乘り淡水河を下る河ハ西北に流れ幅凡そ三四百間乃至五六百間観音山の上手に至り少しく相迫り更に闢けて淡水港となり両岸の距離一哩或ハ二哩許り臺北より此處に至る凡十哩ありと云ふ両岸田野の間点々竹叢を以て圍へる農家あり竹編の苫を以て半圓形に覆へる往來の扁舟あり一般の風景恰も支那畫を見るか如し十一時三十分淡水港に着す商船會社の支店長等出迎へ一行大和屋といふに入る
淡水港
市街は河の北岸にありて道路崎嶇家屋陋隘一万弱の人口と三千余万圓の輸出入を有する港たるの觀なけれとも東大屯山を負ひ南河を隔て觀音山に對し滿目の好景自然に大陸の風ありて身は未た臺灣の一港に在るを忘るヽの思ひあり港口頗る淺くして大船を入るヽに便ならすと云へとも千噸の船猶能く市街の河岸近く繋泊することを得と云ふ加ふるに南淸の大陸と一韋相對して滊船風船の往來自然に頻繁なるあり陸に臺北を負ふて連絡を通するの河水無限の助力を為す此港ハ實に臺灣の最要港たるを失はすと云ふべし
那覇を發志て以來今日に至るまて一週日殆と日光を見す此港もまた基隆に同しく殆と降雨勝にして■るヽこと稀なりと云ふ旅客の不愉快此上もなし (完結)
現代仮名遣い表記
●航清道中日誌 (前承)
半 狂
十六日雨 正午黒岡小将より昼餐の招きありて知事に同行す。参会の客には米国領事、三井物産会社支店長田村実、及び久しく福州に在留せりと云う中島真雄の諸氏なり。紹介するに各適当の人を以て指示するに各剴切の事故を以てする等、頗る懇篤周到主人の風新自ら人をして敬慕の情に堪へざらしむるものあり。米国領事は、今回那覇港が開港したるにつき、自己の事務管轄内に属したりとて知事に逢いたき由の話あり。さて此席に加はれるなりと主人は言はれたり、己に沖縄の朱塗漆器、四日細を本国に送りたりと云い石油、小麦粉が沖縄に需要ありや否を問ひ、将来那覇米国間の貿易隆盛ならんことを祈るなど挨拶し、中々に如才なし会食終て此を辞し、更に田村氏に誘われて三井物産会社に到る。会社は洋風の新築にして頗る壮麗なり。厦門香港の同社支店に向いて添書を貰い且木綿布の見本を送らる。是は紫花布と唱え茶綿を以て織れるのと、普通の白木綿布とにして何れも厚き無地もの也。当地の需要高年に六七十万反に上ると云えば、或は沖縄にて試織するも可ならん。晩より古賀氏の宴席に赴く。
十七日小雨 朝、黒岡小将に昨日の謝礼に赴く。此日、児玉総督地方巡回より帰府の日なりとて、市中国旗を掲げたり。台湾総督も■々えらきもの也と思いぬ。明日淡水港に赴くの予定にて其の用意を為し、為替を支那人の銀行に依頼す。目下、台湾銀行も厦門支店の開設の準備中なりと云い、且厦門は日本紙幣を携帯して不便なかるべしと聞き居れども、偶便りあるに依り為替を試む。晩、田代安定氏を訪問し植物苗樹保存の方法に付有益なる談話を聞き兼て氏の所有せらるヽ数種の熱帯植物の分配を致して帰る。此日より風邪全く癒え、身心頗る爽快を覚ゆ。
十八日小雨 朝十時、行李を収めて淡水河岸に赴き、特に税関より廻し来れる小汽船に乗り淡水河を下る。河は西北に流れ、幅凡そ三四百間乃至五六百間、観音山の上手に至り少しく相迫り更に闢けて淡水港となり。両岸の距離一哩或は二哩許り、台北より此処に至る凡十哩ありと云う。両岸田野の間点々竹叢を以て囲える農家あり、竹編の苫を以て半円形に覆える往来の扁舟あり。一般の風景恰も支那画を見るが如し。十一時三十分淡水港に着す、商船会社の支店長等出迎え一行大和屋というに入る。
淡水港
市街は河の北岸にありて、道路崎嶇家屋陋隘一万弱の人口と三千余万円の輸出入を有する港たるの観なけれども、東大屯山を負ひ、南河を隔て、観音山に対し満目の好景自然に大陸の風ありて、身は未だ台湾の一港に在るを忘るるの思いあり。港口頗る浅くして大船を入るるに便ならずと云えども、千噸の船猶能く市街の河岸近く繋泊することを得と云う。加うるに南清の大陸と一韋相対して汽船風船の往来自然に頻繁なるあり。陸に台北を負うて連絡を通ずるの河水、無限の助力を為す。此港は実に台湾の最要港たるを失わずと云うべし。
那覇を発して以来、今日に至るまで一週日殆ど日光を見ず、此港もまた基隆に同じく殆ど降雨勝にして■るること稀なりと云う、旅客の不愉快此上もなし。 (完結)