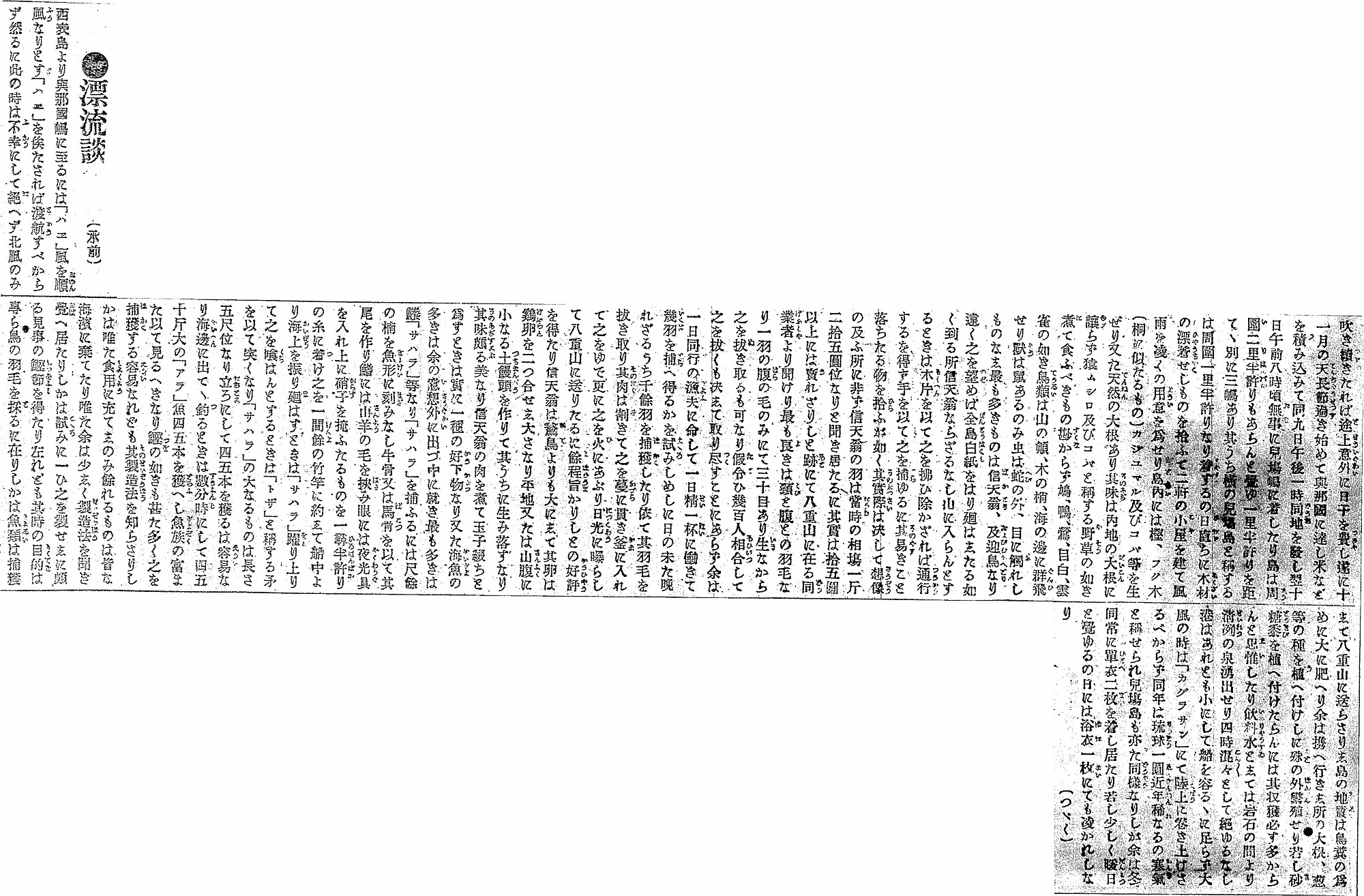キーワード検索
●漂流談
原文表記
●漂流談(承前)
西表島より與那國嶋に至るには「ハエ」風を順風なりとす「ハエ」を俟たされば渡航すべからず然るに此の時は不幸にして絶へず北風のみ吹き続きたれば途上意外に日干を費し遂に十一月の天長節過き始めて與那國に達し米などを積み込みて同九日午後一時同地を發し翌十日午前八時頃無事に兒塲嶋に着したり島は周圍二里半許りもあらんと覺ゆ一里半許りを距てヽ別に三嶋あり其うち横の兒塲島と稱するは周圍一里半許りなり■するの日直ちに木材の漂着せしものを拾ふて二軒の小屋を建て風雨を凌ぐの用意を爲せり島内には樫、フク木(桐に似たるもの)ガジュマル及びコバ等を生ぜり又た天然の大根あり其味は内地の大根に讓らず猿ムシロ及びコバと稱する野草の如き煮て食ふべきもの尠からず鳩、鴨、鶯、目白、雲雀の如き鳥類は山の■、木の梢、海の邊に群飛せり獸は鼠あるのみ虫は蛇の外、目に觸れしものなし最も多きものは信天翁、及迎鳥なり遠く之を望めば全島白紙をはり廻はしたる如く至る所信天翁ならざるなし山に入らんとするときは木片を以て之を拂ひ除かざれば通行するを得ず手を以て之を捕ゆるに其易きこと落ちたる物を拾ふが如く其實際は決して想像の及ふ所に非ず信天翁の羽は當時の相塲一斤二拾五圓位なりと聞き居たるに其實は拾五圓以上には賣れざりしと跡にて八重山に在る同業者より聞けり最も良きは頸と腹との羽毛なり一羽の腹の毛のみにて三十目あり生なから之を抜き取るも可なり假令ひ幾百人相合して之を拔くも決して取り尽すことにあらず余は一日同行の漁夫に命して一日精一杯に働きて幾羽を捕へ得るかを試みしめしに日の未た晩れざるうち千餘羽を捕獲したり依て其羽毛を抜き取り其肉は割きて之を蔓に貫き釜に入れて之をゆで更に之を火にあぶり日光に曝らして八重山に送りたるに餘程旨かりしとの好評を得たり信天翁は鷲鳥よりも大にして其卵は鶏卵を二つ合せし大さなり平地又たは山腹に小なる土饅頭を作りて其うちに生み落すなり其味頗る美なり信天翁の肉を煮て玉子綴ちを爲すときは實に一種の好下物なり又た海魚の多きは余の意想外に出づ中に就き最も多きは鱶「サハラ」等なり「サハラ」を捕ふるには尺餘の楠を魚形に刻みなし牛骨又は馬骨を以て其尾を作り鱰には山羊の毛を挟み眼には夜光具を入れ上に硝子を掩ふたるものを一尋半許りの糸に着け之を一間餘の竹竿に約して船中より海上を振り廻はすときは「サハラ」踊り上りて之を喰はんとするときは「トザ」と稱する矛を以て突くなり「サハラ」の大なるものは長さ五尺位なり立ちにして四五本を獲るは容易なり海邊に出てヽ釣るときは數分時にして四五十斤大の「アラ」魚四五本を獲へし魚族の富また以て見るへきなり鰹の如きも甚た多く之を捕獲する容易なれども其製造法を知らさりしかは唯た食用に充てしのみ餘れるものは皆な海濱に棄てたり唯た余は少しく製造法を聞き覺へ居たりしかは試みに一ひ之を製せしに頗る見事の鰹節を得たり左れども其時の目的は専ら鳥の羽毛を採るに在りしかは魚類は捕獲して八重山に送らさりし島の地質は鳥糞の爲めに大に肥へり余は携へ行き去所の大根、葱等の種を植へ付けしに殊の外繁殖せり若し砂糖黍を植へ付けたらんには其収穫必ず多からんと思惟したり飲料水としては岩石の間より淸冽の泉湧出せり四時混々として絕ゆるなし港はあれとも小にして船を容るヽに足らず大風の時は「カグヲサン」にて陸上に巻き上げさるべからず同年は琉球一圓近年稀なるの寒氣と稱せられ兒塲島も亦た同樣なりしが余は冬同常に單衣二枚を着し居たり若し少しく暖日と覺ゆるの日には浴衣一枚にても凌かれしなり (つヾく)
現代仮名遣い表記
●漂流談(承前)
西表島より与那国嶋に至るには「ハエ」風を順風なりとす「ハエ」を俟たされば渡航すべからず然るに此の時は不幸にして絶へず北風のみ吹き続きたれば途上意外に日干を費し遂に十一月の天長節過き始めて与那国に達し米などを積み込みて同九日午後一時同地を発し翌十日午前八時頃無事に児塲嶋に着したり島は周囲二里半許りもあらんと覚ゆ一里半許りを距てて、別に三嶋あり其うち横の児塲島と称するは周囲一里半許りなり■するの日直ちに木材の漂着せしものを拾ふて二軒の小屋を建て風雨を凌ぐの用意を為せり島内には樫、フク木(桐に似たるもの)ガジュマル及びコバ等を生ぜり又た天然の大根あり其味は内地の大根に譲らず猿ムシロ及びコバと称する野草の如き煮て食ふべきもの尠からず鳩、鴨、鶯、目白、雲雀の如き鳥類は山の■、木の梢、海の辺に群飛せり獣は鼠あるのみ虫は蛇の外、目に触れしものなし最も多きものは信天翁、及迎鳥なり遠く之を望めば全島白紙をはり廻はしたる如く至る所信天翁ならざるなし山に入らんとするときは木片を以て之を払ひ除かざれば通行するを得ず手を以て之を捕ゆるに其易きこと落ちたる物を拾ふが如く其実際は決して想像の及ふ所に非ず信天翁の羽は当時の相塲一斤二拾五円位なりと聞き居たるに其実は拾五円以上には売れざりしと跡にて八重山に在る同業者より聞けり最も良きは頸と腹との羽毛なり。一羽の腹の毛のみにて三十目あり生なから之を抜き取るも可なり仮令ひ幾百人相合して之を抜くも決して取り尽すことにあらず余は一日同行の漁夫に命して一日精一杯に働きて幾羽を捕へ得るかを試みしめしに日の未た晩れざるうち千余羽を捕獲したり依て其羽毛を抜き取り其肉は割きて之を蔓に貫き釜に入れて之をゆで更に之を火にあぶり日光に曝らして八重山に送りたるに余程旨かりしとの好評を得たり信天翁は鷲鳥よりも大にして其卵は鶏卵を二つ合せし大さなり。平地又たは山腹に小なる土饅頭を作りて其うちに生み落すなり其味頗る美なり信天翁の肉を煮て玉子綴ちを為すときは実に一種の好下物なり又た海魚の多きは余の意想外に出づ中に就き最も多きは鱶「サハラ」等なり「サハラ」を捕ふるには尺余の楠を魚形に刻みなし牛骨又は馬骨を以て其尾を作り鱰には山羊の毛を挟み眼には夜光具を入れ上に硝子を掩ふたるものを一尋半許りの糸に着け之を一間余の竹竿に約して船中より海上を振り廻はすときは「サハラ」踊り上りて之を喰はんとするときは「トザ」と称する矛を以て突くなり。「サハラ」の大なるものは長さ五尺位なり立ちにして四五本を獲るは容易なり。海辺に出てて釣るときは数分時にして四五十斤大の「アラ」魚四五本を獲へし魚族の富また以て見るへきなり。鰹の如きも甚た多く之を捕獲する容易なれども其製造法を知らさりしかは唯た食用に充てしのみ余れるものは皆な海浜に棄てたり唯た余は少しく製造法を聞き覚へ居たりしかは試みに一ひ之を製せしに頗る見事の鰹節を得たり左れども其時の目的は専ら鳥の羽毛を採るに在りしかは魚類は捕獲して八重山に送らさりし島の地質は鳥糞の為めに大に肥へり余は携へ行き去所の大根、葱等の種を植へ付けしに殊の外繁殖せり若し砂糖黍を植へ付けたらんには其収穫必ず多からんと思惟したり飲料水としては岩石の間より清冽の泉湧出せり四時混々として絶ゆるなし港はあれとも小にして船を容るるに足らず。大風の時は「カグヲサン」にて陸上に巻き上げさるべからず。同年は琉球一円近年稀なるの寒気と称せられ児塲島も亦た同様なりしが余は冬同常に単衣二枚を着し居たり若し少しく暖日と覚ゆるの日には浴衣一枚にても凌かれしなり (つづく)