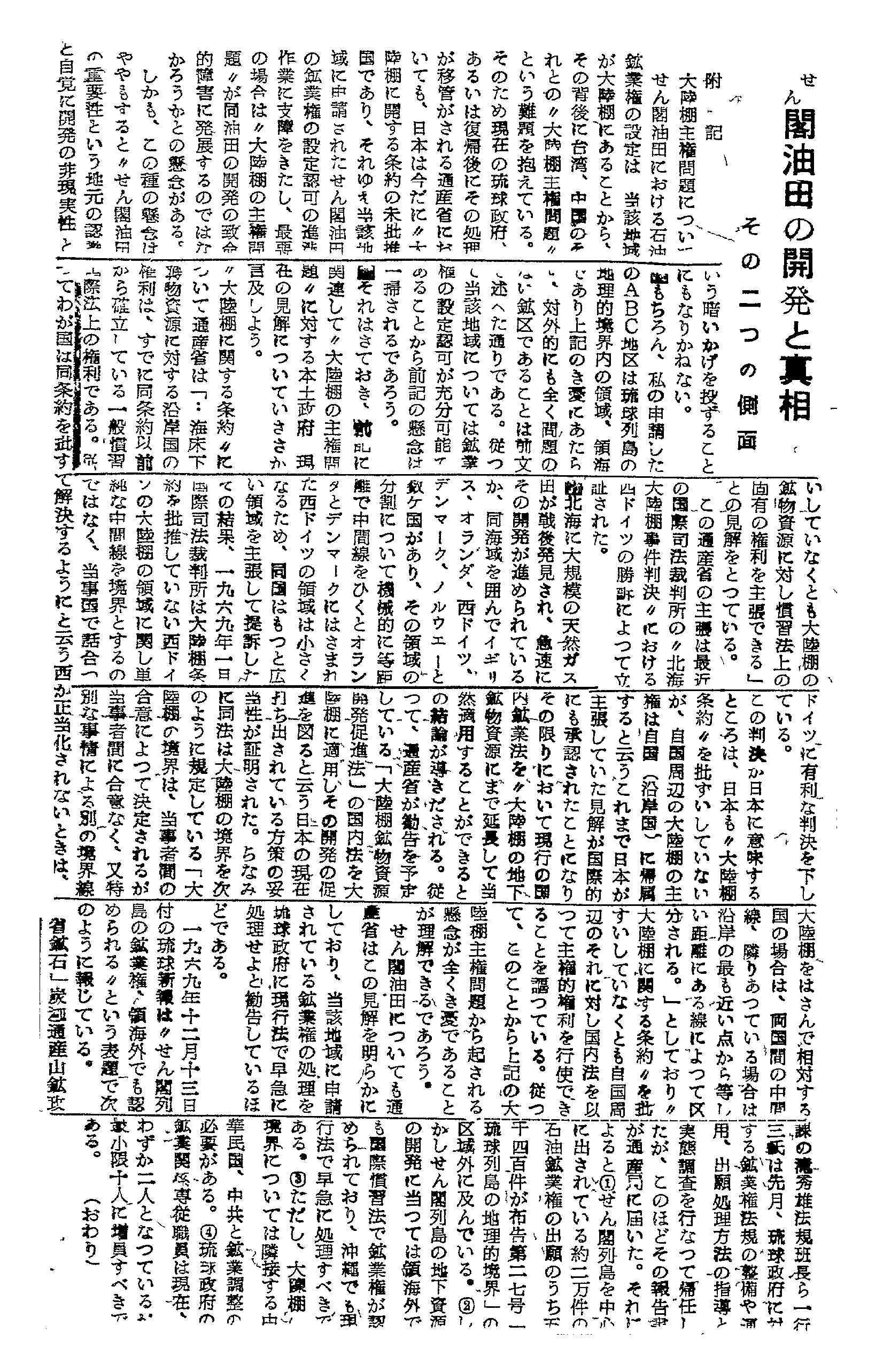キーワード検索
せん閣油田の開発と真相/ その二つの側面
原文表記
せん閣油田の開発と真相 その二つの側面
南西新報 昭和四十五年八月二十五日
附 記
大陸棚主権問題について
せん閣油田における石油鉱業権の設定は、当該地域が大陸棚にあることから、其の背後に台湾、中国のそれとの〝大陸棚主権問題〟という難題を抱えている。そのため現在の琉球政府、あるいは復帰後にその処理が移管がされる通産省においても、日本は今だに〝大陸棚に開する条約の未批准国であり、それゆえ当該地域に申請されたせん閣油田の鉱業権の設定認可の進捗作業に支障をきたし、最悪の場合は〝大陸棚の主権問題〟が同油田の開発の致命的障害に発展するのではなかろうかとの懸念がある。
しかも、この種の懸念はややもすると〝せん閣油田の重要性という地元の認■と自覚に開発の非現実性という暗いかげを投ずることにもなりかねない。
もちろん、私の申請したのABC地区は琉球列島の地理的境界内の領域、領海であり上記のき憂にあたら■、対外的にも全く問題のない鉱区であることは前文■述べた通りである。従つて当該地域については鉱業権の設定認可が充分可能であることから前記の懸念は一掃されるであろう。
それはさておき、前記に関連して〝大陸棚の主権問題〟に対する本土政府 現在の見解についていささか言及しよう。
〝大陸棚に関する条約〟について通産省は「…海床下鉱物資源に対する沿岸国の権利は、すでに同条約以前から確立している一般慣習■際法上の権利である。従つてわが国は同条約を批すいしていなくとも大陸棚の鉱物資源に対し慣習法上の固有の権利を主張できる」との見解をとつている。
この通産省の主張は最近の国際司法裁判所の〝北海大陸棚事件判決〟における西ドイツの勝訴によつて立証された。
北海に大規模の天然ガス田が戦後発見され、急速にその開発が進められているが、同海域を囲んでイギリス、オランダ、西ドイツ、デンマーク、ノルウエーと数ケ国があり、その領域の分割について機械的に等距離で中間線をひくとオランダとデンマークにはさまれた西ドイツの領域は小さくなるため、同国はもつと広い領域を主張して提訴したその結果、一九六九年一月国際司法裁判所は大陸棚条約を批准していない西ドイツの大陸棚の領域に関し単純な中間線を境界とするのではなく、当事国で話合つて解決するようにと云う西ドイツに有利な判決を下している。
この判決が日本に意味するところは、日本も〝大陸棚条約〟を批すいしていないが、自国周辺の大陸棚の主権は自国(沿岸国)に帰属すると云うこれまで日本が主張していた見解が国際的にも承認されたことになりその限りにおいて現行の国内鉱業法を〝大陸棚の地下鉱物資源にまで延長して当然適用することができるとの結論が導きだされる。従つて、通産省が勧告を予定している「大陸棚鉱物資源開発促進法」の国内法を大陸棚に適用しその開発の促進を図ると云う日本の現在打ち出されている方策の妥当性が証明された。ちなみに同法は大陸棚の境界を次のように規定している「大陸棚の境界は、当事者間の合意なく、又特別な事情による別の境界線が正当化されないときは、大陸棚をはさんで相対する国の場合は、両国間の中間線、隣りあつている場合は沿岸の最も近い点から等しい距離にある線によつて区分される。」としており〝大陸棚に関する条約〟を批すいしていなくとも自国周辺のそれに対し国内法を以つて主権的権利を行使できることを謳つている。従つて、このことから上記の大陸棚主権問題から起される懸念が全くき憂であることが理解できるであろう。
せん閣油田についても通産省はこの見解を明らかにしており、当該地域に申請されている鉱業権の処理を琉球政府に現行法で早急に処理せよと勧告しているほどである。
一九六九年十二月十三日付の琉球新報は〝せん閣列島の鉱業権、領海外でも認められる〟という表題で次のように報じている。
省鉱石」炭■通産山鉱政課の滝秀雄法規班長ら一行三氏は先月、琉球政府に対する鉱業権法規の整備や運用、出願処理方法の指導と実態調査を行つて帰任したが、このほどその報告書が通産局に届いた。それによると①せん閣列島を中心に出されている約二万件の石油鉱業権の出願のうち五千四百件が布告第二七号「琉球列島の地理的境界」の区域外に及んでいる。②しかしせん閣列島の地下資源の開発に当つては領海外でも国際慣習法で鉱業権が認められており、沖繩でも現行法で早急に処理すべきである。③ただし、大陸棚■境界については隣接する中華民国、中共と鉱業調整の必要がある。④琉球政府の鉱業関係専従職員は現在、わずか二人となつているが最小限十人に増員すべきである。
(おわり)
現代仮名遣い表記
せん閣油田の開発と真相 その二つの側面
南西新報 昭和四十五年八月二十五日
附 記
大陸棚主権問題について
せん閣油田における石油鉱業権の設定は、当該地域が大陸棚にあることから、其の背後に台湾、中国のそれとの〝大陸棚主権問題〟という難題を抱えている。そのため現在の琉球政府、あるいは復帰後にその処理が移管がされる通産省においても、日本は未だに〝大陸棚に関する条約の未批准国であり、それゆえ当該地域に申請されたせん閣油田の鉱業権の設定認可の進捗作業に支障をきたし、最悪の場合は〝大陸棚の主権問題〟が同油田の開発の致命的障害に発展するのではなかろうかとの懸念がある。
しかも、この種の懸念はややもすると〝せん閣油田の重要性という地元の認■と自覚に開発の非現実性という暗いかげを投ずることにもなりかねない。
もちろん、私の申請したABC地区は、琉球列島の地理的境界内の領域、領海であり、上記のき憂にあたら■、対外的にも全く問題のない鉱区であることは前文■述べた通りである。従って当該地域については鉱業権の設定認可が充分可能であることから、前記の懸念は一掃されるであろう。
それはさておき、前記に関連して〝大陸棚の主権問題〟に対する本土政府 現在の見解についていささか言及しよう。
〝大陸棚に関する条約〟について通産省は「…海床下鉱物資源に対する沿岸国の権利は、すでに同条約以前から確立している一般慣習■際法上の権利である。従ってわが国は同条約を批すいしていなくとも大陸棚の鉱物資源に対し慣習法上の固有の権利を主張できる」との見解をとっている。
この通産省の主張は最近の国際司法裁判所の〝北海大陸棚事件判決〟における西ドイツの勝訴によって立証された。
北海に大規模の天然ガス田が戦後発見され、急速にその開発が進められているが、同海域を囲んでイギリス、オランダ、西ドイツ、デンマーク、ノルウェーと数ヶ国があり、その領域の分割について機械的に等距離で中間線をひくと、オランダとデンマークにはさまれた西ドイツの領域は小さくなるため、同国はもっと広い領域を主張して提訴したその結果、一九六九年一月、国際司法裁判所は大陸棚条約を批准していない西ドイツの大陸棚の領域に関し、単純な中間線を境界とするのではなく、当事国で話合って解決するようにと言う西ドイツに有利な判決を下している。
この判決が日本に意味するところは、日本も〝大陸棚条約〟を批すいしていないが、自国周辺の大陸棚の主権は自国(沿岸国)に帰属すると言うこれまで日本が主張していた見解が国際的にも承認されたことになり、その限りにおいて現行の国内鉱業法を〝大陸棚の地下鉱物資源にまで延長して当然適用することができるとの結論が導きだされる。従って、通産省が勧告を予定している「大陸棚鉱物資源開発促進法」の国内法を大陸棚に適用し、その開発の促進を図ると言う日本の現在打ち出されている方策の妥当性が証明された。ちなみに同法は大陸棚の境界を次のように規定している。「大陸棚の境界は、当事者間の合意なく、又特別な事情による別の境界線が正当化されないときは、大陸棚をはさんで相対する国の場合は、両国間の中間線、隣りあっている場合は沿岸の最も近い点から等しい距離にある線によって区分される。」としており〝大陸棚に関する条約〟を批すいしていなくとも自国周辺のそれに対し国内法を以って主権的権利を行使できることを謳っている。従って、このことから上記の大陸棚主権問題から起される懸念が全くき憂であることが理解できるであろう。
せん閣油田についても通産省はこの見解を明らかにしており、当該地域に申請されている鉱業権の処理を琉球政府に現行法で早急に処理せよと勧告しているほどである。
一九六九年十二月十三日付の琉球新報は〝せん閣列島の鉱業権、領海外でも認められる〟という表題で次のように報じている。
省鉱石」炭■通産山鉱政課の滝秀雄法規班長ら一行三氏は先月、琉球政府に対する鉱業権法規の整備や運用、出願処理方法の指導と実態調査を行って帰任したが、このほどその報告書が通産局に届いた。それによると①せん閣列島を中心に出されている約二万件の石油鉱業権の出願のうち五千四百件が布告第二七号「琉球列島の地理的境界」の区域外に及んでいる。②しかしせん閣列島の地下資源の開発に当っては領海外でも国際慣習法で鉱業権が認められており、沖縄でも現行法で早急に処理すべきである。③ただし、大陸棚■境界については隣接する中華民国、中共と鉱業調整の必要がある。④琉球政府の鉱業関係専従職員は現在、わずか二人となっているが、最小限十人に増員すべきである。
(おわり)