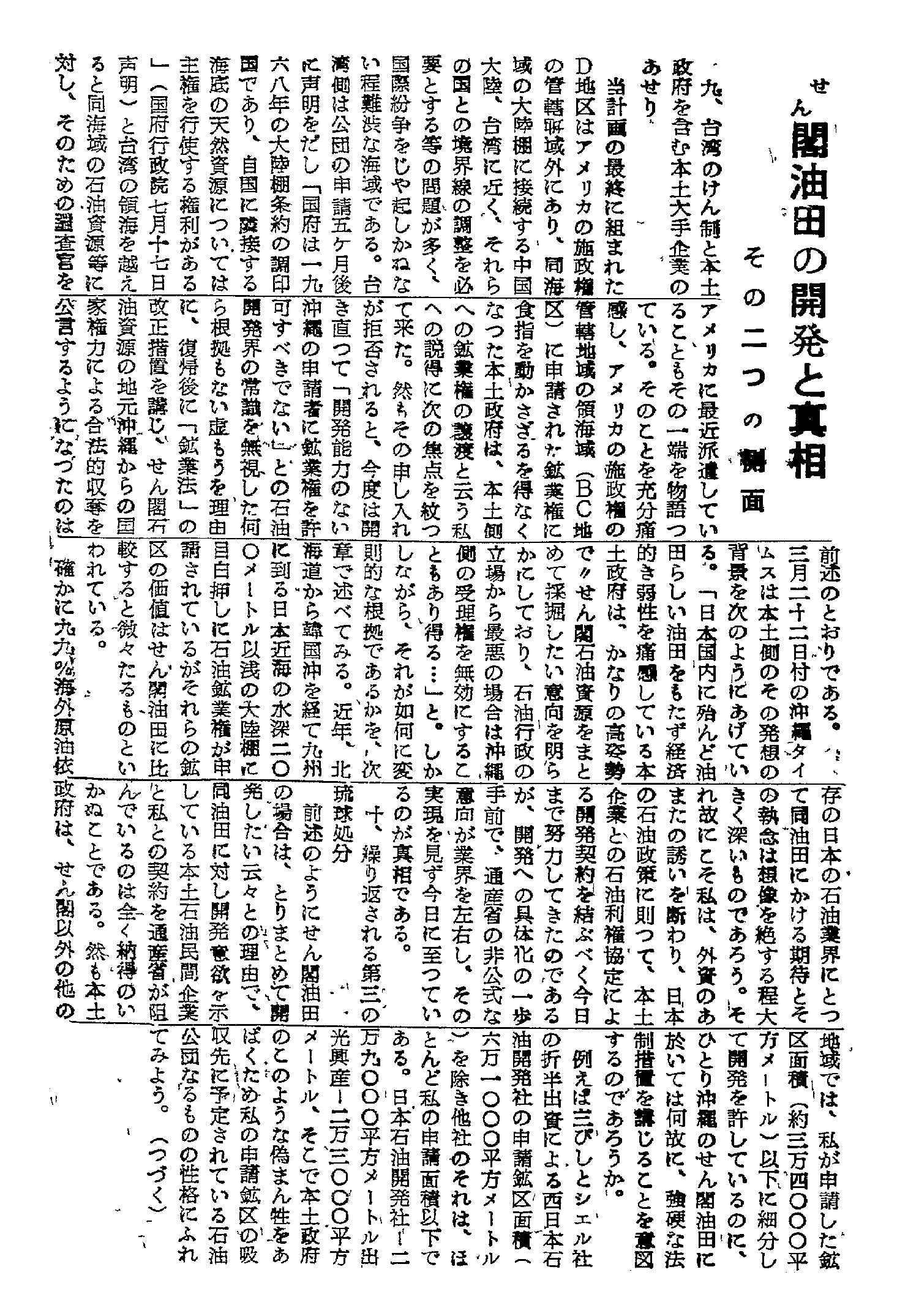キーワード検索
せん閣油田の開発と真相/ その二つの側面
原文表記
せん閣油田の開発と真相 その二つの側面
南西新報 昭和四十五年八月十九日
九、台湾のけん制と本土政府を含む本土大手企業のあせり
当計画の最終に組まれたD地区はアメリカの施政権の管轄地域外にあり、同海域の大陸棚に接続する中国大陸、台湾に近く、それらの国との境界線の調整を必要とする等の問題が多く、国際紛争をじや起しかねない程難渋な海域である。台湾側は公団の申請五ケ月後に声明を出し「国府は一九六八年の大陸棚条約の調印国であり、自国に隣接する海底の天然資源については主権を行使する権利がある」(国府行政院七月十七日声明)と台湾の領海を越えると同海域の石油資源等に対し、そのための調査官をアメリカに最近派遣していることもその一端を物語つている。そのことを充分痛感し、アメリカの施政権管轄地域の領海域(BC地区)に申請された鉱業権に食指を動かさざるを得なくなつた本土政府は、本土側への鉱業権の譲渡と云う私への説得に次の焦点を絞つて来た。然もその申し入れが拒否されると、今度は開き直つて「開発能力のない沖繩の申請者に鉱業権を許可すべきでない」との石油開発界の常識を無視した何ら根拠もない虚もうを理由に、復帰後に「鉱業法」の改正措置を講じ、せん閣石油資源の地元沖繩からの国家権力による合法的収奪を公言するようになつたのは前述のとおりである。
三月二十二日付の沖繩タイムスは本土側のその発想の背景を次のようにあげている。「日本国内に殆んど油田らしい油田をもたず経済的き弱性を痛感している本土政府は、かなりの高姿勢で〝せん閣石油資源をまとめて採掘したい意向を明らかにしており、石油行政の立場から最悪の場合は沖繩側の受理権を無効にすることもあり得る…」と。しかしながら、それが如何に変則的な根拠であるかを、次章で述べてみる。近年、北海道から韓国沖を経て九州に到る日本近海の水深二〇〇メートル以浅の大陸棚に目白押しに石油鉱業権が申請されているがそれらの鉱区の価値はせん閣油田に比較すると微々たるものといわれている。
確かに九九%海外原油依存の日本の石油業界にとつて同油田にかける期待とその執念は想像を絶する程大きく深いものであろう。それ故にこそ私は、外資のあまたの誘いを断わり、日本の石油政策に則つて、本土企業との石油利権協定による開発契約を結ぶべく今日まで努力してきたのであるが、開発への具体化の一歩手前で、通産省の非公式な意向が業界を左右し、その実現を見ず今日に至つているのが真相である。
十、繰り返される第三の琉球処分
前述のようにせん閣油田の場合は、とりまとめて開発したい云々との理由で、同油田に対し開発意欲を示している本土石油民間企業と私との契約を通産省が阻んでいるのは全く納得のいかぬことである。然も本土政府は、せん閣以外の他の地域では、私が申請した鉱区面積(約三万四〇〇〇平方メートル)以下に細分して開発を許しているのに、ひとり沖繩のせん閣油田に於いては何故に、強硬な法制措置を講じることを意図するのであろうか。
例えば三びしとシエル社の折半出資による西日本石油開発社の申請鉱区面積(六万一〇〇〇平方メートル)を除き他社のそれは、ほとんど私の申請面積以下である。日本石油開発社―二万九〇〇〇平方メートル出光興産―二万三〇〇〇平方メートル、そこで本土政府のこのような偽まん牲をあばくため私の申請鉱区の吸収先に予定されている石油公団なるものの性格にふれてみよう。
(つづく)
現代仮名遣い表記
せん閣油田の開発と真相 その二つの側面
南西新報 昭和四十五年八月十九日
九、台湾のけん制と本土政府を含む本土大手企業のあせり
当計画の最終に組まれたD地区はアメリカの施政権の管轄地域外にあり、同海域の大陸棚に接続する中国大陸、台湾に近く、それらの国との境界線の調整を必要とする等の問題が多く、国際紛争をじゃっ起しかねない程難渋な海域である。台湾側は公団の申請五ヶ月後に声明を出し「国府は一九六八年の大陸棚条約の調印国であり、自国に隣接する海底の天然資源については主権を行使する権利がある」(国府行政院七月十七日声明)と台湾の領海を越えると同海域の石油資源等に対し、そのための調査官をアメリカに最近派遣していることもその一端を物語っている。そのことを充分痛感し、アメリカの施政権管轄地域の領海域(BC地区)に申請された鉱業権に食指を動かさざるを得なくなった本土政府は、本土側への鉱業権の譲渡と言う私への説得に次の焦点を絞って来た。然もその申し入れが拒否されると、今度は開き直って「開発能力のない沖縄の申請者に鉱業権を許可すべきでない」との石油開発界の常識を無視した何ら根拠もない虚もうを理由に、復帰後に「鉱業法」の改正措置を講じ、せん閣石油資源の地元沖縄からの国家権力による合法的収奪を公言するようになったのは前述のとおりである。
三月二十二日付の沖繩タイムスは本土側のその発想の背景を次のようにあげている。「日本国内に殆んど油田らしい油田をもたず経済的き弱性を痛感している本土政府は、かなりの高姿勢で〝せん閣石油資源をまとめて採掘したい意向を明らかにしており、石油行政の立場から最悪の場合は沖縄側の受理権を無効にすることもあり得る…」と。しかしながら、それが如何に変則的な根拠であるかを、次章で述べてみる。近年、北海道から韓国沖を経て九州に到る日本近海の水深二〇〇メートル以浅の大陸棚に目白押しに石油鉱業権が申請されているが、それらの鉱区の価値はせん閣油田に比較すると微々たるものといわれている。
確かに九九%海外原油依存の日本の石油業界にとって同油田にかける期待とその執念は想像を絶する程大きく深いものであろう。それ故にこそ私は、外資のあまたの誘いを断わり、日本の石油政策に則って、本土企業との石油利権協定による開発契約を結ぶべく今日まで努力してきたのであるが、開発への具体化の一歩手前で、通産省の非公式な意向が業界を左右し、その実現を見ず今日に至っているのが真相である。
十、繰り返される第三の琉球処分
前述のようにせん閣油田の場合は、とりまとめて開発したい云々との理由で、同油田に対し開発意欲を示している本土石油民間企業と私との契約を通産省が阻んでいるのは全く納得のいかぬことである。然も本土政府は、せん閣以外の他の地域では、私が申請した鉱区面積(約三万四〇〇〇平方メートル)以下に細分して開発を許しているのに、ひとり沖縄のせん閣油田に於いては何故に、強硬な法制措置を講じることを意図するのであろうか。
例えば三びしとシェル社の折半出資による西日本石油開発社の申請鉱区面積(六万一〇〇〇平方メートル)を除き他社のそれは、ほとんど私の申請面積以下である。日本石油開発社―二万九〇〇〇平方メートル、出光興産―二万三〇〇〇平方メートル、そこで本土政府のこのような偽まん性をあばくため私の申請鉱区の吸収先に予定されている石油公団なるものの性格にふれてみよう。
(つづく)