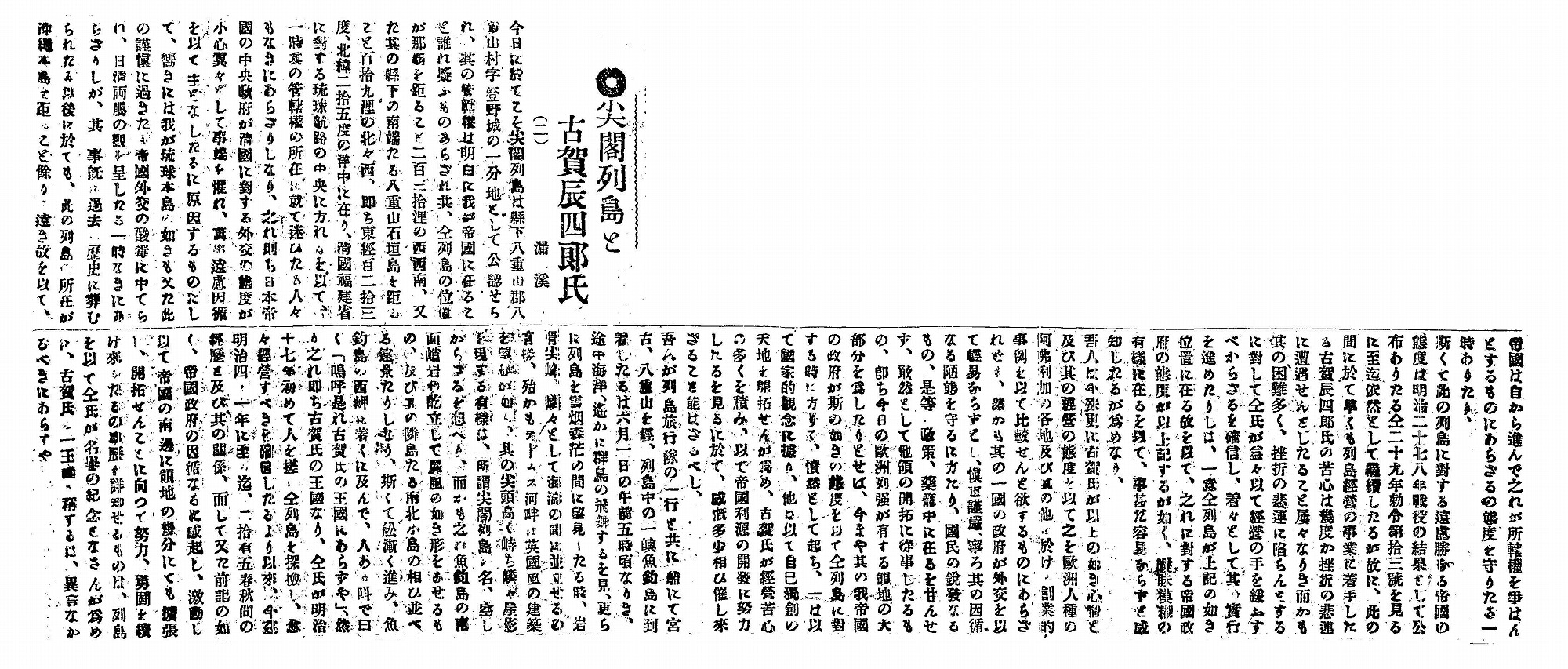キーワード検索
尖閣列島と古賀辰四郞氏(二)
原文表記
尖閣列島と古賀辰四郞氏(二)
琉球新報 明治四十一年六月十六日 漏 渓
今日に於てこそ尖閣列島は縣下八重山郡八重山村字登野城の一分地として公認せられ、其の管轄權は明白に我が帝國に在ること誰れ疑ふものあらざれ共、仝列島の位置が那覇を距ること二百三拾浬の西南西、又た其の縣下の南端たる八重山石垣島を距ること百拾九浬の北々西、即ち東經百二拾三度、北緯二拾五度の洋中に在り、淸國福建省に對する琉球航路の中央に方れるを以て、一時其の管轄權の所在に就て迷ひたる人々もなきにあらさりしなり、之れ則ち日本帝國の中央政府が淸國に對する外交の態度が小心翼々として事端を懼れ、万事遠慮因循を以て主となしたるに原因するものにして、嚮きには我が琉球本島の如きも又た此の謹慎に過きたる帝國外交の酸毒に中てられ、日淸両属の觀を呈したる一時なきにあらざりしが、其■事既■過去■歴史に葬むられたる以後に於ても、此の列島の所在が沖繩本島を距ること餘り■遠き故を以て、■■は自から進んで之れが所轄權を爭はんとするものにあらざるの態度を守りたる一時ありた■
斯くて此の列島に對する遠慮勝なる帝國の態度は明治二十七八年戦役の結果として公布ありたる仝二十九年勅令第拾三號を見るに至迄依然として繼續したるが故に、此の間に於て早くも列島經營の事業に着手したる古賀辰四郞氏の苦心は幾度か挫折の悲運に遭遇せんとしたること屢々なりき而かも其の困難多く、挫折の悲運に陥らんとするに對して仝氏が益々以て經營の手を緩ふすべからざるを確信し、着々として其の實行を進めたりしは、一■仝列島が上記の如き位置に在る故を以て、之れに對する帝國政府の態度が以上記するが如く、曖昧模糊の有様に在るを以て、事甚だ容易ならずと感知したるが爲めなり、
吾人は今殊更に古賀氏が以上の如き心情と及び其の經營の態度を以て之を歐洲人種の阿弗利加の各地及び其の他に於ける創業的事例を以て比較せんと欲するものにあらざれども、然かも其の一國の政府が外交を以て軽易ならずとし、慎重謹厳、寧ろ其の因循なる陋態を守るに方たり、國民の鋭發なるもの、是等■政策、藥龍中に在るを甘んせず、敢然として他領の開拓に従事したるもの、即ち今日の歐洲列強が有する領地の大部分を爲したりとせは、今まや其の我帝國の政府が斯の如きの態度を以て仝列島に對する時に方りて、憤然として起ち、一は以て國家的觀念に據り、他は以て自己獨創の天地を開拓せんが爲め、古賀氏が經營苦心の多くを積み、以て帝國利源の開發に努力したるを見るに於て、感慨多少相ひ催し來ざること能はざるべし、
吾人が列島旅行隊の一行と共に船にて宮古、八重山を經、列島中の一嶼魚釣島に到着したるは六月一日の午前五時頃なりき、途中海洋、遙かに群鳥の飛舞するを見、更らに列島を雲烟森茫の間に望見したる時、岩骨尖峰、嶙々として海濤の間に並立せるの有様、殆かもテームス河畔に英國風の建築を望むが如く、其の尖頭高く峙ち嶙々屋影を現する有様は、所謂尖閣列島の名、空しからざるを想へり、而かも之れ魚釣島の南面峭岩の屹立して屏風の如き形をなせるもの、及び其の隣島たる南北小島の相ひ並べる遠景たりしなり、斯くて舩漸く進み、魚釣島の西岬に着くに及んで、人あり叫で曰く「鳴呼是れ古賀氏の王國にあらずや」、然り之れ即ち古賀氏の王國なり、仝氏が明治十七年初めて人を搓し仝列島を探檢し、愈々經營すべきを確信したるより以來、今茲明治四十一年に至る迄、二拾有五春秋間の經歴と及び其の關係、而して又た前記の如く、帝國政府の因循なるに成起し、激動■以て帝國の南邊に領地の幾分にても壙張し、開拓せんことに向つて勞力、勇鬪を續け來りたるの事歴を詳知せるものは、列島を以て仝氏が名誉の紀念となさんが爲めに、古賀氏の一王國と稱するは、異言なかるべきにあらすや
現代仮名遣い表記
尖閣列島と古賀辰四郞氏(二)
琉球新報 明治四十一年六月十六日 漏 渓
今日に於てこそ尖閣列島は県下八重山郡八重山村字登野城の一分地として公認せられ、其の管轄権は明白に我が帝国に在ること誰れ疑うものあらざれ共、同列島の位置が那覇を距ること二百三十浬の西南西、又た其の県下の南端たる八重山石垣島を距ること百十九浬の北々西、即ち東経百二十三度、北緯二十五度の洋中に在り、清国福建省に対する琉球航路の中央に方れるを以て、一時其の管轄権の所在に就て迷いたる人々もなきにあらざりしなり。之れ則ち日本帝国の中央政府が清国に対する外交の態度が小心翼々として事端を恐れ、万事遠慮因循を以て主となしたるに原因するものにして、嚮きには我が琉球本島の如きも又た此の謹慎に過ぎたる帝国外交の酸毒に中てられ、日清両属の観を呈したる一時なきにあらざりしが、其■事既■過去■歴史に葬むられたる以後に於ても、此の列島の所在が沖縄本島を距ること余り■遠き故を以て、帝国は自から進んで之れが所轄権を争わんとするものにあらざるの態度を守りたる一時ありた■。
斯くて此の列島に対する遠慮勝なる帝国の態度は、明治二十七、八年戦役の結果として公布ありたる同二十九年勅令第十三号を見るに至迄依然として継続したるが故に、此の間に於て早くも列島経営の事業に着手したる古賀辰四郞氏の苦心は、幾度か挫折の悲運に遭遇せんとしたること屢々なりき。而かも其の困難多く、挫折の悲運に陥らんとするに対して同氏が益々以て経営の手を緩うすべからざるを確信し、着々として其の実行を進めたりしは、一■同列島が上記の如き位置に在る故を以て、之れに対する帝国政府の態度が以上記するが如く、曖昧模糊の有様に在るを以て、事甚だ容易ならずと感知したるが為めなり。
吾人は今殊更に古賀氏が以上の如き心情と及び其の経営の態度を以て、之を欧洲人種の阿弗利加の各地及び其の他に於ける創業的事例を以て比較せんと欲するものにあらざれども、然かも其の一国の政府が外交を以て軽易ならずとし、慎重謹厳、寧ろ其の因循なる陋態を守るに方たり、国民の鋭発なるもの、是等の政策、薬龍中に在るを甘んぜず、敢然として他領の開拓に従事したるもの、即ち今日の欧洲列強が有する領地の大部分を為したりとせば、今まや其の我帝国の政府が斯の如きの態度を以て同列島に対する時に当りて、憤然として起ち、一は以て国家的観念に拠り、他は以て自己独創の天地を開拓せんが為め、古賀氏が経営苦心の多くを積み、以て帝国利源の開発に努力したるを見るに於て、感慨多少相い催し来ざること能わざるべし。
吾人が列島旅行隊の一行と共に船にて宮古、八重山を経、列島中の一嶼魚釣島に到着したるは六月一日の午前五時頃なりき。途中海洋遙かに群鳥の飛舞するを見、更らに列島を雲煙森茫の間に望見したる時、岩骨尖峰、嶙々として海濤の間に並立せるの有様、殆かもテームス河畔に英国風の建築を望むが如く、其の尖頭高く峙ち、嶙々屋影を現する有様は、所謂尖閣列島の名空しからざるを想えり。而かも之は魚釣島の南面峭岩の屹立して屏風の如き形をなせるもの、及び其の隣島たる南北小島の相い並べる遠景たりしなり。斯くて船漸く進み、魚釣島の西岬に着くに及んで、人あり、叫で曰く「鳴呼是れ古賀氏の王国にあらずや」。然り之れ即ち古賀氏の王国なり。同氏が明治十七年初めて人を搓し同列島を探検し、愈々経営すべきを確信したるより以来、今茲明治四十一年に至る迄、二十有五春秋間の経歴と及び其の関係、而して又た前記の如く、帝国政府の因循なるに成起し、激動■以て帝国の南辺に領地の幾分にても拡張し、開拓せんことに向って努力、勇闘を続け来りたるの事歴を詳知せるものは、列島を以て同氏が名誉の紀念となさんが為めに、古賀氏の一王国と称するは、異言なかるべきにあらずや。