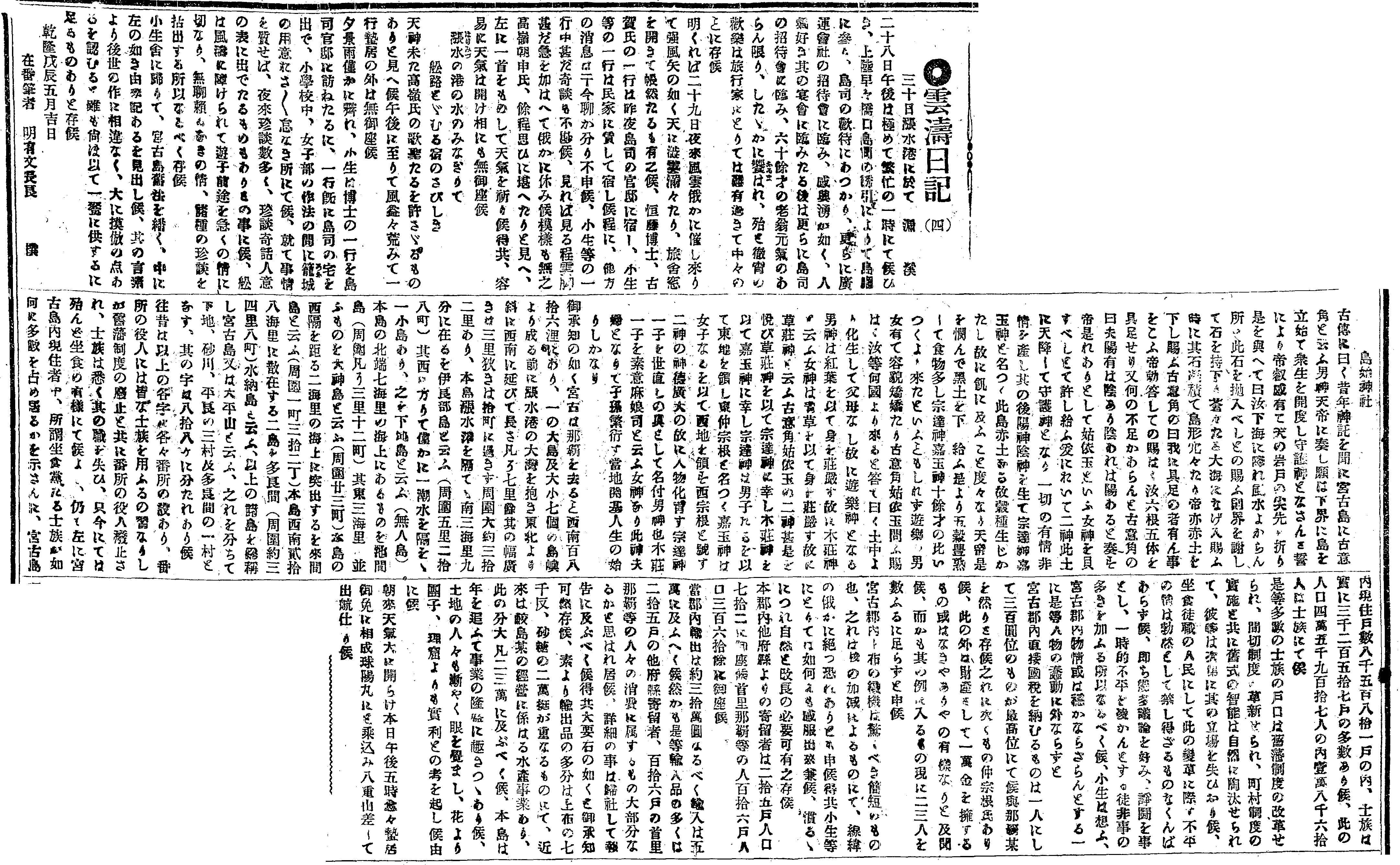キーワード検索
◎雲濤日記(四)三十日漲水港に於て 漏溪
原文表記
◎雲濤日記(四)
三十日漲水港に於て 漏渓
二十八日午後は極めて繁忙の一時にて候ひき、上陸早々橋口島司の誘引によりて島廳に參り、島司の觀待にあつかり、更らに廣運會社の招待會に臨み、感興湧が如く、人氣好き其の宴會に臨みたる後は更に島司の招待會に臨み、六十餘才の老翁元氣のあらん限り、したたかに饗はれ、殆ど徹宵の觀樂は旅行家にとりては難有過ぎて中々のことに存候
明くれば二十九日夜來風雲俄かに催し來りて强風矢の如く天に澁雲滿々たり、旅舎窓を開きて帳然たるも有之候、恒藤博士、古賀氏の一行は昨夜島司の官邸に宿し、小生等の一行は民家に賃して宿し候程に、他方の消息は于今聊か分り不申候、小生等の一行中甚だ奇談も不尠候、見れば見る程雲脚甚だ急を加はへて俄かに休み候模樣も無之、高嶺朝申氏、餘程思ひに堪へたりと見へ、左に一首をものして天氣を祈り候得共、容易に天氣は開け相にも無御座候
漲水の港の水のみなぎりて
舩路とどむる宿のさびしき
天神未だ高嶺氏の歌聖たるを許さゞるものありと見へ候午後に至りて風益々荒みて一行蟄居の外は無御座候
夕景雨僅かに霽れ、小生は博士の一行を島司官邸に訪ねたるに、一行既に島司の宅を出で、小學校中、女子部の作法の間に籠城の用意■ささ怠なき所にて候、就て事情を質せば、夜來珍談數多く、珍談奇話人意の表に出でたるものもありとの事に候、舩は風■に障けられて遊子前途を急くの情に切なり、無聊賴みなきの情、諸種の珍談を拈出する所以なるべく存候
小生舎に歸りて、宮古島舊法を繙く、中に左の如き由■記あるを見出し候、其の言葉より後世の作に相違なく、大に模倣の点あるを認むる■雖も尚ほ以て一餐に供するに足るものありと存候
乾隆戉辰五月吉日
在番筆者 明有文長良 撰
島始神社
古傳に曰く昔年神託を聞に宮古島に古意角と云ふ男神天帝に泰し願は下界に島を立始て衆生を開度し守護神となさんと誓により帝叡感有て天の岩戸の尖先■折り是を與へて日汝下海に降れ風水よからん所■此石を抛入べしとの賜ふ■界を謝して石を持下り蒼々たる大海になげ入賜ふ時に其石■積て島形■々たり帝亦赤土を下し賜ふ古意角の日我に具足の者有ん事をこふ帝勅答しての賜はく汝六根五体を具足せり又何の不足かあらんと古意角の日夫陽有は陰あり陰あれは陽のあると泰す帝是れありとして姑依玉といふ女神を貝すべしとて許し給ふ爰にれいて二神此土に天降して守護神となり一切の有情非情を產し其の後陽神陰神を生て宗達■嘉玉神と名つく此島赤土■る故榖種生じかたし故に飢に及ふこと度々なり天帝是を憫んで黒土を下■給ふ是より五榖豊熟して食物多し宗達神嘉玉神十餘才の比いつくよ■來たといふこともしれず遊樂■男女有て容貎矯嬌たり古意角姑依玉問ふ賜はく汝等何國より來ると答て曰く土中よ■化生して父母なし故に遊樂神となる男神は紅葉を以て身を荘嚴ず故に木荘神■云ふ女神は青草を以て身を荘嚴す故に草荘神と云ふ古意角姑依玉の二神甚是を悦び草荘神を以て宗達神に幸し木荘神を以て嘉玉神に幸し宗達神は男子たるを以て東地を領し東仲宗根と名つく嘉玉神は女子なるを以て西地を領す西宗根と號す二神の神徳廣大の故に人物化有す宗達神一子を世直しの眞として名付男神也木莊一子を素意麻娘司と云ふ女神なり此神夫婦となりて子孫繁行す當地開基人生の始りしかなり
御承知の如く宮古は那覇を去ること西南百八拾六浬にあり、一の大島及大小七個の島嶼より成る前に漲水港の大灣を抱き東北より斜に西南に延びて長さ凡ろ七里餘其の幅廣きは三里狭きは拾町に過ぎず周圍大約三拾二里あり、本島漲水港を隔てゝ南三海里九分に在ること伊良部島と云ふ(周圍五里二拾八町)其西に方りて僅かに一潮水を隔をゝ一小島あり、之を下地島と云ふ(無人島)本島の北端七海里の海上にあるものを池間島(周圍凡り三里十二町)其東三海里■並ふものを大神島と云ふ(周圍廿三町)本島の西隔を距る二海里の海上に突出するを來来間島と云ふ(周圍一町三拾二丁)本島西南貳拾八海里に散在する二島を多良間(周圍約三四里八町)水納島と云ふ、以上の諸島を總稱し宮古島又は大平山と云ふ、之れを分ちて下地、砂川、平良の三村及多良間の一村となす、其の字は八拾八ヶに分たれあり候
往昔は以上の各字■各々番所の設あり、番所の役人には皆な士族を用ふるの習なりしが舊藩制度の廢止と共に番所の役人廢止され、士族は悉く其の職を失ひ、只今にては殆ど坐食の有樣にて候よ■、仍も左に宮古島内現住者中、所謂坐食黨たる士族が如何に多數を占め居るかを示さんに、宮古島内現住戸數八千五百八拾一戸の内、士族は実に三千二百五拾七戸の多數あり候、此の人口四萬五千九百拾七人の内壹萬八千六拾人は士族にて候
是等多數の士族の戸口は舊藩制度の改革せられ、間切制度■革新せられ、町村制度の實施と共に舊式の智能は自然に淘汰せられて、彼等は次第に其の立塲を失ひなり候、坐食徒職の人民にして此の變革に際す不平の情は勃然として禁し得ざるものなくんばあらず候、即ち幾多議論を好み、諍闘を事とし、一時的不平を凌かんとす■徒非事の多きを加ふる所以なるべく候、小生は想ふ、宮古郡内物情或は穏かならざらんとする一に是等人物の蠢動に外ならずと
宮古郡内直接國稅を納むるものは一人にして三百圓位のものが最高位にて候與那覇某を然りを存候之れに次くもの仲宗根氏あり候、此の外は財産をして一萬金を擁するもの或はなきやありやの有樣なりと及聞候、而かも其の例に入るもの現に二三人を數ふるに足らずと申候
宮古郡内と布織機は驚きくべき簡短のもの也、之れは梭の加減によるものにて、線緯の俄かに絶つ恐れありとも申候得共小生等にとりては如何■も感服出來兼候、慣るるにつれ自然と改良の必要可有之存候
本郡内他府縣よりの寄留者は二拾五戸人口七拾二に御座候首里那覇等の人百拾六戸人口三百六拾餘に御座候
當郡内輸出は約三拾萬圓なるべく輸入は五萬に及ふへく候然かも是等輸入品の多くは二拾五戸の他府縣寄留者、百拾六戸の首里那覇等の人々の消費に属するもの大部分なるかと思はれ居候、詳細の事は歸社して報告に及ぶべく候得共大要石の如くと御承知可然存候、素より輸出品の多分は上布の七千反、砂糖の二萬挺が重なるものにて、近來は鮫島某經營に係はる水產事業あり、此の分大凡二三萬に及ぶべく候、本島は年を追ふて事業の隆盛に趣きつつあり候、土地の人々も漸やく眼を覺まし、花より團子、理屈よりも實利との考えを起し候由に候
朝來天氣大に開らけ本日午後五時愈々蟄■御免に相成球陽丸にと乗込み八重山差して出航仕り候
現代仮名遣い表記
◎雲涛日記(四)
三十日漲水港に於て 漏渓
二十八日午後は極めて繁忙の一時にて候ひき、上陸早々橋口島司の誘引によりて島庁に参り、島司の歓待にあづかり、更らに広運会社の招待会に臨み、感興湧が如く人気好き其の宴会に臨みたる後は、更に島司の招待会に臨み、六十余才の老翁元気のあらん限り、したたかに饗われ、殆ど徹宵の歓楽は旅行家にとりては難有過ぎて中々のことに存じます。
明くれば二十日夜来風雲俄かに催し来りて、強風矢の如く天に渋雲満々たり、旅舎窓を開きて帳然たるも有之候。恒藤博士、古賀氏の一行は昨夜島司の官邸に宿し、小生等の一行は民家に賃して宿し候程に、他方の消息は于今聊か分り不申候。小生等の一行中、甚だ奇談も不尠候、見れば見る程雲脚甚だ急を加えて俄かに休み候模様も無之、高嶺朝申氏余程思ひに堪えたりと見え、左に一首をものして天気を祈りますが、容易に天気は開け相にもございません
漲水の港の水のみなぎりて
船路とどむる宿のさびしき
天神未だ高嶺氏の歌聖たるを許さゞるものありと見へます、午後に至りて風益々荒みて、一行蟄居の外はございません。
夕景雨僅かに霽れ、小生は博士の一行を島司官邸に訪ねたるに、一行既に島司の宅を出で、小学校中、女子部の作法の間に籠城の用意■ささ怠なき所にてます。就て事情を質せば、夜来珍談数多く、珍談奇話人意の表に出でたるものもありとの事です。船は風■に障けられて遊子前途を急ぐの情に切なり、無聊頼みなきの情、諸種の珍談を拈出する所以なるべき存です。
小生舎に帰りて宮古島旧法を繙く、中に左の如き由■記あるを見出します。その言葉より後世の作に相違なく、大に模倣の点あるを認むる■雖も、尚お以て一餐に供するに足るものありと存じます。
乾隆戉辰五月吉日
在番筆者 明有文長良 撰
島始神社
古伝に曰く、昔年神託を聞に宮古島に古意角と云う男神天帝に奏し、願は下界に島を立始め衆生を開度し守護神となさんと誓により、帝叡感有て天の岩戸の尖先■折り是を与えて曰、汝下海に降れ風水よからん所■此石を抛入べしとの賜う。■界を謝して石を持下り蒼々たる大海に投げ入賜う時に、其石■積て島形■々たり帝亦赤土を下し賜う。古意角の曰、我に具足の者有ん事をこう。帝勅答しての賜わく汝六根五体を具足せり又何の不足かあらんと。古意角の曰、夫陽有は陰あり陰あれば陽のあると奏す、帝是れありとして姑依玉という女神を貝すべしとて許し給ふ。爰において二神此土に天降して守護神となり一切の有情非情を産し、其の後、陽神陰神を生て宗達■嘉玉神と名つく。此島赤土■る故殻種生じがたし故に飢に及ぶこと度々なり、天帝是を憫んで黒土を下■給ふ、是より五穀豊熟して食物多し。宗達神嘉玉神十餘才の比、いづくよ■来たということもしれず遊楽の男女有て容貎矯嬌たり。古意角姑依玉問い賜わく汝等何國より来ると、答て曰く、土中よ■化生して父母なし故に遊楽神となる男神は紅葉を以て身を荘厳す故に木荘神■云う、女神は青草を以て身を荘厳す故に草荘神と云う。古意角姑依玉の二神甚是を悦び、草荘神を以て宗達神に幸し、木荘神を以て嘉玉神に幸し、宗達神は男子たるを以て東地を領し東仲宗根と名づく、嘉玉神は女子なるを以て西地を領す西宗根と号す。二神の神徳大の故に、人物化有す宗達神一子を世直しの真として名付、男神也木荘一子を素意麻娘司と云う女神なり此神夫婦となりて子孫繁行す、当地開基人生の始りしかなり。
御承知の如く宮古は那覇を去ること西南百八十六浬にあり、一の大島及大小七個の島嶼より成る。前に漲水港の大湾を抱き東北より斜に西南に延びて長さ凡ろ七里余、其の幅広きは三里、狭きは十町に過ぎず。周囲大約三十二里あり、本島漲水港を隔てて南三海里九分に在ること伊良部島と云う(周囲五里二拾八町)其西に方りて僅かに一潮水を隔をゝ一小島あり之を下地島と云う(無人島)、本島の北端七海里の海上にあるものを池間島(周囲凡り三里十二町)、其東三海里■並ぶもの大神島と云う(周囲二三町)、本島の西隔を距る二海里の海上に突出するを来間島と云う(周囲一町三十二丁)、本島西南二十八海里に散在する二島を多良間(周囲約三四里八町)水納島と云う、以上の諸島を総称し宮古島又は大平山と云う。之れを分ちて下地、砂川、平良の三村及多良間の一村となす、其の字は八拾八ヶに分たれあり候。
往昔は以上の各字■各々番所の設あり。番所の役人には皆な士族を用ふるの習なりしが、旧藩制度の廃止と共に番所の役人廃止され、士族は悉く其の職を失ひ、只今にては殆ど坐食の有様にて候よ■。仍も左に宮古島内現住者中、所謂坐食党たる士族が如何に多数を占め居るかを示さんに、宮古島内現住戸数八千五百八十一戸の内、士族は実に三千二百五十七戸の多数あります。此の人口四万五千九百十七人の内、一万八千六十人は士族です。
是等多数の士族の戸口は旧藩制度の改革せられ、間切制度■革新せられ、町村制度の実施と共に旧式の智能は自然に淘汰せられて、彼等は次第に其の立場を失ひなります。坐食徒職の人民にして此の変革に際す不平の情は勃然として禁じ得ざるものなくんばあらずです。即ち幾多議論を好み、諍闘を事とし、一時的不平を凌かんとす■徒非事の多きを加ふる所以なるべく候。小生は想う、宮古郡内物情或は穏かならざらんとする一に是等人物の蠢動に外ならずと。
宮古郡内直接国税を納むるものは、一人にして三百円位のものが最高位です、與那覇某を然りと存候之れに欠くもの仲宗根氏あります。此の外は財産をして一萬金を擁するもの或はなきやありやの有様なりと及聞きます。而かも其の例に入るもの、現に二三人を数えるに足らずと申候。
宮古郡内上布織機は驚くべき簡短のもの也、之れは■の加減によるものにて、線緯の俄かに絶つ恐れありとも申候得共。小生等にとりては如何■も感服出来兼候、慣れるにつれ自然と改良の必要可有之存候。
本郡内他府県よりの寄留者は二十五戸人口七十二に御座候。首里那覇等の人百十六戸、人口三百六十余に御座候。
当郡内輸出は約三十万円なるべく、輸入は五万及ぶべく候。然かも是等輸入品の多くは、二十五戸の他府県寄留者、百十六戸の首里那覇等の人々の消費に属するもの大部分なるかと思われ居候。詳細の事は帰社して報告に及ぶべく候得共、大要石の如くと御承知可然在候。素より輸出品の多分は上布の七千反、砂糖の二万挺が重なるものにて、近来は鮫島某経営に係わる水産事業あり、此の分大凡二三万に及ぶべく候。本島は年を追うて事業の隆盛に趣きつつあり候、土地の人々も漸やく眼を覚まし、花より団子、理屈よりも実利との考えを起し候由に候。
朝来天気大に開らけ、本日午後五時愈々蟄居御免に相成、球陽丸にと乗込み八重山差して出港仕り候。