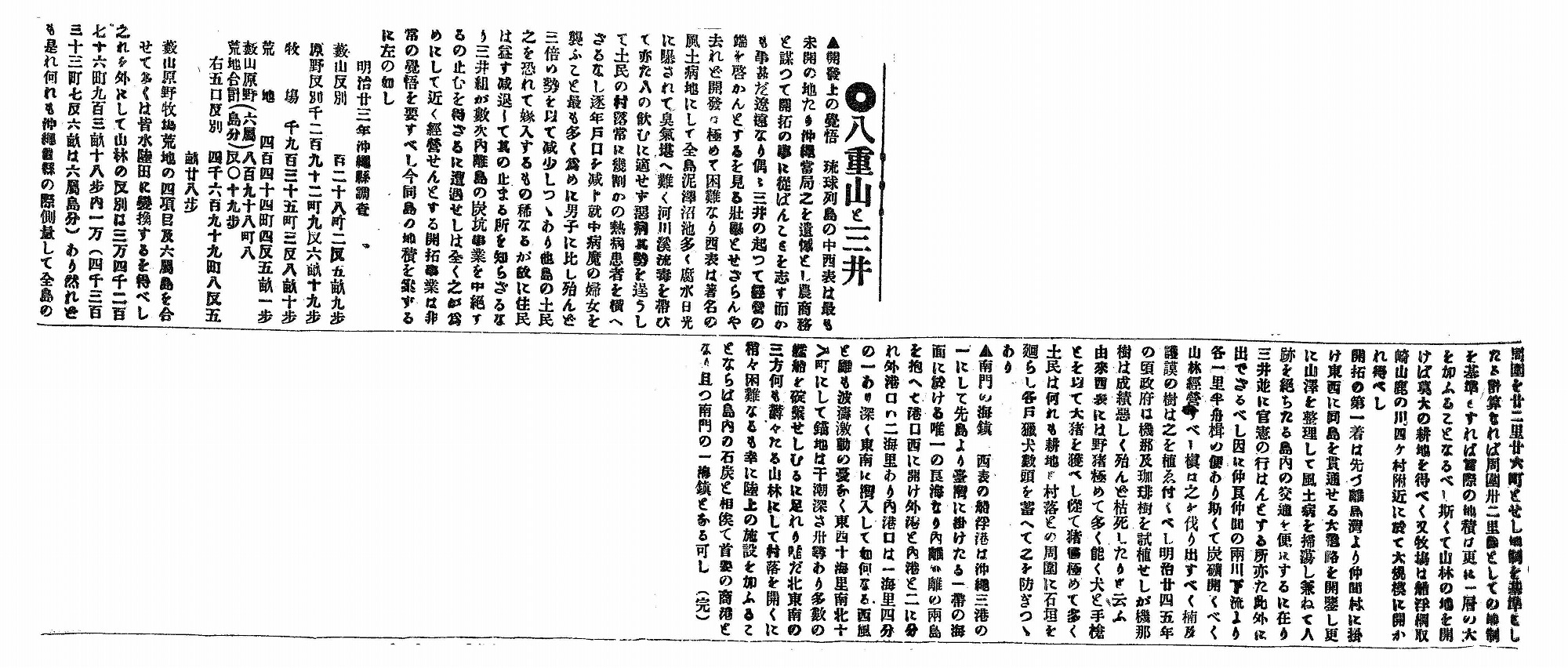キーワード検索
八重山と三井(下)
原文表記
八重山と三井(下)
琉球新報 明治四十一年二月二十三日
▲開發上の覺悟 琉球列島の中西表は最も未開の地たり沖繩當局之を遺憾とし農商務と謀つて開拓の事に從はんことを志す而かも事甚だ遼遠なり偶々三井の起つて經營の端を啓かんとするを見る壯擧とせざらんや去れど開發は極めて困難なり西表は著名の風土病地にして全島泥澤沼池多く腐水日光に曝されて臭氣堪へ難く河川渓流毒を帶びて亦た人の飮むに適せず惡病其勢を逞うして土民の村落常に幾割かの熱病患者を横へざるなし逐年戸口を減じ就中病魔の婦女を襲ふこと最も多く爲めに男子に比し殆んど三倍の勢を以て減少しつゝあり他島の土民之を恐れて嫁入するもの稀なるが故に住民は益す減退して其の止まる所を知らざるなり三井組が數次内離島の炭坑事業を中絶するの止むを得ざるに遭遇せしは全く之が爲めにして近く經營せんとする開拓事業は非常の覺悟を要すべし今同島の地積を案ずるに左の如し
明治廿三年沖繩県縣調査
藪山反別 百二十八町二反五畝九歩
原野反別 千二百九十二町九反六畝十九歩
牧 場 千九百三十五町三反八畝十歩
荒 地 四百四十四町四反五畝一歩
藪山原野荒地合計(六属島分) 八百九十八町八反〇十九歩
右五口反別 四千六百九十九町八反五畝廿八歩
藪山原野牧場荒地の四項目及六属島を合せて多くは皆水陸田に變換す
るを得べし
之れを外にして山林の反別は三万四千二百七十六町九百三畝十八歩内一万(四千三百三十三町七反六畝は六属島分)あり然れども是れ何れも沖繩置縣の際測量して全島の周圍を廿二里廿六町とせし地制を基準としたる計算なれば周圍卅二里餘としての地制を基準とすれば實際の地積は更に一層の大を加ふることなるべし斯くて山林の地を開けば莫大の耕地を得べく又牧場は船浮網取崎山鹿の川四ヶ村附近に於て大規模に開かれ得べし
開拓の第一着は先づ離島灣より仲間村に掛け東西に同島を貫通せる大道路を開鑿し更に山澤を整理して風土病を掃蕩し兼ねて人跡を絶ちたる島内の交通を便にするに在り三井並に官憲の行はんとする所亦た此外に出でざるべし因に仲良仲間の兩川下流より各一里半舟楫の便あり斯くて炭礦開くべく山林經營すべし槇は之を伐り出すべく楠及護謨の樹は之を植ゑ付くべし明治廿四五年の頃政府は機那及珈琲樹を試植せしが機那樹は成績惡しく殆んど枯死したりと云ふ
由來西表には野猪極めて多く能く犬と手槍とを以て大猪を獲べし從て猪害極めて多く土民は何れも耕地■村落との周圍に石垣を廻らし各戸猟犬數頭を蓄へて之を防ぎつゝあり
▲南門の海鎭 西表の船浮港は沖繩三港の一にして先島より臺灣に掛けたる一帶の海面に於ける唯一の良海なり内離外離の兩島を抱へて港口西に開け外港と内港と二に分れ外港口ハ二海里あり内港口は一海里四分の一あり深く東南に灣入して如何なる西風と雖も波濤激動の憂なく東西十海里南北十八町にして錨地は干潮深さ卅尋あり多數の艦船を碇繫せしむるに足れり唯だ北東南の三方何も欝々たる山林にして村落を開くに稍々困難なるも幸に陸上の施設を加ふることならば島内の石炭と相俟て首要の商港となり且つ南門の一海鎭となる可し
(完)
現代仮名遣い表記
八重山と三井(下)
琉球新報 明治四十一年二月二十三日
▲開発上の覚悟 琉球列島の中西表は最も未開の地たり。沖縄当局之を遺憾とし、農商務と謀って開拓の事に従わんことを志す。而かも事甚だ遼遠なり。偶々三井の起って経営の端を啓かんとするを見る。壮挙とせざらんや。去れど開発は極めて困難なり。西表は著名の風土病地にして全島泥沢沼池多く、腐水日光に曝されて臭気堪え難く、河川渓流毒を帯びて亦た人の飲むに適せず。悪病其勢を逞うして土民の村落常に幾割かの熱病患者を横えざるなし。逐年戸口を減じ、就中病魔の婦女を襲うこと最も多く、為めに男子に比し殆んど三倍の勢を以て減少しつゝあり。他島の土民之を恐れて嫁入するもの稀なるが故に、住民は益す減退して其の止まる所を知らざるなり。三井組が数次内離島の炭坑事業を中絶するの止むを得ざるに遭遇せしは全く之が為めにして、近く経営せんとする開拓事業は非常の覚悟を要すべし。今同島の地積を案ずるに左の如し。
明治二十三年沖縄県調査
藪山反別 百二十八町二反五畝九歩
原野反別 千二百九十二町九反六畝十九歩
牧 場 千九百三十五町三反八畝十歩
荒 地 四百四十四町四反五畝一歩
藪山原野荒地合計(六属島分) 八百九十八町八反〇十九歩
右五口反別 四千六百九十九町八反五畝二十八歩
藪山原野牧場荒地の四項目及六属島を合せて多くは皆水陸田に変換す
るを得べし。
之れを外にして、山林の反別は三万四千二百七十六町九百三畝十八歩(内一万四千三百三十三町七反六畝は六属島分)あり。然れども是れ何れも沖縄置県の際測量して全島の周囲を二十二里二十六町とせし地調を基準としたる計算なれば、周囲三十二里余としての地制を基準とすれば実際の地積は更に一層の大を加うることなるべし。斯くて山林の地を開けば莫大の耕地を得べく、又牧場は船浮、網取、崎山、鹿の川四ヶ村附近に於て大規模に開かれ得べし。
開拓の第一着は、先づ離島湾より仲間村に掛け、東西に同島を貫通せる大道路を開鑿し、更に山沢を整理して風土病を掃蕩し、兼ねて人跡を絶ちたる島内の交通を便にするに在り。三井並に官憲の行わんとする所亦た此外に出でざるべし。因に仲良、仲間の両川下流より各一里半舟楫の便あり。斯くて炭鉱開くべく山林経営すべし。槇は之を伐り出すべく、楠及護謨の樹は之を植え付くべし。明治二十四、五年の頃政府は機那及珈琲樹を試植せしが、幾那樹は成績悪しく殆んど枯死したりと言う。
由来西表には野猪極めて多く、能く犬と手槍とを以て大猪を獲べし。従て猪害極めて多く、土民は何れも耕地■村落との周囲に石垣を廻らし、各戸猟犬数頭を蓄えて之を防ぎつゝあり。
▲南門の海鎮 西表の船浮港は沖縄三港の一にして、先島より台湾に掛けたる一帯の海面に於ける唯一の良海なり。内離外離の両島を抱えて港口西に開け、外港と内港と二に分れ、外港口は二海里あり。内港口は一海里四分の一あり。深く東南に湾入して、如何なる西風と雖も波濤激動の憂なく、東西十海里南北十八町にして錨地は干潮深さ三十尋あり。多数の艦船を碇繫せしむるに足れり。唯だ北東南の三方何も鬱々たる山林にして村落を開くに稍々困難なるも、幸に陸上の施設を加うることならば、島内の石炭と相俟て首要の南港となり、且つ南門の一海鎮となる可し。
(完)