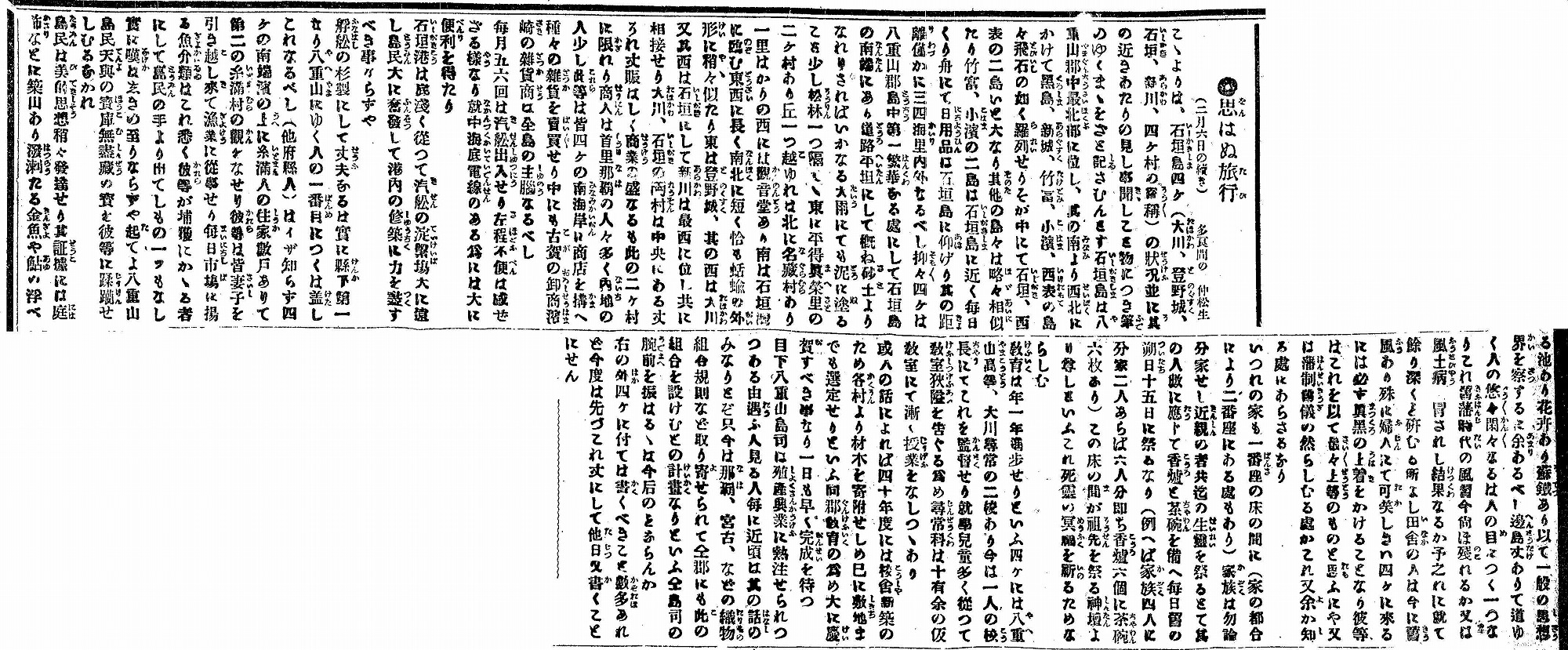キーワード検索
◎思はぬ旅行 (二月六日の續き)多良間の仲松生
原文表記
◎思はぬ旅行
(二月六日の續き) 多良間の 仲松生
こゝよりは、石垣島四ケ(大川、登野城、石垣、新川、四ケ村の總稱)の狀况並に其の近きあたりの見し事聞しことを物につき筆のゆくままをざと記さむんとす石垣島は八重山郡中最北部に位置し、其の南より西北にかけて黒島、新城、竹富、小濱、西表の島々飛石の如く羅列せりそが中にて石垣、西表の二島いと大なり其他の島々は略々相似たり竹富、小濱の二島は石垣島に近く毎日くり舟にて日用品は石垣島に仰げり其の距離僅かに三四海里内外なるべし仰々四ヶは八重山郡島中第一繁華なる處にして石垣島の南端にあり道路平坦にして槪ね砂土よりなれりさればいかなる大雨にても泥に塗ること少し松林一つ隔てゝ東に平得真栄里の二ヶ村あり丘一る越ゆれは北に名藏村あり一里はかりの西には觀音堂あり南は石垣灣に臨む東西に長く南北に短く恰も蛞蝓の外形に稍々似たり東は登野城、其の西は大川又其西は石垣にして新川は最西に位し共に相接せり大川、石垣の両村は中央にある丈ろれ丈賑はしく商業の盛なる此の二ヶ村は限れり商人は首里那覇の人々多く内地の人少し此等は皆四ヶの南海岸に商店を搆へ種々の雜貨を賣買せり中にも古賀の卸商濱崎の雜貨商は全島の主腦なるべし
毎月五六回は汽船出入せり左程不便は感ぜざる樣なり就中海底電線のある爲には大に便利を得たり石垣港は底淺く從つて気舩の淀繁塲大に遠くし島民大に奮發して港内の修築に力を盡すべき事ならずや
船舩の杉製にして丈夫なるは実に縣下第一なり八重山にゆく人の一番目につくは盖しこれなるべし(他府縣人)はイザ知らず四ヶの南端濱の上に糸滿人の住家數戶ありて第二の糸滿村の觀をなせり彼等は皆妻子を引き越し來て漁業に從事せり毎日市塲に揚る魚介類はこれ悉く彼等が捕獲にかゝる者にして島民の手より出てしもの一ッもなし實に嘆ぬ志きめ至りならずや起てよ八重山島民天與の寳庫無盡藏の寶を彼等に蹂躙せしむるなかれ
島民は美的思想梢々發達せり其証拠には庭飾なとに築山あり發溂たる金魚や鮎の浮べる池あり花卉あり蘇鐵あり以て一般の思想界を察するに余りあるべし辺島丈ありて道ゆく人の悠々閑々なるは人の目につく一つなりこれ舊藩時代の風習今尚ほ残れるか又は風土病■冒されし結果なるか予之れに就いて餘り深くを研むる所なし田舎の人は今に舊風あり殊に
婦人にて可笑しきは四ヶに來るには必ず眞黑の上着をかけることなり彼等はこれを以て最々上等のものを思ふにや又は藩制舊儀の然らしむる處かこれ又余かしる處にあらさつなり
いつもの家も一番座の床の間に(家の都合により二番座にある處もあり)家族は勿論分家せし近親の元共迄の生靈を祭るとて其人数に應じて香爐と茶碗を備へ毎日舊の朔日十五日に祭りなり(例へば家族四人に分家二人あらば六人分即ち香爐六個に茶碗六枚なり)この床の間が祖先を祭る神壇より尊しをいふこれ死靈の冥福を祈るためならしむ
敎育は年一年進歩せりというふ四ヶには八重山高等、大川尋常の二校あり今は一人の校長にてこれを監督せり就學兒童多く従つて教室挟隘を告ぐる爲め尋常科は十有余の仮敎室にて漸し授業をなしつつあり
成人の話によれば四十年度には校舍新築のため各村より材木を寄附せしめ己に敷地までも選定せりといふ同郡敎育の爲めに大に慶賀すべき事なり一日も早く完成を待つ
目下八重山司は殖產興業に熱注せられつある由遇ふ人見る人毎に近頃は其の話のみなりとぞ只今は那覇、宮古、などの織物組合規則など取り寄せられて仝郡にも此の組合を設けむとの計画なりといふ仝島自司の腕前を振はるるは今后のとならんか
右の外四ケに付ては書くべきこと數多あれど今度は先づこれ丈にして他日又書くことにせん
現代仮名遣い表記
◎思はぬ旅行
(二月六日の続き) 多良間の 仲松生
ここよりは、石垣島四ヶ(大川、登野城、石垣、新川、四ケ村の総称)の状況並に其の近きあたりの見し事聞しことを、物につき筆のゆくままをざと記さんとす石垣島は八重山郡中最北部に位置し、其の南より西北にかけて黒島、新城、竹富、小浜、西表の島々飛石の如く羅列せり。そが中にて石垣、西表の二島いと大なり、其他の島々は略々相似たり。竹富、小浜の二島は石垣島に近く、毎日くり舟にて日用品は石垣島に仰げり。其の距離僅かに三四海里内外なるべし。
仰々四ヶは、八重山郡島中第一繁華なる処にして石垣島の南端にあり。道路平坦にして概ね砂土よりなれり、さればいかなる大雨にても泥に塗ること少し。松林一つ隔てて東に平得、真栄里の二ヶ村あり、丘一つ越えれば北に名蔵村あり、一里ばかりの西には観音堂あり。南は石垣湾に臨む東西に長く、南北に短く恰も蛞蝓の外形に稍々似たり。東は登野城、其の西は大川又其西は石垣にして、新川は最西に位し共に相接せり。大川、石垣の両村は中央にある丈それ丈賑わしく、商業の盛なるも此の二ヶ村に限れり。商人は首里那覇の人々多く、内地の人少し、此等は皆四ヶの南海岸に商店を構え種々の雑貨を売買せり。中にも古賀の卸商濱崎の雑貨商は、全島の主脳なるべし。
毎月五六回は汽船出入せり、左程不便は感ぜざる様なり。就中海底電線のある為には大に便利を得たり、石垣港は底浅く従って気船の淀繁場大に遠し、島民大に奮発して港内の修築に力を尽くすべき事ならずや。
艀舩の杉製にして丈夫なるは実に県下第一なり、八重山にゆく人の一番目につくは盖しこれなるべし。(他府県人)はイザ知らず、四ヶの南端浜の上に糸満人の住家数戸ありて、第二の糸満村の観をなせり。彼等は皆妻子を引き越し来て、漁業に従事せり。毎日市場に揚る魚介類はこれ悉く彼等が捕獲にかかる者にして、島民の手より出でしもの一つもなし。実に嘆わしきの至りならずや、起てよ八重山島民、天与の宝庫無尽蔵の宝を彼等に蹂躙せしむるなかれ。
島民は美的思想梢々発達せり、其証拠には庭飾りなどに築山あり、溌剌たる金魚や鮎の浮べる池あり、花卉あり、蘇鉄あり、以て一般の思想界を察するに余りあるべし。辺島だけありて道ゆく人の悠々閑々なるは人の目につく一つなり、これ旧藩時代の風習今尚ほ残れるか又は風土病■冐されし結果なるか、予之れに就いて余り深くを研むる所なし。田舎の人は今に旧風あり、殊に婦人にて可笑しきは、四ヶに来るには必ず真黒の上着をかけることなり。彼等はこれを以て最々上等のものを思ふにや、又は藩制旧儀の然らしむる処か、これ又余かしる処にあらざるなり。
いづれの家も一番座の床の間に(家の都合により二番座にある処もあり)家族は勿論、分家せし近親の者共迄の生霊を祭るとて、其人数に応じて香炉と茶碗を備へ毎日旧の朔日十五日に祭るなり(例へば家族四人に分家二人あらば六人分即ち香炉六個に茶碗六枚なり)、この床の間が祖先を祭る神壇より尊しという、これ死霊の冥福を祈るためならしむ。
教育は年一年進歩せりという四ヶには八重山高等、大川尋常の二校あり。今は一人の校長にてこれを監督せり、就学児童多く従って教室狭隘を告ぐる為め、尋常科は十有余の仮教室にて漸く授業をなしつつあり。成人の話によれば、四十年度には校舎新築のため各村より材木を寄附せしめ、巳に敷地までも選定せりという。同郡教育の為めに大に慶賀すべき事なり、一日も早く完成を待つ。
目下八重山島司は殖産興業に熱注せられつつある由、遇ふ人見る人毎に近頃は其の話のみなりとぞ、只今は那覇、宮古などの織物組合規則など取り寄せられて、同郡にも此の組合を設けんとの計画なりという。同島司の腕前を振はるるは、今后のとならんか。
右の外、四ヶに付ては書くべきこと数多あれど、今度は先づこれ丈にして他日又書くことにせん。