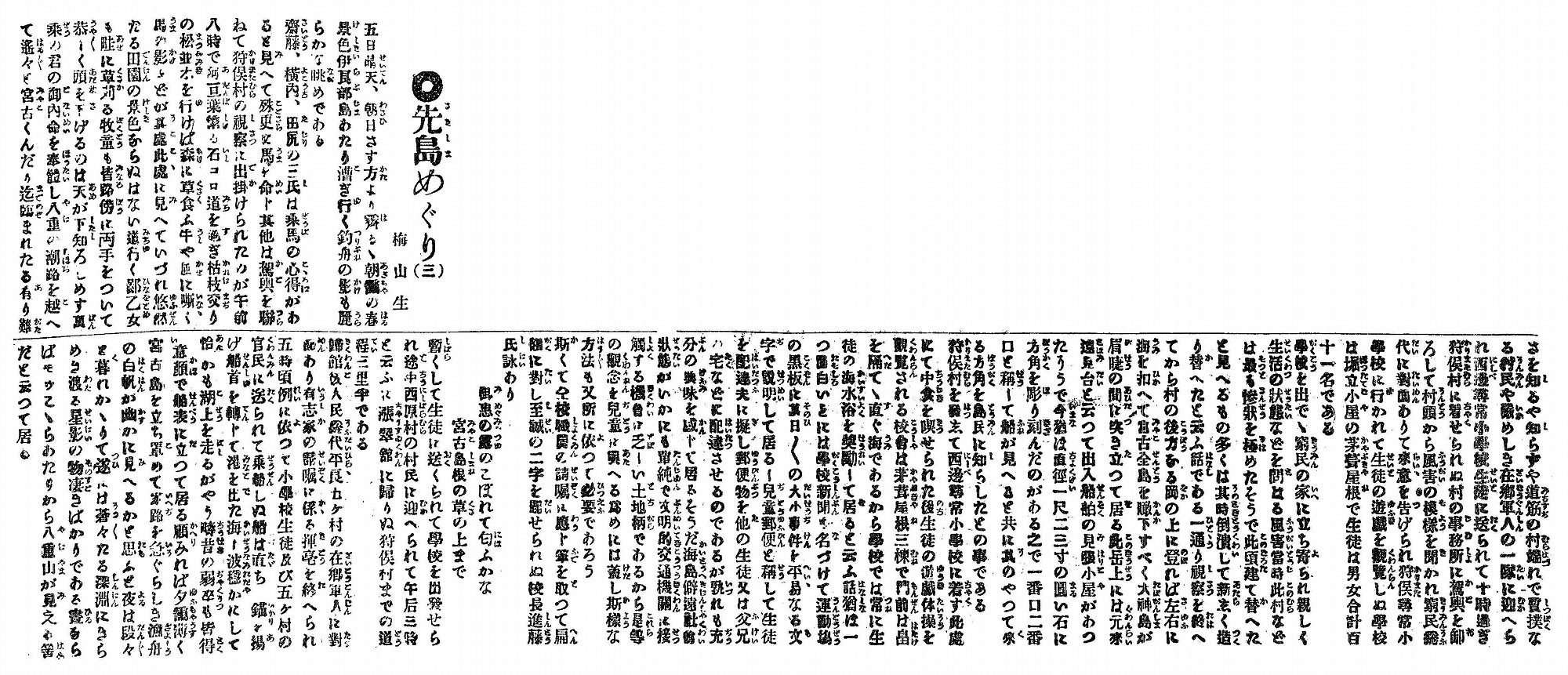キーワード検索
◎先島めぐり(三)
原文表記
◎先島めぐり(三)
梅山生
五日晴天、朝日さす方より霽るヽ朝靄の春景色伊良部島あたり漕ぎ行く釣舟の影も麗らかな眺めである
齋藤、横内、田尻の三氏は乗馬の心得があると見へて殊更に馬を命じ其他は駕輿を聯て狩俣村の視察に出掛けられたのが午前八時で阿旦葉繁る石コロ道を過ぎ枯枝交りの松並木を行けば森に草食ふ牛や風に嘶く馬の影などが其處此處に見へていづれ悠然たる田園の景色ならぬはない道行く鄙乙女も畦に草刈る牧童も皆路傍に両手をついて恭しく頭を下げるのは天が下知ろしめす萬乘の君の御内命を奉體し八重の潮路を越へて遥々宮古くんだり迄臨まれたる有り難さを知るや知らずや道筋の村端れで質撲なる村民や厳めしき在郷軍人の一隊に迎へられ西邊尋常小學校生徒に送られて十時過ぎ狩俣村に着せられぬ村の事務所に駕輿を卸して村頭から風害の模樣を聞かれ窮民総代に對面ありて來意を告げられ狩俣尋常小學校に行かれて生徒の遊戯を観覧しぬ學校は掘立小屋の茅葺屋根で生徒は男女合計百十一名である
學校を出でヽ窮民の家に立ち寄られ親しく生活の状態などを問はる風害當時此村などは最も惨状を極めたそうで此頃建て替へたと見へるもの多くは其時倒潰して新しく造り変へたと云ふ話である一通り視察を終へてから村の後方なる岡の上に登れば左右に海を扣へて宮古全島を瞰下すべく大神島が眉睫の間に突き立つて居る此岳上には元來遠見台と云つて出入船舶の見張小屋があつたそうで今猶ほ直徑一尺二三寸の圓い石に方角を彫り刻んだのがある之で一番口二番口と稱して船が見えると共に其のやつて來る方角を島民に知らしたとの事である
狩俣村を發して西邊尋常小學校に着す此處にて中食を喫せられた後生徒の遊戯体操を観覧される校舎は茅葺屋根三棟で門前は畠を隔てヽ直ぐ海であるから學校では常に生徒の海水浴を奬勵して居ると云ふ話猶ほ一つ面白いことには學校新聞■名づけて運動塲の黒板に其日其日の大小事件を平易なる文字で説明して居る■兒童郵便と稱して生徒を配達夫に擬し郵便物を他の生徒又は父兄の宅などに配達させるのであるが孰れも充分の興味を感じて居るそうだ海島僻遠社會状態がいかにも單純で文明的交通機關に接觸する機會に乏しい土地柄であるから是等の觀念を兒童に與える爲めには蓋し斯樣な方法も又所に依つて必要であろう
斯くて仝校職員の請嘱に應じ筆を取つて扁額に對し至誠の二字を題せられぬ校長進藤氏詠あり
御恵の露のこぼれて匂ふかな
宮古島根の草の上まで
暫くして生徒に送られて學校を出發せられ途中西原村の村民に迎へられて午后三時と云ふに漲翠舘に歸りぬ狩俣村までの道程三里半である
歸館後人民総代平良五ヶ村在郷軍人に對面あり有志家の請嘱に係る揮毫を終へられ五時頃例に依つて小學校生徒及び五ヶ村の官民に送られて乗船しぬ船は直ち 錨を挙げ船首を轉じて港を出た海上波穏かにして恰も湖上を走るがやう■昔の弱卒も皆得意顔で船表に立つて居る顧みれば夕靄薄く宮古島を立ち罩めて家路を急ぐらしき漁舟の白帆が幽かに見へるかと思ふと夜は段々と暮れかヽりて遂には蒼々たる深淵にきらめき渡る星影の物凄きばかりである晝ならばモウこヽらあたりから八重山が見える筈だと云つて居る
現代仮名遣い表記
◎先島めぐり(三)
梅山生
五日晴天、朝日さす方より霽るヽ朝靄の春景色。伊良部島あたり漕ぎ行く釣舟の影も麗らかな眺めである。
斎藤、横内、田尻の三氏は乗馬の心得があると見えて殊更に馬を命じ、其他は駕輿(かご)をつらねて狩俣村の視察に出掛けられたのが午前八時で、阿旦葉繁る石コロ道を過ぎ枯枝交りの松並木を行けば、森に草食う牛や、風に嘶く馬の影などが其処此処に見えていづれ悠然たる田園の景色ならぬはない。道行く鄙乙女も畦に草刈る牧童も皆、路傍に両手をついて恭しく頭を下げるのは、天が下知ろしめす万乗の君の御内命を奉体し八重の潮路を越へて遥々宮古くんだり迄臨まれたる有り難さを知るや知らずや。道筋の村端れで質撲なる村民や厳めしき在郷軍人の一隊に迎へられ、西辺尋常小学校生徒に送られて十時過ぎ狩俣村に着せられぬ。村の事務所に駕輿(かご)を卸して、村頭から風害の模様を聞かれ窮民総代に対面ありて来意を告げられ、狩俣尋常小学校に行かれて生徒の遊戯を観覧しぬ。学校は掘立小屋の茅葺屋根で、生徒は男女合計百十一名である。
学校を出でて、窮民の家に立ち寄られ親しく生活の状態などを問はる。風害当時此村などは最も惨状を極めたそうで、此頃建て替えたと見えるもの多くは、其時倒潰して新しく造り変えたと云う話である。一通り視察を終えてから村の後方なる岡の上に登れば、左右に海をひかえて宮古全島を瞰下すべく大神島が眉睫の間に突き立って居る。此岳上には元来遠見台と云って出入船舶の見張小屋があったそうで、今猶ほ直径一尺二三寸の円い石に方角を彫り刻んだのがある。之で一番口二番口と称して、船が見えると共に其のやって来る方角を島民に知らせたとの事である。
狩俣村を発して西辺尋常小学校に着す。此処にて中食を喫せられた後、生徒の遊戯体操を観覧される。校舎は茅葺屋根三棟で、門前は畠を隔てて直ぐ海であるから、学校では常に生徒の海水浴を奨励して居ると云う話。なほ一つ面白いことには、学校新聞■名づけて運動場の黒板に其日其日の大小事件を平易なる文字で説明して居る。■児童郵便と称して生徒を配達夫に擬し、郵便物を他の生徒又は父兄の宅などに配達させるのであるが孰れも充分の興味を感じて居るそうだ。海島僻遠社会状態がいかにも単純で文明的交通機関に接触する機会に乏しい土地柄であるから、是等の観念を児童に与える為めには確かに斯様な方法も又所に依って必要であろう。
斯くて同校職員の請嘱に応じ、筆を取って扁額に対し至誠の二字を題せられぬ。校長進藤氏詠あり
御恵の露のこぼれて匂ふかな
宮古島根の草の上まで
しばらくして生徒に送られて学校を出発せられ、途中西原村の村民に迎へられて午後三時と云うに漲翠舘に帰りぬ。狩俣村までの道程三里半である。
帰館後、人民総代平良五ヶ村在郷軍人に対面あり。有志家の請嘱に係る揮毫を終へられ、五時頃例に依って小学校生徒及び五ヶ村の官民に送られて乗船しぬ。船は直ち 錨を挙げ、船首を転じて港を出た。海上波穏かにしてあたかも湖上を走るがよう、■昔の弱卒も皆得意顔で船表に立って居る。顧みれば夕靄薄く宮古島を立ちこめて、家路を急ぐらしき漁舟の白帆が幽かに見えるかと思うと、夜は段々と暮れかかりて遂には蒼々たる深淵にきらめき渡る星影の物凄きばかりである。昼ならばモウここらあたりから八重山が見える筈だ、と云って居る。