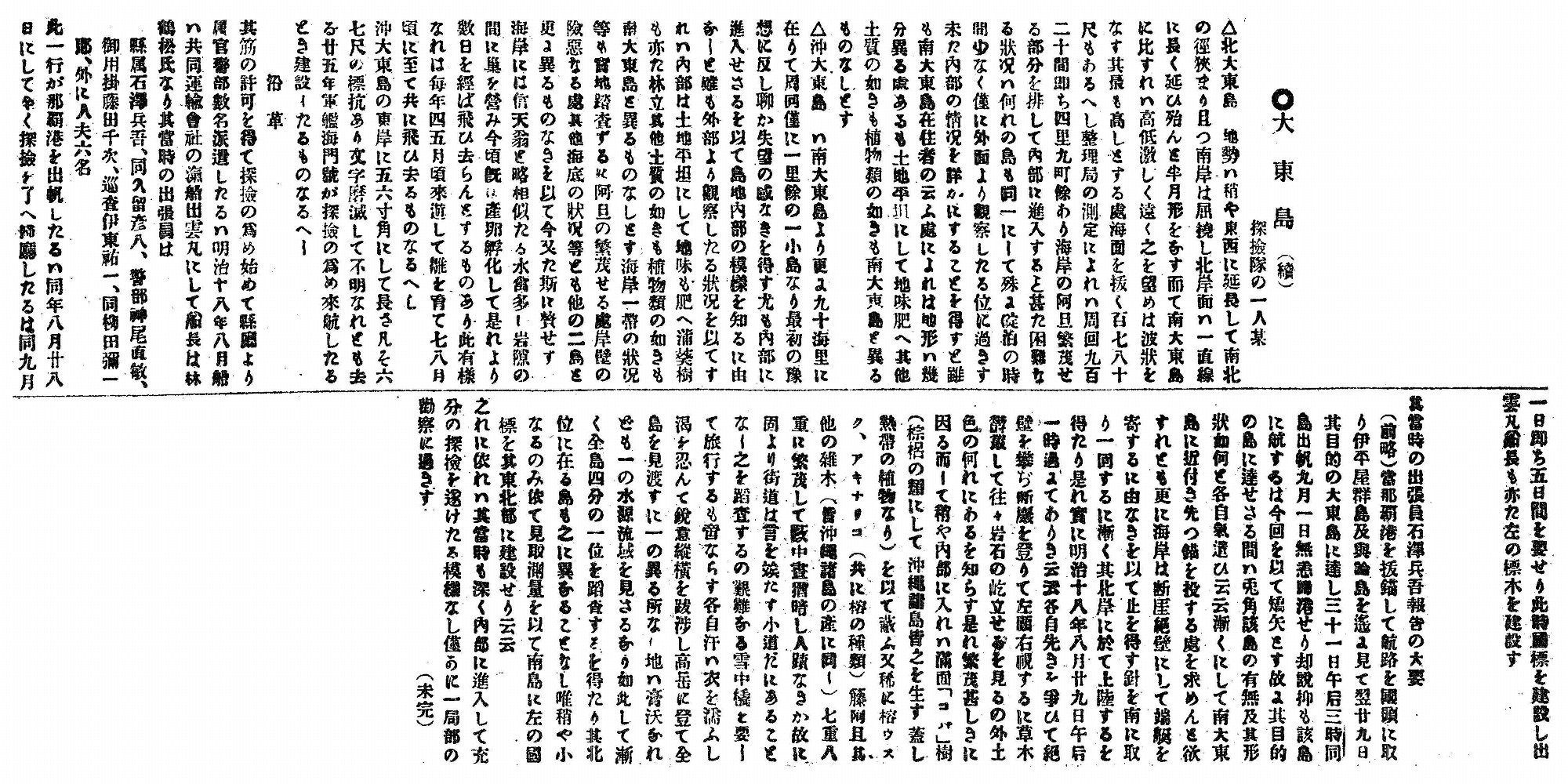キーワード検索
◎大東島(續)
原文表記
◎大東島(續)
探撿隊の一人某
△北大東島 地勢は稍や東西に延長して南北の徑猍まり且つ南岸は屈撓し北岸面は一直線に長く延ひ殆んと半月形をなす而て南大東島に比すれは高低激しく遠く之を望めは波狀をなす其最も高しとする處海面を■く百七八十尺もあるへし整理局の測定によれは周回九百二十間即ち四里九町餘あり海岸の阿旦繁茂せる部分を拝して内部に進入すること甚た困難なる狀况は何れの島も同一にして殊に碇泊の時間少なく僅に外面より觀察したる位に過きす未た内部の情况を詳かにすることを得すと雖も南大東島在住者の云ふ處によれは地形は幾分異る處あるも土地平坦にして地味肥へ其他土質の如きも植物類の如きも南大東島と異るものとなしとす
△沖大東島 ハ南大東島より更に九十海里に在りて周回僅に一里餘の一小島なり最初の豫想に反し聊か失望の感なきを得す尤も内部に進入させるを以て島地内部の模樣を知るに由なしと雖も外部より觀察したる狀况を以てすれは内部は土地平坦にして地味も肥へ蒲葵樹も亦た林立其他土質の如きも植物類の如きも南大東島と異るものなしとす海岸一帶の狀况等も實地踏査するに阿旦の繁茂せる處岸壁の險惡なる處其他海底の狀况等とも他の二島と更に異るものなきを以て今又た斯に賛せす
海岸には信天翁と略相似たる水禽多し岩隙の間に巢を營み今頃既■產卵孵化して是れより數日を經ば飛ひ去らんとするものあり此有樣なれは毎年四五月頃來遊して雛を育て七八月頃に至て飛ひ去るものなるへし
沖大東島の東岸に五六寸角にして長さ凡そ六七尺の標杭あり文字磨烕して不明なれとも去る廿五年軍艦海門號が探撿の爲め來航したるとき建設したるものなるへし
沿 革
其筋の許可を得て探撿の爲め始めて縣廳より属官警部數名派遣したるは明治十八年八月船は共同運輸會社の滊船出雲凡にして船長は林鶴松氏なり其當時の出張員は
縣属石澤兵吾、同久留彦八、警部神尾直敏、 御用掛藤田千次、巡査伊東裕一、同柳田彌一■、外に人夫六名
此一行が那覇港を出帆したるは同年八月廿八日にして■く探撿を了へ歸廳したるは同九月一日即ち五日間を要せり此時目標を建設し出雲丸船長も亦た左の標木を建設す
其當時の出張石澤兵吾報告の大要
(前略)當那覇港を抜錨して航路國頭に取り伊平屋群島及輿論島を遙にみて翌廿九日其目的の大東島に達し三十一日午后三時同島出帆九月一日無患歸港せり却說抑も該島に航するは今回を以て矯矢とする故に其目的の島に達せさる間は兎角該島の有無及其形狀如何と各自氣遣ひ云云漸くにして南大東島に近付き先つ錨を投する處を求めんと欲すれとも更に海岸は断崖絕壁にして端艇を寄するに由なきを以て止を得す針を南に取り一回するに漸く其北岸に於て上陸するを得たり是れ實に明治十八年八月廿九日午后一時過にてありき云云各自先きを爭ひて絕壁を攀ぢ断■を登りて左顧右視するに草木爵■して往々岩石の屹立せるを見るの外土色の何れにあるを知らす是れ繁茂甚しきに因る而して稍や内部に入れは滿面「コバ」樹(棕梠の類にして沖繩諸島皆之を生す蓋し熱帶の植物なり)を以て獘ふ又稀に榕ウスク、アキナ■コ(共に榕の種類)籐阿且其他の雜木(■沖繩諸島の產に同し)七重八重に繁茂して■中畫猶暗し人蹟なきか故に固より街道は言を■たす小道だにあることなし之を踏査するの艱難なる雪中橋を要して旅行するも啻ならす各自汗は衣を濡ふし渇を忍んて銳意縱横を跋渉し高岳に登て全島を見渡すに一の異る所な■地は膏沃なれども一の水源流域を見さるなり如此して漸く全島四分の一位を踏査するを得たり其北位に在る島も之に異なることなし唯稍や小なるのみ依て見取測量を以て南島に左の國標を其東北部に建設せり云云
之に依れは其當時も深く内部に進入して充分の探撿を遂けたる模様なし僅かに一局部の勸察に過きす(未完)
現代仮名遣い表記
◎大東島(続)
探険隊の一人某
△北大東島 地勢は稍や東西に延長して南北の径猍まり且つ南岸は、屈撓し北岸面は一直線に長く延び、殆んと半月形をなす。しかして南大東島に比すれば、高低激しく遠く之を望めば波状をなす。其最も高しとする処海面を抜く百七八十尺もあるへし整理局の測定によれば、周回九百二十間即ち、四里九町余あり。海岸の阿旦繁茂せる部分を拝して内部に進入すること、甚だ困難なる状況は何れの島も同一にして、殊に碇泊の時間少なく僅に外面より観察したる位に過きず。未た内部の情況を詳かにすることを得すと、雖も南大東島在住者の云う処によれば、地形は幾分異る処あるも、土地平坦にして地味肥え其他土質の如きも、植物類の如きも南大東島と異るものとなしとす。
△沖大東島 は南大東島より更に九十海里に在りて、周回僅に一里余の一小島なり。最初の予想に反し聊か失望の感なきを得す、もっとも内部に進入させるを以て島地内部の模様を知るに由なしと、雖も外部より観察したる状況を以てすれば、内部は土地平坦にして地味も肥え、蒲葵樹も亦た林立。其他土質の如きも、植物類の如きも南大東島と異るものなしとす。海岸一帯の状況等も実地踏査するに、阿旦の繁茂せる処岸壁の険悪なる処、其他海底の状況等とも他の二島と更に異るものなきを以て今又た斯に賛せす。
海岸には信天翁と略相似たる水禽多し、岩隙の間に巣を営み今頃既■産卵孵化して、是れより数日を経ば飛び去らんとするものあり。此有様なれば毎年四五月頃来遊して雛を育て、七八月頃に至て飛び去るものなるべし。
沖大東島の東岸に、五六寸角にして長さ凡そ六七尺の標杭あり。文字磨滅して不明なれとも、去る二十五年軍艦海門号が探険の為め来航したるとき建設したるものなるべし。
沿 革
其筋の許可を得て探険の為め、始めて県庁より属官警部数名派遣したるは、明治十八年八月、船は共同運輸会社の汽船出雲凡にして船長は林鶴松氏なり。其当時の出張員は
県属石沢兵吾、同久留彦八、警部神尾直敏、 御用掛藤田千次、巡査伊東裕一、同柳田弥一■、外に人夫六名
此一行が那覇港を出帆したるは同年八月二十八日にして、■く探険を了へ帰庁したるは同九月一日即ち五日間を要せり。此時目標を建設し出雲丸船長も亦た左の標木を建設す。
其当時の出張石沢兵吾報告の大要
(前略)当那覇港を抜錨して航路国頭に取り、伊平屋群島及与論島を遥にみて。翌二十九日其目的の大東島に達し、三十一日午後三時同島出帆九月一日無患帰港せり。却説抑も該島に航するは今回を以て矯矢とする、故に其目的の島に達せさる間は、兎角該島の有無及其形状如。何と各自気遣い云云漸くにして、南大東島に近付き先つ錨を投する処を求めんと欲すれとも、更に海岸は断崖絶壁にして端艇を寄するに、由なきを以て止を得す。針を南に取り一回するに漸く其北岸に於て上陸するを得たり、是れ実に明治十八年八月二十九日午後一時過にてありき。云云各自先きを争いて絶壁を攀ぢ断■を登りて、左顧右視するに草木爵■して往々岩石の■屹立せるを見るの、外土色の何れにあるを知らす。是れ繁茂甚しきに因るしかしして、稍や内部に入れは満面「コバ」樹(棕梠の類にして沖縄諸島皆之を生す。蓋し熱帯の植物なり)を以て弊ふ、又稀に榕ウスク、アキナ■コ(共に榕の種類)籐阿且其他の雑木(■沖縄諸島の産に同し)七重八重に繁茂して、■中画猶暗し。人跡なきか故に固より街道は言を竢たす小道だにあることなし、之を踏査するの艱難なる雪中橋を要して旅行するも啻ならず。各自汗は衣を濡うし、渇を忍んて鋭意縦横を跋渉し高岳に登て、全島を見渡すに一の異る所な■。地は膏沃なれども一の水源流域を見さるなり、如此して漸く全島四分の一位を踏査するを得たり。其北位に在る島も之に異なることなし、唯稍や小なるのみ依て、見取測量を以て南島に左の国標を其東北部に建設せり云云。
之に依れは其当時も深く内部に進入して、充分の探険を遂げたる模様なし。僅かに一局部の観察に過きず(未完)