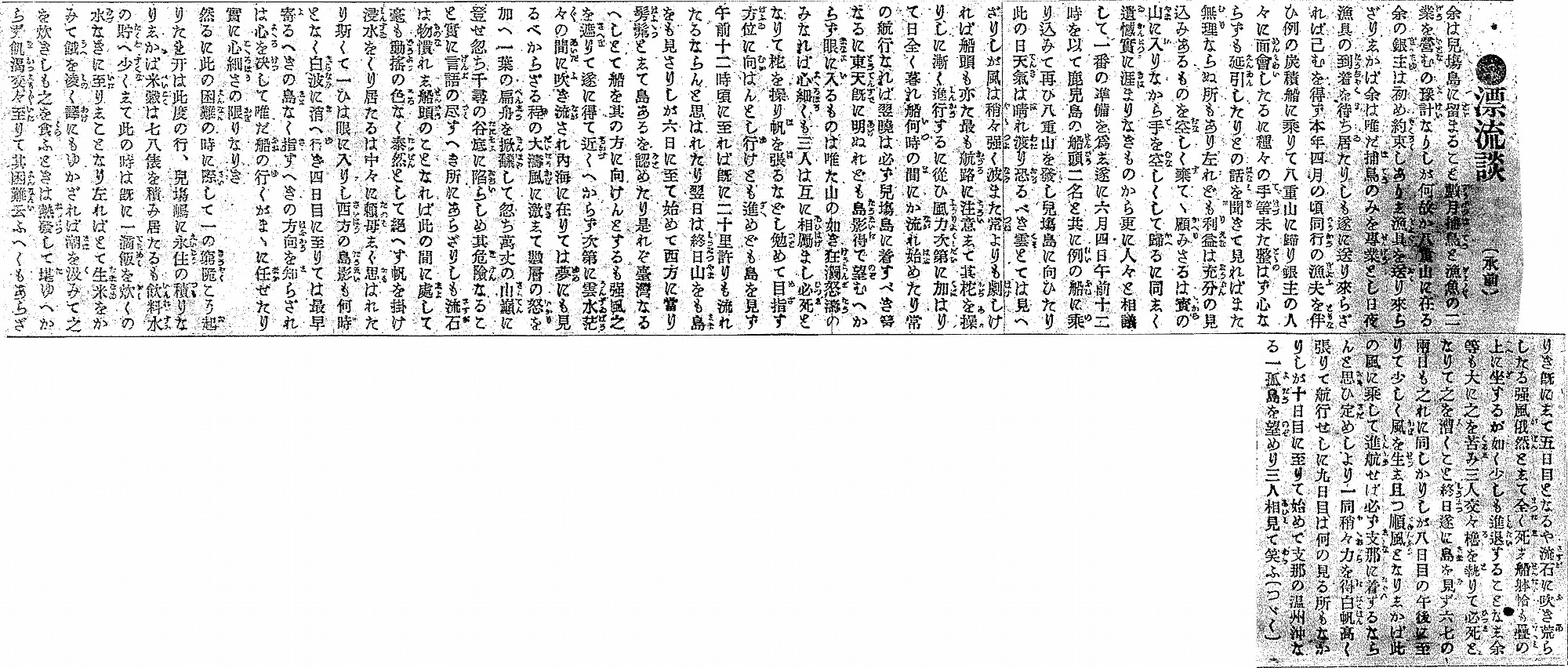キーワード検索
●漂流談
原文表記
●漂流談(承前)
余は兒塲島に留まること數月捕鳥と漁魚の二業を營むの豫計なりしが何故か八重山に在る余の銀主は初め約束しありし漁具を送り來らざりしかば余は唯だ捕鳥のみを專業とし日夜漁具の到着を待ち居たりしも遂に送り來らざれば己むを得ず本年四月の頃同行の漁夫を伴ひ例の炭積船に乘りて八重山に歸り銀主の人々に面會したるに種々の手筈末た整はず心ならずも延引したりとの話を聞きて見ればまた無理ならぬ所もあり左れども利益は充分の見込みあるものを空しく棄てヽ顧みさるは賓の山に入りなから手を空しくして歸るに同しく遺憾實に涯まりなきものから更に人々と相議して一番の準備を爲し遂に六月四日午前十二時を以て鹿兒島の船頭二名と共に例の船に乘り込みて再ひ八重山を発し兒塲島に向ひたり此の日天氣は晴れ渡り恐るべき雲とては見へざりしが風は稍々强く波また常よりも劇しければ船頭も亦た最も航路に注意して其柁を操りしに漸く進行するに從ひ風力次第に加はりて日全く暮れ船何時の間にか流れ始めたり常の航行なれば翌曉は必ず兒塲島に着すべき筈なるに東天既に明ぬれども島影得て望むへからず眼に入るものは唯た山の如き狂瀾怒濤のみなれば心細くも三人は互に相勵まし必死となりて柁を操り帆を張るなどし勉めて目指す方位に向はんとし行けとも進めども島そ見ず午前十二時頃に至れば既に二十里許りも流れたるならんと思はれたり翌日は終日山をも島をも見さりしが六日に至て始めて西方に當り髣髴として島あるを認めたり是れぞ臺灣なるへしとて船を其の方に向けんとするも强風之を遮りて遂に得て近くへからず次第に雲水茫々の間に吹き流され内海に在りては夢にも見るべからざる程の大濤風に激して數層の怒を加へ一葉の扁舟を掀飜して忽ち萬丈の山巓に登せ忽ち千尋の谷底に陥らしめ其危險なること實に言語の尽すへき所にあらざりしも流石は物慣れし船頭のことなれば此の間に處して亳も動揺の色なく泰然として絶えす帆を掛け浸水をくり居たるは中々に賴母しく思はれたり斯くて一ひは眼に入りし西方の島影も何時となく白波に消へ行き四日目に至りては最早寄るへきの島なく指すへきの方向を知らざれは心を決して唯だ船の行くがまヽに任せたり實に心細さの限りなりき
然るに此の困難の時に際して一の窮陒こう起りたれ并は此度の行、兒塲嶋に永住の積りなりしかは米穀は七八俵を積み至たるも飲料水の貯へ少くして此の時は既に一滴飯を炊くの水なきに至りしことなり左ればとて生米をかみて飢を凌く譯にもゆかざれば潮を汲みて之を炊きしも之を食ふときは熱發して堪ゆへからず飢渇交々至りて其困難云ふへくもあらざりき既にして五日目となるや流石に吹き荒らしたる强風俄然として全く死■船躰恰も疊の上に坐するが如く少しも進退することなし余等も大に之を苦み三人交々櫓を執りて必死となりて之を漕くこと終日遂に島を見ず六七の兩日も之れに同しかりしが八日目の午後に至りて少しく風を生し且つ順風となりしかは此の風に乘して進航せば必ず支那に着するならんと思ひ定めしより一同稍々力を得白帆高く張りて航行せしに九日目は何の見る所もなかりしが十日目に至りて始めて支那の溫州冲なる一孤島を望めり三人相見て笑ふ(つヾく)
現代仮名遣い表記
●漂流談(承前)
余は児塲島に留まること数月捕鳥と漁魚の二業を営むの予計なりしが、何故か八重山に在る余の銀主は初め約束しありし漁具を送り来らざりしかば余は唯だ捕鳥のみを専業とし日夜漁具の到着を待ち居たりしも遂に送り来らざれば己むを得ず本年四月の頃同行の漁夫を伴ひ例の炭積船に乗りて八重山に帰り銀主の人々に面会したるに種々の手筈末た整はず心ならずも延引したりとの話を聞きて見ればまた無理ならぬ所もあり左れども利益は充分の見込みあるものを空しく棄てて顧みさるは賓の山に入りなから手を空しくして帰るに同しく遺憾実に涯まりなきものから更に人々と相議して一番の準備を為し遂に六月四日午前十二時を以て鹿児島の船頭二名と共に例の船に乗り込みて再ひ八重山を発し児塲島に向ひたり此の日天気は晴れ渡り恐るべき雲とては見へざりしが風は稍々強く波また常よりも劇しければ船頭も亦た最も航路に注意して其柁を操りしに漸く進行するに従ひ風力次第に加はりて日全く暮れ船何時の間にか流れ始めたり常の航行なれば翌暁は必ず児塲島に着すべき筈なるに東天既に明ぬれども島影得て望むへからず眼に入るものは唯た山の如き狂瀾怒濤のみなれば心細くも三人は互に相励まし必死となりて柁を操り帆を張るなどし勉めて目指す方位に向はんとし行けとも進めども島そ見ず午前十二時頃に至れば既に二十里許りも流れたるならんと思はれたり翌日は終日山をも島をも見さりしが六日に至て始めて西方に当り髣髴として島あるを認めたり是れぞ台湾なるへしとて船を其の方に向けんとするも強風之を遮りて遂に得て近くへからず次第に雲水茫々の間に吹き流され内海に在りては夢にも見るべからざる程の大濤風に激して数層の怒を加へ一葉の扁舟を掀翻して忽ち万丈の山巓に登せ忽ち千尋の谷底に陥らしめ其危険なること実に言語の尽すへき所にあらざりしも流石は物慣れし船頭のことなれば此の間に処して亳も動揺の色なく泰然として絶えす帆を掛け浸水をくり居たるは中々に頼母しく思はれたり斯くて一ひは眼に入りし西方の島影も何時となく白波に消へ行き四日目に至りては最早寄るへきの島なく指すへきの方向を知らざれは心を決して唯だ船の行くがままに任せたり実に心細さの限りなりき。
然るに此の困難の時に際して一の窮陒こう起りたれ并は此度の行、児塲嶋に永住の積りなりしかは米穀は七八俵を積み至たるも飲料水の貯へ少くして此の時は既に一滴飯を炊くの水なきに至りしことなり左ればとて生米をかみて飢を凌く訳にもゆかざれば、潮を汲みて之を炊きしも之を食ふときは熱発して堪ゆへからず飢渇交々至りて其困難云ふへくもあらざりき既にして五日目となるや流石に吹き荒らしたる強風俄然として全く死■船躰恰も畳の上に坐するが如く少しも進退することなし余等も大に之を苦み三人交々櫓を執りて必死となりて之を漕くこと終日遂に島を見ず六七の両日も之れに同しかりしが、八日目の午後に至りて少しく風を生し且つ順風となりしかは此の風に乗して進航せば必ず支那に着するならんと思ひ定めしより一同稍々力を得白帆高く張りて航行せしに九日目は何の見る所もなかりしが十日目に至りて始めて支那の温州冲なる一孤島を望めり三人相見て笑ふ(つづく)