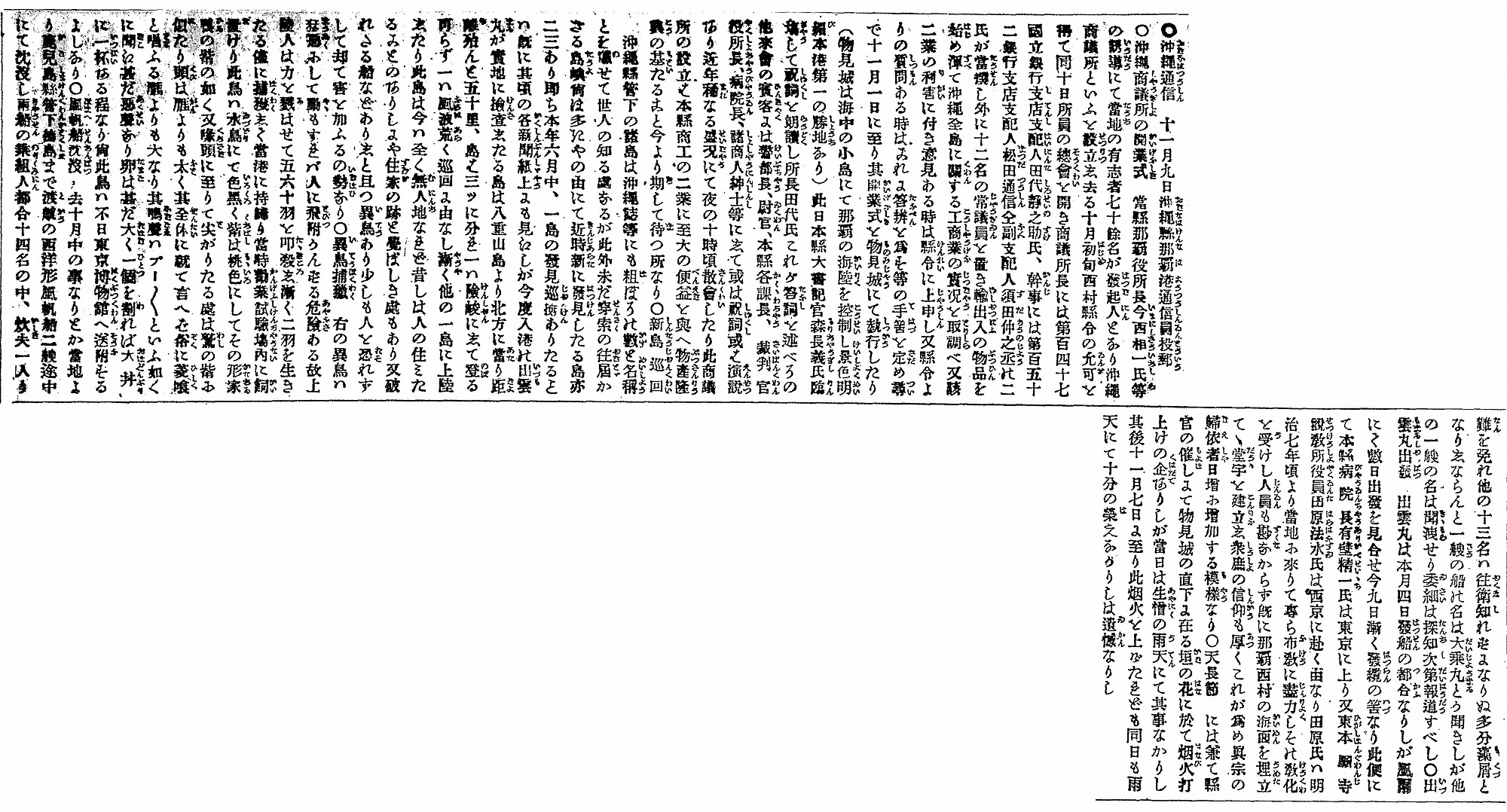キーワード検索
◎沖繩通信 十一月九日沖縄縣那覇港通信員投郵
原文表記
◎沖繩通信 十一月九日沖繩縣那覇港通信員投郵
○沖繩商議所の開業式 當縣那覇役所長今西相一氏等の誘導にて當地の有志者七十餘名が發起人となり沖繩商議所といふを設立志去る十月初旬西村縣令の允可を得て同十日所員の總會を開き商議所長には第百四十七國立銀行支店支配人田代靜之助氏、幹事には第百五十二銀行支店支配人松田通信仝副支配人須田仲之丞の二氏が當撰し外に十二名の常議員を置き輸出入の物品を始め渾て沖繩全島に關する工商業の實况を取調べ又該二業の利害に付き意見ある時は縣令に上申し又縣令よりの質問ある時はこれに答辨を爲す等の手筈を定め尋で十一月一日に至り其開業式を物見城にて執行したり(物見城は海中の小島にて那覇の海陸を控制し景色明媚本港第一の勝地なり)此日本縣大書記官森長義氏臨塲して祝詞を朗讀し所長田代氏これが答辞を述べその他來會の賓客には警部長、尉官、本縣各課長、裁判官役所長、病院長、諸商人紳士等に志て或は祝詞或は演說なり近年稀なる盛况にて夜の十時頃散會したり此商議所の設立は本縣商工の二業に至大の便益と與へ物產隆興の基たること今より期して待つ所なり○新島巡回 沖繩縣管下の諸島は沖繩誌等にも粗ぼその數と名稱とを載せて世人の知る處なるが此外未だ穿索の住屆かざる島嶼尙ほ多きやの由にて近時新に發見したる島亦二三あり即ち本年六月中、一島の發見巡撿ありたることハ既に其頃の各新聞紙上にも見えしが今度入港の出雲丸が實地に撿査志たる島は八重山島より北方に當り距離殆んと五十里、島は三ッに分れ一ハ険峻に志て登る■らず一ハ風波荒く巡回に由なし漸く他の一島に上陸志たり此島は今ハ全く無人地なれど昔しは人の住ミたることのありしにや住家の跡と覺ぼしき處もあり又破れたる船などあり志と且つ異鳥あり少しも人を恐れずして却て害と加ふるの勢なり○異鳥捕獵 右の異鳥ハ猛惡にして動もすれバ人に飛附かんずる危險ある故上陸人は力を■はせて五六十羽を叩殺志漸く二羽を生きたる儘に捕獲志て當港に持歸り當時勸業試驗塲内に飼置けり此鳥ハ水鳥にて色黒く觜は桃色にしてその形家鴨の觜の如く又■頭に至りて尖がいたる處は鷲の觜に似たり頭は雁よりも太く其全体に就て言へば俗に菱喰と唱ふる雁よりも大なり其鳴聲ハプープーといふ如くに聞え甚だ惡聲なり卵は甚だ大く一個を割れば大丼に一杯ある程なり尙此鳥ハ不日東京博物舘へ送附するよしなり○■帆船沈沒 去十月中の事なりとか當地より鹿兒島縣管下桜島まで渡航の西洋形風帆船二艘途中にて沈沒し兩船の乗組人都合十四名の中、炊夫一人か難を免れ他の十三名ハ住衛知れずになりぬ多分藻屑となり志ならんと一艘の船の名は大乗丸とか聞きしが他の一艘の名は聞洩せり委細は探知次第報道すべし○出雲丸出發 出雲丸は本月四日發船の都合なりしが風雨にて數日出發を見合せ今九日漸く發纜の筈なり此便にて本縣病院長有壁精一氏は東京に上り又東本願寺說敎所役員田原法水氏は西京に赴く由なり田原氏ハ明治七年頃より當地に來りて專ら布敎に盡力しその敎化を受けし人員も尠なからず既に那覇西村の海面を埋立てゝ堂宇を建立志衆庶の信仰も厚くこれが爲め眞宗の歸依者日增に增加する模樣なり○天長節 には兼て縣官の催しにて物見城の直下に在る垣の花に於て烟火打上げの企ありしが當日は生憎の雨天にて其事なかりし其後十一月七日に至り此烟火を上げたれども同日も雨天にて十分の榮之なかりしは遺憾なりし
現代仮名遣い表記
◎沖縄通信 十一月九日沖縄県那覇港通信員投郵
○沖縄商議所の開業式 当県那覇役所長今西相一氏等の誘導にて当地の有志者七十余名が発起人となり、沖縄商議所というを設立し、去る十月初旬西村県令の允可を得て、同十日所員の総会を開き商議所長には、第百四十七国立銀行支店支配人田代静之助氏、幹事には第百五十二銀行支店支配人松田通信同副支配人須田仲之丞、の二氏が当選し外に十二名の常議員を置き、輸出入の物品を始め渾て沖縄全島に関する工商業の実況を取調べ、又該二業の利害に付き意見ある時は県令に上申し、又県令よりの質問ある時はこれに答弁を為す等の手筈を定め、尋で十一月一日に至りその開業式を物見城にて執行したり。(物見城は海中の小島にて那覇の海陸を控制し景色明媚本港第一の勝地なり)ここ日本県大書記官森長義氏臨場して祝詞を朗読し、所長田代氏これが答辞を述べ、その他来会の賓客には警部長、尉官、本県各課長、裁判官役所長、病院長、諸商人紳士等にして、あるは祝詞、あるは演説なり近年稀なる盛況にて夜の十時頃散会したり。この商議所の設立は本県商工の二業に至大の便益と与へ、物産隆興の基たること今より期して待つ所なり。
○新島巡回 沖縄県管下の諸島は沖縄誌等にも粗ぼその数と名称とを載せて世人の知る処なるが、この外未だ穿索の住届かざる島嶼尚ほ多きやの由にて近時新に発見したる島また二、三あり。即ち本年六月中、一島の発見巡検ありたることは既にその頃の各新聞紙上にも見えしが、今度入港の出雲丸が実地に検査したる島は、八重山島より北方に当り距離殆んど五十里、島は三ッに分れ一は険峻にして登る■らず、一は風波荒く巡回に由なし。漸く他の一島に上陸したりこの島は今は全く無人地なれど、昔しは人の住みたることのありしにや。住家の跡と覚ぼしき所もあり、又破れたる船などありしと且つ異鳥あり。少しも人を恐れずして却て害と加ふるの勢なり
○異鳥捕猟 右の異鳥は猛悪にして動もすれば人に飛附かんずる危険ある故、上陸人は力を■はせて五、六十羽を叩殺し漸く二羽を生きたるままに捕獲して、当港に持帰り当時勧業試験場内に飼置けり。この鳥は水鳥にて色黒く觜は桃色にしてその形、家鴨の觜の如く。又■頭に至りて尖がいたる所は鷲の觜に似たり。頭は雁よりも太く、その全体に就て言へば俗に菱喰と唱ふる雁よりも大なりその鳴声はプープーという如くに聞え、はなはだ悪声なり。卵は、はなはだ大く一個を割れば大丼に一杯ある程なり。尚この鳥は不日東京博物館へ送附するよしなり
○■帆船沈没 去十月中の事なりとか。当地より鹿児島県管下桜島まで渡航の西洋形風帆船二艘途中にて沈没し、両船の乗組人都合十四名の中、炊夫一人が難を免れ他の十三名は住衛知れずになりぬ。多分藻屑となりしならんと。一艘の船の名は大乗丸とか聞きしが、他の一艘の名は聞洩せり委細は探知次第報道すべし。
○出雲丸出発 出雲丸は本月四日発船の都合なりしが、風雨にて数日出発を見合せ今九日漸く発纜の筈なり。この便にて本県病院長有壁精一氏は東京に上り、又東本願寺説教所役員田原法水氏は西京に赴く由なり。田原氏は明治七年頃より当地に来りて専ら布教に尽力し、その教化を受けし人員も少なからず。既に那覇西村の海面を埋立てて堂宇を建立し衆庶の信仰も厚くこれが為め真宗の帰依者日増に増加する模様なり。
○天長節 には兼て県官の催しにて物見城の直下に在る垣の花に於て烟火打上げの企ありしが、当日はあいにくの雨天にてその事なかりしその後十一月七日に至り此烟火を上げたれども同日も雨天にて十分の栄之なかりしは遺憾なりし